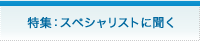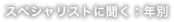香川県立中央病院で昨年、不妊治療を受けていた女性患者に、別の患者のものである可能性のある受精卵が移植され、妊娠判明後に中絶に至るという事故が起こった。この事故の発表後、同院の安全管理体制にはさまざまな問題があったことが明らかになっているが、はたしてこれが特別な事例といえるのだろうか。
日本産科婦人科学会の生殖・内分泌委員会委員、日本生殖補助医療学会の生命倫理委員長などを務める埼玉医科大学の石原理教授(産科婦人科学)に、生殖補助医療施設における安全管理の現状と問題点、今後の課題についてお話を聞いた。
※文中、「不妊治療」は「生殖補助医療」の意味で使用している。ART(ART: Assisted Reproductive Technology)は「生殖補助医療」、AIHは「配偶者間人工授精」(AIH:Artificial Insemination with Husband's semen)を指す。

埼玉医科大学 石原理教授
生殖内分泌学、不妊症治療学、生殖人類学
日本産科婦人科学会産婦人科専門医
日本生殖医学会生殖医療指導医
生殖補助医療の特殊性と普及発展の歴史的経緯
日本の生殖補助医療(ART)の実施施設数は、1985年頃から一直線に増加し、2006年末で530施設に達しています。同年の凍結胚移植(FER)、顕微受精(ICSI)、体外受精(IVF)を合わせた生殖補助医療の総治療周期数は14万近くになっています。
生殖補助医療には、実験的医療にすぎなかったものがわずか数十年の間に完全に一般臨床の標準治療になったという特徴があります。生殖補助医療によって生まれた子どもは世界中で300万人になり、アイスランドでは30人に1人、日本でも年間出生児総数のうち55人に1人、年間2万人近くが何らかの方法による体外受精によって生まれています。
社会的な認識としても、世界初の体外受精児がイギリスで生まれた1978年には宗教的な意味合いを含む反発が強くありましたが、30年たった現在は、一般の人の間でも、生殖補助医療はさまざまな医療の一つという認識に変わってきています。しかし、治療の安全性について、あらゆる観点から検証がすべて済んでいるのかというとそうではありません。直接の理由としては、次々に新技術が生まれ、方法が変化してきたということがあります。
日本では1983年に初めて体外受精児が生まれましたが、日本での生殖補助医療の技術は、自動車産業の技術発展の経緯と似たようなところがあります。最初は海外からの技術移転、次に海外の技術をまねして日本で技術を開発する、その後に日本独自に技術を発展させるという流れです。80年代にはARTはほとんどが海外からの技術移転で、その時点での関心は、いかに外国で行われたことを日本で再現するかということが中心でした。90年代には日本の技術開発が進み、さまざまな試行錯誤が行われたのですが、この時点で安全性の検討が十分行われたかというと必ずしもそうなりませんでした。医療供給側の動機付けとして、医学的な興味、あるいは患者さんの希望をかなえるために何とかしたいという思い入れが強くあったためです。
そして、90年代後半には既に医療器具の改善もなされ、使用する医薬品もほぼ標準形ができました。2000年頃にはパッケージとして不妊治療クリニックが開けるという段階を迎えました。最近では生殖補助医療の経験がほとんどないような産婦人科医が、お産はいろいろ大変だからということで、ビジネスモデルとしての不妊治療クリニックをパッケージで導入して参入する例も出てきています。従来とはかなり違った背景を持つ施設が増えてきているのです。
その間に何が起こったかというと、それを担う医師の質の変化です。90年代までは主に大学病院で治療が行われていたので、大学で研修を受け、生殖補助医療に関係する研究に従事してから臨床現場に出ていくというパターンでしたが、現在では大学で5年学んだら開業しているクリニックの医師として就職し、そこで技術を学んで、自分も開業するという流れができつつあります。そういうシステムの中で、産婦人科医としてあるいは医師として、十分広い知識と倫理的な価値観を持った医師が育つかというと、懸念される部分があると思います。どういう医師をめざすのかというモチベーションが違えば、医療の安全管理のやり方も必然的に違ってくるからです。
患者さんからすれば、どこにいても不妊治療が受けられるから施設数が増えたのはよいという面はありますが、それが安全性の検証の面から見てよいことといえるのかどうかは極めて疑問です。
研究面でも変化が出ています。大学病院にいた医師が相次いで開業し、生殖補助医療を多数施行する大学病院は埼玉医科大、慶応、東大、自治医大の4つしかなくなりました。一方で大きな民間クリニックの中には大学よりもはるかに多くの基礎研究者を抱えて研究を進めているところもあります。大学病院と民間クリニックの研究面でのコラボレーションも必要になってきています。
各学会の医療安全の取り組み
このような中で、生殖補助医療の質と安全の確保が重要な課題とされ、関連学会も自主的な取り組みを進めてきました。
とくに、専門医、指導医を認定する制度が重要であるとの認識から、日本生殖医学会は2003年、関連学会として初めて専門医認定制度を作りました。2007年までで約350人の医師が生殖専門医の認定を受けています。他の学会もこれまで主にやってきたのは、基本的に人を対象にしたものです。ある個人に関して能力、資質、考え方を評価し、認定するというアプローチの仕方です。
しかし、香川県立病院の事故後の動きとして、2009年3月に日本産科婦人科学会は生殖・内分泌委員会に「リスクマネージメント委員会」を作ることになりました。また、日本受精着床学会では従来から医師、看護師、胚培養師(エンブリオロジスト)の生涯研修を行ってきましたが、施設認定の可能性について検討するため「ART施設あり方委員会」を設置しました。
基本的な法的枠組みは既に整備されています。2007年4月1日の医療法改正によって、病院だけでなく診療所、助産所の管理者が医療安全確保のための指針の策定、研修の実施などの措置を行うことが義務付けられました。また、医療法第25 条に基づき、都道府県は原則年1回の立ち入り検査をしなければなりません。しかし、実際にはそのような頻度で、診療所で立ち入り検査が行われているという話はあまり聞きません。
つまり、法的枠組みはできていても、それが正しく運用されていないのです。香川県立病院では普通では考えられないようなことが行われていたのですが、県立であるのに監督を怠っていた県に大きな責任があると考えています。そのことが言われずに、医師の責任だけが追及されるのはおかしな話です。
埼玉医科大学病院の取り組み
埼玉医科大学病院では2000年に抗がん剤投与のミスがあったことをきっかけに、病院としての医療安全に徹底して取り組んできました。病院全体として、医療安全管理指針の整備、診療基本マニュアル策定、医療安全対策委員会および小委員会の活動、日本医療機能評価機構による認定という形で安全の取り組みが行われています。それと同時に産婦人科で取り組んでいることをまとめると、以下のような形になります。
埼玉医科大学産婦人科の安全の取り組み
1)治療を受けるカップルの理解を深めるための教育
- 時間をかけた病態と治療の説明
- 説明に用いる適切な資材・資料の収集と利用
- わかりやすい患者説明文と同意書の整備および適切な運用
2)治療スタッフの継続的な教育とトレーニング
- 定期的症例検討ミーティングによる治療方針などについての意思統一
- 学会、研究会、講習会などへの出席に対する時間的・金銭的援助
- 臨床カンファレンスなどによる問題点の抽出と方針の修正
- 年次統計作成によるデータ集積
- 学会資格取得の援助・支援
3)基本マニュアルの整備
- ARTマニュアルの整備
- AIHマニュアルの整備
4)日常の運用への留意
- 記録と保存の徹底(患者用、紙カルテ用、電子カルテ用、台帳に保存)
- 意志伝達と連絡・報告の徹底
- 責任所在の明確化と危機管理の徹底
香川県の事件を受け、埼玉県から「体外受精についてのマニュアルがあるかどうか」という調査がありました。われわれは生殖医療に特化したマニュアルは作っていなかったので、「胚および配偶子取り扱いにおける本人確認にかかわるARTマニュアル」と「精子取り扱いにおける本人確認にかかわるAIHマニュアル」を作成しました。
マニュアルには、入院時、外来時、採卵時、採精時の本人確認方法が細かく記載されており、採精容器には患者本人に油性マーカーでふた・本体の両方に妻のフルネームを記載してもらい、一日に二人以上の採精があったときは、マーカーの色を変えることや、卵および胚の操作にかかわる器具のすべてに患者のフルネームを記載することなどが明記されています。同時に二人以上の卵・胚・精子を操作しないことや、やむを得ず複数の医師や胚培養士がかかわる場合は責任を明確にすること、記録の管理方法についても明記し、患者本人にも記録を手渡し保管してもらうようにしています。
しかし、問題はマニュアルがあるかどうかではありません。マニュアルは方法であり、目的ではないからです。
当院では本人確認については本人からフルネールを言ってもらう上に、IDカードなどで二重に確認するということが全病院で以前から行われていますし、生殖医療の現場では受精卵の取り違えも当然起こる可能性があるのだから、そうならないための対策をとってきました。しかし、それでもヒューマンエラーをゼロにすることはできません。ミスがあったときに当事者が訴えられても、それは事故の予防に直接つながるものではありません。
事故予防のためにチェックすべきポイントはあくまでも、記録・集積・保管です。たとえば当院では、症例ファイルを作り、治療から妊娠まですべて記録し、空欄があると登録が完了しない仕組みにしています。また、病歴シートも非常に細かく記載するようになっています。
日本産婦人科学会では体外受精・胚移植等の生殖医学の臨床実施に関して、1986年から登録報告制をとり、1993年からは同学会の「診療・研究に関する倫理委員会」がすべての登録施設を対象に治療成績を含む包括的調査を行い、「生殖・内分泌委員会」が一部の協力施設を対象に詳細な調査を行ってきました。そして、2007年以降の治療からは、全対象施設から記録のオンライン登録を導入しています。したがってわれわれも、院内での体外受精や顕微授精を行ったときは、一例ごとに日本産婦人科学会にオンライン登録していきます。
これは、検証することが予防につながると考えるからです。そのためにも段階を踏んで記録し、検証の材料を残すことが重要である、記録・集積・保管をしっかりやるように指導しています。医師教育の役割を持つ大学病院にとっては、システム的に必要なことでもありますから完全な形で行います。
しかし、たとえば技術移転型の施設で安全管理責任者と実施者が同じであるようなところで、記録そのものが確実に行われているかどうかはわかりません。また生殖医療施設が飽和状態にあるために、競争が激しく、アメリカなら1回の治療に150万円かかるところが日本では30〜40万円です。そのしわ寄せで人件費を削減するしかないために人が足りなくなる。そういう状況の中で、全体として安全な医療を行うことが非常に難しくなっているのは事実だと思います。
今後の課題と取り組み
1)法的枠組み
法的な枠組みは、医療法などにより既に整備されており、生殖医療もこの枠組みの中で検討するということが重要です。現状では法的枠組みが運用されていません。機能させるための環境に問題があると考えるべきです。
2)施設要件
日本産婦人科学会は、施設要件について書面審査をしています。この書面は非常に細かく、見取り図で鍵の位置から諸検査器具の位置まで、あるいはそこにかかわる人の履歴書まで提出させています。香川中央病院の場合も医師数やエンブリオロジスト(胚培養士)数を届けており、書類上はパーフェクトでした。しかし、実際にその人たちは中央検査部で働いていてARTには関与していなかったと言われています。では学術団体である日本産婦人科学会がそれを調べられるかというと、それは実際には不可能です。
調査は行政が行うべきだと思います。厚生労働省が2005年から始めた「特定不妊治療費助成事業」では、都道府県、指定都市、中核市が指定医療機関の指定基準を決めています。ここには(1)必要に応じ、現場調査を行い、適当と認めるときに指定書を交付する(2)基準により適正に実施されていることを確認するために、必要に応じて報告の聴取および現地調査を行うことができる--と定められています。
実際に埼玉県の場合、指定書交付にあたっては、私を含め生殖医療指導医数人が、手分けして全施設の現場調査を行いました。そして、空気の清浄度が低いとか、鍵をより厳重なものでなければならないとか、改善要求を出しましたし、必要があれば再度現場調査に行くこともできます。福岡県の話を聞いても、非常に厳しい現場調査があったと聞いています。ところが香川県の場合は、対象施設数が少ないにもかかわらず、県は県立病院にも調査に行っていません。少なくとも調査をしていれば今回のようなとんでもない事件は防げたはずですし、施設の改善要求をして、それが改善されない限り施設認定をすべきではありません。そのために指定が遅れるということになれば、改善するしかなくなります。この制度は始まって間もないため、指定更新のための再調査などの決まりがありませんが、今後はそれが必要だという意見も出てくると思います。そのときにネックになるのが対象施設数です。厚生労働省は法令は出しますが手足がないから、実施するのは地方自治体で、調査を指導医など外部に依頼すれば予算もかかる。そうなると、行政側にやる気があっても、施設数が多い地域でどこまで調査が現実にできるのかということになります。
3)医師・エンブリオロジストの要件
医師については、医師免許に加え、各学会による認定により基本的な要件をチェックすることが可能ですが、今後、より質の高い生殖医療を提供するためにはどうするか。私は生殖医療専門医資格を持つ医師の在籍を義務付ける必要も生じる可能性があると考えています。
エンブリオロジストは現状では農学・獣医学系科学者、臨床検査技師、薬剤師、看護師、その他さまざまな背景を持つ人が従事しており、いくつかの学会などが認定していますが、統一された資格はありません。その人たちに十分な教育と研修の機会が与えられていればそれでよいという考え方もあります。医師が1人、看護師が1人という施設もありますから、統一資格を作り、それを施設要件に組み入れるということになると、現在の生殖医療施設の多くが成り立たなくなる可能性もあります。この点をどうするかは検討していく必要があると思います。
企画・取材:山崎ひろみ