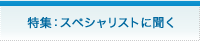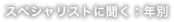厚生労働省は、医薬品の使用により発生する副作用疾患について、平成17年度から、「重篤副作用総合対策事業」に着手している。その中で最初にスタートしたのが、「重篤副作用疾患別マニュアル」(リンク先は医薬品医療機器総合機構)の作成事業である。マニュアルはすでに、10領域にわたりまとめられ厚生労働省のホームページでも公表されているが、最も早く作成されたのが、皮膚領域の疾患を伴うマニュアルである。マニュアル作成にあたった飯島正文・昭和大学病院長(医学部皮膚科教授)にお話を伺った。

飯島 正文氏
副作用の事後対策から予測・予防型への転換
従来の厚生労働省の副作用対策は、医薬品ごとに発生した副作用を収集・評価し、臨床現場に添付文書の改訂などによって注意を促す「警報発信型」「事後対策型」が中心であった。
これを、副作用の発生機序の解明、研究の推進によって、「予測・予防型」対策に転換するというのが「重篤副作用総合対策事業」の目的だ。その事業の第一段階として、4年計画で進められているのがマニュアル作成事業で、重篤度から判断して必要性の高いと考えられる副作用について、早期発見・早期対応することをねらいとしている。
厚生労働省は松本和則・国際医療福祉大学教授を座長に「重篤副作用総合対策検討会」を設け、各疾病領域の関連学会に委託してマニュアル作成委員会を組織してもらい、日本病院薬剤師会とともに、議論を重ねて、順次マニュアルを公表してきた。
日本皮膚科学会がマニュアル作りを提案した理由
飯島教授は「重篤副作用総合対策検討会」メンバーであるとともに、日本皮膚科学会マニュアル作成委員会の委員として、スティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)、中毒性表皮壊死症(TEN)、薬剤性過敏症症候群のマニュアル作成にあたった。
内容について、飯島教授は「これまでは、薬剤ごとに副作用の警告を見ることができましたが、このマニュアルは逆の発想で、どこにどんな症状がある、その原因となる薬剤にはどういうものがある、というかたちで、副作用を調べることができます。そこが大きな違い」と説明する。
このような副作用対策の必要性は、皮膚科では以前から求められていた。
「経緯からいうと、マニュアル作成を厚生労働省から委託されたというより、私たち皮膚科学会の医師のほうから、こうした副作用対策が必要であると提案した、といったほうが近いと思います」と飯島教授は言う。
それには、二つの理由があった。一つは、医療訴訟で医師の司法責任が問われるという事態が各地で起こっていたこと、もう一つは、重篤副作用に苦しむ患者からの「医療従事者がもっと関心を持っていてくれたら、早期診断・早期治療できたはずだ」という訴えを聞いたことだ。
薬剤を適正使用しても一定の割合でSJS/TENは発症する
どんな薬も効果があれば、副作用・副反応があるのは当然のことだ。そして、副作用には原疾患とは異なる臓器で発生するものが少なくない。また、重篤な副作用は発生頻度が非常に低いため、医療従事者によって見逃されがちで、発見が遅れて、患者が危険な状態に陥ることもある。
「皮膚科には重症薬疹の患者さんが来院します。内科や精神科など、別の診療科で処方された薬による薬疹です。その中に、極めてまれに、失明したり、死にいたるような重篤な薬疹があるわけです。皮膚科専門医であれば、診断して治療にかかれますが、患者さん自身も副作用とは気づいていませんから、内科の開業医や皮膚科の病院などを受診した場合、治療が手遅れになることがあります。そのために、医療訴訟が起こり、医師の司法責任が問われる事件が各地で起こってきました」
その契機となったのが、1996年2月に高松高裁が判決を出した、ある医大の中毒性表皮壊死症(TEN)の事例である。
TENとは、全身が広範囲にわたり赤くなり、全身の10%以上にやけどのような水ぶくれ、皮膚のはがれ、ただれなどを起こす皮膚障害だ。高熱、角膜びらん、眼球癒着などの症状を伴う重症の皮膚障害だ。その多くが、医薬品が原因で発症する。特殊な医薬品ではなく、抗生物質、解熱消炎鎮痛薬、消化性潰瘍薬、催眠鎮静薬・抗不安薬、精神神経用薬、緑内障治療薬、高血圧治療薬など、広範囲な医薬品によるアレルギー反応と考えられている。TENの発生頻度は、人口100 万人当たり年間0.4〜1.2 人と報告されている。
TENはスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)と一連の病態と考えられており、TENの症例の多くがSJSの進展型だ。SJSの原因薬剤も抗生物質、解熱消炎鎮痛薬、抗てんかん薬などで、総合感冒薬のような市販の薬の副作用で起こることもある。
この医大の患者の場合は、脳外科で髄膜腫の手術後に投与された抗てんかん薬の副作用として退院後にTENを発症、二つの病院を受診するも原因が特定できず、緊急入院から4日後に死亡。最初の退院からは1か月足らずのできごとだった。この事例では、判決で「退院の際に、何かあればいらっしゃい、と注意しただけで、副作用を念頭に置いた具体的な指導を行わなかった」脳外科医に患者への情報提供義務(療養指導義務)を怠った過失がある、として賠償責任が確定した。
その後、裁判では飯島教授らの参考意見が認められるようになり、重篤副作用の注意義務違反に問われるより、主治医による初期症状の見逃し、皮膚科への転医を勧めなかったことが問われるという流れになっている。
「高松高裁の判決は確かに問題でした。患者さんが例えば肝機能障害があるとか、免疫不全があるという特殊な場合なら、医師は投薬の際から注意しますが、これらの副作用は特別な患者さんにおこるわけではなく、家族歴も既往歴もない患者さんにも起こる。また、薬害とも区別しなければなりません。薬剤が適正に使われた場合でも人口百万人あたりにTENでは1人、SJSでは3人の割合でこうした副作用が起こるということです。しかし、そういうまれな病気ですから、主治医は誤診することがあり、皮膚科専門医にみせるのが遅れると、失明状態など重篤になる患者さんもいます。こうした事態を防ぐためにどうすればよいか、ということから、対策が必要だと考えるようになりました」と飯島教授は言う。
心を揺さぶった患者会のメッセージ
だが、なによりも飯島教授の心を動かしたのは、患者会のメッセージだった。
「司法の動向から訴訟対策の必要性を感じたというより、SJSの患者会の方々との出会いに、強いショックを受けましたね」
平成11年に結成されたSJS患者会の患者たちと何度も会ううちに、飯島教授は「初めはヘルペスと診断された」「水ぼうそうと誤診され、みるみる悪化して、失明した」「SJSのことを全く知らない医療関係者がいて、不信感を持った」などの訴えを聞かされた。当時は、日本に同じような副作用に苦しむ人はどのくらいいるのかもわからない、疫学調査も行われず、どのくらいの割合でSJSが起こっているのかもわからず、患者会が厚生労働省に陳情を行っていた。だが、患者会は、なによりも、適切な早期診断・治療法の確立・拠点病院の充実など治療体制の確立を求めていた。
飯島教授は、病気の研究を基に、SJSの進展型がTENであると概念を整理し、患者たちが疑問に思っているような「薬害」とは違うことを説明した。それと同時に、「患者さんたちの心からの叫び声に素直に耳を傾けて、望ましい医療体制の整備をすることに力を注ぐことが、皮膚科医の任務だ」と考えるようになった。
マニュアルは手元に置いて活用を
また、飯島教授ら皮膚科学会の医師はSJS/TENの疫学調査を行うとともに、厚生労働省に対し、重篤副作用を早期発見する体制が必要であると働きかけ、マニュアル作成が実現した。
飯島教授は、医療従事者、とくに医師、薬剤師、看護師はこれらのマニュアルで病態を知り、似た症状があるときは素早く専門医と連携をとるよう訴える。
「内科の開業医の方も眼科にかかわる方も、マニュアルを手元に置いてください。高熱が出た、粘膜が赤くなったり、ただれてきた、目ヤニで瞼が開けにくい、水ぶくれがたくさん出てきたという患者さんの場合、薬疹の疑いがないかどうか、まず確かめてほしいと思います」
企画・取材:山崎ひろみ