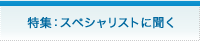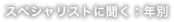国際基督教大学 教授 村上陽一郎先生
最近立て続けに起こる飛行機事故、海外での事件など、安全について考えさせられるニュースが後を絶ちません。そこで第2回目の「スペシャリストに聞く!」では、本ネットワークの名称にも含まれる「安全」をキーワードに取り上げてみたいと思います。お話を伺ったのは国際基督教大学教授の村上陽一郎先生。安全に関する問題を科学的かつ総合的に捉えることを目指した「安全学」(青土社)の著者に、今回は特に「医療の中の安全」について語っていただきました。


|
「安全学」 定価 本体1,800円+税 |
 |
-先生が安全の問題に目を向けたきっかけは何だったのでしょうか?
私は、1980年代の初め、唄孝一(ばいこういち)先生を中心とした医療問題に関する研究会に所属していました。そして同じくその研究会のメンバーであった、当時北里大学附属病院の院長をしていらっしゃった坂上正道(さかのうえまさみち)先生から、「安全カンファレンス」についてのお話を聞きました。それは週に一回、「免責」で院内の事故を報告させることを実験的にはじめたものでした。研究のためということで、そのカンファレンスの録音テープの一部を名前は伏せて聞かせていただきました。今でこそ「インシデント・アクシデントレポート」として知られるようになってきた、院内で起こった事故、あるいは事故にはならなかったけれどもヒヤリとしたりハットしたものを報告するというものですが、当時そういう試みはまだめずらしいものでした。そして、他の分野では行われているような、このような当たり前のことが、医療の分野ではそれまでほとんど試みられていなかったということに気づき、ひどくショックを受けたのです。このことをきっかけに、私は「安全」の中でも特に「医療の中の安全」を主なテーマにしてきました。
-医療の分野と他の分野での安全対策には随分大きな差があったのですね。
製造業では20~30年も前から「QC(quality control=品質管理)サークル活動」が存在しています。これは、第一線の現場で働いている人が、自分たち自身の問題として、細部まで克明に、一緒になってさまざまな事例を報告しあい、事故や問題が発生しないようにするためにはどうしたらよいか改善策を考えるというものです。かつて、看護婦が壁にセットされたコックを酸素供給用のコックだと間違えて、笑気ガスのコックと繋いでしまったために起こった事故がありました。この話を製造業の人にしたら「悪いけれど笑っちゃう」と言われました。そんな重大な部分が誤ってつながってしまうような構造になっているなんて、「安全のいろは」も知らないことになるのだと。
製造業のような意識さえあれば、医療の世界でもとっくに行われていなければならないことが、犠牲者を出しながら今ようやくひとつずつ改善されている状況は、いったい何なのだろうという思いがします。
「To Err Is Human」(邦題:人は誰でも間違える)は、1999年11月にアメリカで発表された医療事故とその防止策を提言した報告書です。この中で、アメリカの医療の分野は、他の分野に比べて安全対策が10年遅れている、と書かれています。日本における医療分野の遅れは10年どころではないと思います。
-医療の分野の安全対策が他の分野より遅れている現状の背景にあるもの、原因は何なのでしょうか?
医療の世界では「安全」についていろいろな対策を講じること自体が、安全性に問題がある、すなわち「危険」で「不安」だということを公表することになるという思い込みがあります。そしてこれが大きなバリアになっているのだと思います。例えば「インシデント・レポート」を始めようという提言を、院長の立場からであれば言いだせるが、あるセクションの一責任者の立場からは言い出せない雰囲気があるというのです。理由は、そういうことを言い出すと、自分の部署がそれほど安全じゃないという証拠になる、そのセクションを貶めることになる、部下を信用できないといっているようで部下にも悪いから、というのですが、これはとんでもないばかげた思い込みです。そうではなくて、安全についてあらゆることを配慮しているところこそ、安全な職場であり現場なのです。
そもそも医療関係者は自分たちに自信がありすぎるのではないでしょうか。高度な教育を受けた自分たちが、まともにきちんとやってさえいれば、間違いなど起こるはずはないという過信がどこかにあるように思えます。
何が起こるかわからないことに対して出来る限りの防御措置をとっておくこと、起きた時どう対処するか、起きないようにどうするか、本来は、そうしたことを24時間考えていなければならないはずなのです。しかしそれが出来ていないのが医療の世界の欠点なのです。
もう一つの大きな問題は、医療の従事者たちが、問題が起きても自分の中だけで抱え込んだり、お互いにかばいあったりする傾向がある点です。自分たちの病院内でさえ言いだせない事が、どうして外部に公表できるでしょうか。医療従事者同士が、もっと隠さずに話し合うことを本気で考えなければいけないと思います。
-実際、上記のようなバリアを感じたことはありますか?
私自身、某病院の「インシデント・レポート」システムの立ち上げに参加したことがあるのです。しかし、立ち上げた後、その病院長に「あなたはひどい人だ!」といわれてしまいました。「インシデント・レポートをやり始めてから、夜眠れなくなった」というのです。「これほど自分の病院でいろいろなことがおきているとは・・・」という思いからです。逆に言えば、このシステムが始まらなければ、管理者である院長の耳に入らず、組織的な対応策もないままに、適当に処理されたことが、いかにたくさんあったかということです。
-その後、その病院ではどのように改善されていきましたか?
例えば看護婦さんが新生児の体重を計ろうとして体重計のそばへ運んでいた時、手が思わず滑ってしまい、赤ちゃんを落としてしまった、という事故報告がありました。不幸中の幸いで赤ちゃんにケガはなかったそうですが、「これについて今後どうしていきますか?」と聞いたら、「看護婦さんがもっと注意をする」との解答でした。もちろんそれも大切ですが、もっと大切なのは「赤ちゃんを動かすのではなく、体重計のほうを赤ちゃんのそばに持ってくる」ということなのです。そういうふうに一つ一つ問題をつぶしていき、マニュアルを作成していきました。
報告により集まったデータは宝物です。「予想し得ること」の対策をしていないのは怠慢以外のなにものでもありませんが、報告は「予想も出来ない、思いもかけないこと」を教えてくれます。それが判って初めて、それへの対応を取ることが出来るのです。人間の想像能力には限界があります。その限りの外にあるとんでもないデータはかけがえのない教訓です。そうして得られたデータを皆で共有し、次にそれが起こらないようにすることが大切なのです。
-安全について最近気になったことを何かお話いただけますか?
最近、なかなかいい雑誌が創刊されました。「患者のための医療」というものです。この中には今までの医療事故がたくさん載っています。もちろん、ここに載っているのは実際起きたもののほんの一部なのでしょうが。この雑誌に紹介されているものを見ていると、過去の医療事故の被害者にさまざまな思いがある中で、一つ共通点があることに気づきます。それは「自分たちと同じ被害が二度と繰り返されないようにしてほしい。だから、今後どういう対応をとるか決めてほしい」という思いです。この思いを決して無駄にしてはならないと思います。
また、最近ある医療関係者から、現場のミスで一番多いのは「患者の取り違え」だと聞きました。手術の際に間違えることはめったにありませんが、そこまで行かない程度の取り違えは日常茶飯事で起きているといっても過言ではないと。最近は、ファーストネームまで名前を呼ぶようになってきていますが、それでもまだ間違えはあります。また、看護婦さんが冷蔵庫から薬を患者さんの人数分順番に取り出して、それを配って歩く時、患者さんのベッドの順番をまちがえて渡してしまうということもあります。降圧剤のような効き目の強い薬であればすぐに違った反応を起こして、間違いに気づくのでしょう。しかし、家庭療養の患者で、それが胃腸薬などであれば、2週間ぐらい(もらった薬の分だけ)気づかずに飲みつづけてしまう、つまり、取り違えられていることさえわからないことだってありうるのです。これは恐ろしいことだと思います。
先程、他業界の話に触れましたが、航空業界は安全対策が特に進んでいる業界です。パイロットには毎月健康診断があったり、常にベストの体調で職務に臨めるように体調管理等にも相当な注意が払われています。そしてそれだけ訓練を受けているパイロットでさえ、繰り返し適性テストを受けるのです。 そのように出来る限りの防御措置をとっていても、昨日のように飛行機事故は起こるのです(お話を伺った4月16日は、奇しくも韓国・釜山での中国機墜落事故が起こった翌日でした)。
ましてや、一回国の試験に受かれば一生医師としていられるのが日本の状況です。ミスを防ぐ為に、どんなことでもやろう、という姿勢で臨まなければ、とつくづく思います。
-今後考えるべき医療の安全対策としてはどのようなことがありますか?
以下のようにチェックポイントを増やすことだと思います。
- ペナルティの設置
- 情報の透明性はできるだけ必要です。ただ、現在のように法的規制がない段階では、良心的なところだけが事故を公表しているようで、逆効果かもしれません。インシデント・レポートを公表している熱意のある病院ほど世の中からは「あの病院ではこんな事故があった、危険な病院だ」と思われ、逆に何も公表しないところが「事故がなくて安全だ」ということになってしまう。ですから、もしやろうとするなら「義務」にしないといけないでしょう。つまり公表しなかったところには何らかのペナルティが必要だということです。 また、実際、ハイリスク医療機関、ハイリスク医者というのはやはりあると思うのです。事故のリピーターはいるのです。むごいようですが、事故にレベルをつけて、例えばCレベルの事故を三回起こした医師に対しては再教育するまで免許を停止するとか、そういったことが安全対策の一つとして必要だと思います。
- 電子カルテ
- 誰にも読めないようなカルテを書く医者が、あたかも偉い先生かのようにとられ、そのカルテを読める人は「○○先生係」とか「特技」といわれたりしますが、ナンセンスです。カルテは誰にでも読めるようにすべきです。誰でも読めるということは、他の人もチェックすることができる、つまりそれだけチェックポイントが増えるということです。それが間違いを防ぐ重要な条件です。その意味で、読み間違えのない電子カルテという方向にいくのはある程度はいいことだと思います。勿論、それはそれで、ミスが起るのですが。
- 医薬分業
- 問診のときに「現在、何か他の病気で治療を受けたり薬をもらったりしていますか?」と聞かれた経験はありますか? そうした質問は100パーセントされるべきなのです。それを訊かない医者は信用できないといっても過言ではありません。ただ、実際今の日本では、がんについては無告知の患者が未だ相当います。ですから患者本人が知らずに治療を受けていたり、薬を飲んでいる可能性は避けられません。この点からも、告知ということが充分に考慮されなければならないでしょう。難しい問題ですが。
しかし、同じ病院の調剤部が出した危険な薬の併用で起こる事故というのがあります。他の病院の状況はわからなかったとしても、同一の医療機関内では、情報の共有さえできていれば、禁忌配合は防げるはずです。実際にはなかなか行えずにいるようですが、薬剤師法24条にもあるように、薬剤師には疑義紹介の義務があります。そういうふうに考えると、医薬分業はチェックが二回になるということで安全対策の一つになると思います。 - 看護師の地位向上
- アメリカでは看護師は一人前の医療者として強い権力をもっています。開業しているケースもたくさんあります。看護師の高学歴化に伴い、日本でも最近になってようやく医師と看護師が対等の「パートナー」となるところが少しずつ増えてきました。実際、患者に接している時間が長いのは看護師です。医師と看護師とがそれぞれの立場で判断していくことで、患者に対するチェックポイントが増えます。
-最後にこれからの課題についてお話していただけますか?
以前、核燃料を運ぶ輸送船に乗り込んだ新聞記者が、新聞の社会面一面に「やっぱりあった安全マニュアル!」と、書いていました。記者の本音は「安全だ、安全だ、と言われていたが、船内にこんなマニュアルがあった。やはりそれほど危険だったのだ!」というところにあったのでしょう。しかしこれには腹が立ちました。「やっぱりなかった安全マニュアル」であったら、そのときこそ大々的に報道されるべきなのです。
また、ある病院が新聞で「うちの病院は患者にリストバンドやアンクルバンドのIDタグをつけて事故防止にとりくんでいる」と事例紹介を投稿したところ、「患者を物扱いしているようだ、そもそも医者が患者を間違えること自体あってはならない。」という反論がありました。これもおかしいと思います。もちろんIDタグをつけて全部の事故が防げるわけではありません。しかし、防げる事故は防げるのです。
事故を防止するためにはどんなにやりすぎてもやりすぎということはないし、決して恥ずかしいことでもなんでもないのです。自分たちのところではこんなことをしていて恥ずかしいなどと思わずに、「徹底的にあらゆることを安全を目指してやりましょう」という覚悟で臨むべきなのです。それでも起こった事故は不幸であるにしても、その経験は宝物だから、それを生かし次に起こらないようにできる限りのことをしましょう、と言った姿勢が必要なのです。
乳幼児の死亡率の低さ、平均寿命の長さなど、医療に関していえば、日本は確かに世界的な水準を越えているところもあります。それらすべてが医療のせいではないにしても。しかし、こと安全に関してはまだまだです。全てが患者の健康と安全を第一に組み立てられるべきです。100人のうちたとえ99人が満足でも、不満な人が1人いればだめなのです。「安全のためなら何でもあり」という意識改革が、現代の医療に求められていることだと思います。
今回、村上先生からご紹介いただいた本
|
「To Err Is Human」 定価 本体2,500円+税 |
 |
|
「患者のための医療」 2002年3月創刊 |
 |