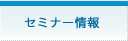「医療の安全フォーラム―適切な危機管理が信頼をつむぐ力になる―」が、平成18年10月8日(日)、都内で開催された。
まず、日本医師会会長唐澤祥人氏による基調講演「日本の医療のあり方について」があった。
続いて、第1部として参議院議員の武見敬三氏と西島英利氏によるトークショー「医療制度改革の光と陰」、第2部として虎の門病院医療安全対策室長松崎道男氏の司会によるシンポジウム「最近の医療裁判事例から」が行われた。
ここでは、第2部のシンポジウムの一部分をお伝えする。
最近の医療裁判事例から
産婦人科の医療事故・医事紛争
樋口産婦人科医院 院長 樋口正俊氏
周産期医事紛争の典型的なものに、経膣分娩か帝切分娩かの選択の適否を争点とするものがある。平成17年9月8日の最高裁判決は、患者の自己決定権の侵害を認め医療者に対して損害賠償請求を認めた。この事例は、胎盤が骨盤位であることから帝王切開を希望した夫婦に対し、主治医は経膣分娩を勧め、結果長男が重症仮死で出生し、4時間後に死亡したものである。1審の地裁は医師無責の判決、原告は控訴し、高裁も医師無責とした。しかし、さらに上告した結果、医師の裁量権よりも原告の自己決定権の優位を認めて高裁に差し戻しの判決となった。担当医の勤務する管理者に対して債務不履行または不法行為(使用者責任)による損害賠償を認めている。
これからは、受診者の自己決定権の侵害にならぬような高度の配慮が必要といえる判例である。
ドイツの農学者フォン・リービッヒが農作物に必要な肥料成分とその収穫量との関係から提唱した「最小律の法則」というものがある。これは医療の現場にも応用できる。医療の評価も最も低い要素で決まる(下図参照)。
例えば、産婦人科医療を汲む桶で考えると三要素は(1)妊産婦死亡(2)周産期死亡(3)医療事故となる。自院の医療水準が受診者を診療するに必要な水準に達しているかの判定は、最も低いと思われる診療要素で判断することが事故・紛争発生防止上重要である。

小児救急医療の現状と医療事故
日本小児救急医学会 理事長 市川光太郎氏
小児救急疾患には次のような特徴がある。
- 軽症者が多いものの、その中に、非典型的症状を呈する重傷者が紛れ込んでいる
- 自己表現が乏しく、主訴が不明確で、診断プロセスが困難なことも少なくない
- 病勢の進行が早く、重症化の予知が困難であることが多い
- 先天性疾患の存在や養育環境の影響が傷病の発生に影響していることも少なくない
- 対象患者の年齢幅の割に、身体的・精神心理的発達の幅が大きい
- 子どもの心身の全体像を通して、あらゆる疾患を想定して診療対応を行わねばならない
- 小児救急医療提供者は子ども自身、そしてその複数の保護者への対応が求められている
事例をあげると、
- 腹痛・嘔吐、いきなり心停止
- 5歳7ヶ月の男児。6月末に発疹出現し、皮膚科にて中毒疹として、外用薬・抗ヒスタミン薬を処方され、軽快していた。7月12日夜、腹痛を訴えるも特に重症感はなく観察。翌朝も少しグズグズ言ったが、幼稚園に登園させた。しかし、嘔吐が立て続けに起こったため、園を早退し、正午過ぎに近医受診。嘔吐がひどいため順番を早めて診察。点滴開始時、全身けいれんが出現、そのまま心肺停止。結局、急性心筋炎(超劇症型)で亡くなった。
- 単純性股関節炎?
- 5歳男児。8月27日朝より股関節痛を訴えて来院。翌28日には歩行困難と37.6℃の微熱が認められたため、当センターを夜間受診。軽症の単純性股関節炎として外来フォローとなる。しかし、翌日も痛がるために、当センターを再受診。発熱もあるため、入院精査を勧めた。血液検査をしたところおかしいデータがあり、精査したところ急性リンパ性白血病であることがわかった。
このように、予測できないことや思わぬ疾患が隠れていることがあり、それらを全て見抜くことは困難である。
医療過誤・事故を回避するためには、国民全員が子ども達の健全育成への責務を再認識し、医療資源としての小児救急医療の擁護・育成が課題である。
医療崩壊の阻止のために
医療法務弁護士グループ代表 弁護士 井上清成氏
自動販売機にコインをいれるように、法律に問題を入れればチャリンと答えが出てくる、一義的に明確に決まっている、そう思っている人が多いかもしれない。しかし、テレビ番組でもわかるように、弁護士の意見は必ずしも一致しない。法律の事案についての回答は一義的ではなく不確実なものなのである。
これは、医療も同じではないだろうか。最近は、悪い結果が出たら即逮捕、即業務上過失致死罪という形になりかねない。しかし、医療は不確実なものであり、限界があることを是非理解してもらいたい。