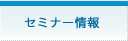「レジリエンスの探求~つながり、共創、イノベーション~」をテーマとする「第14回 医療の質・安全学会学術集会」が2019年11月29、30の両日、国立京都国際会館で開かれた。今回は柔軟性や弾力性、しなやかさなどを意味する「レジリエンス」を踏まえたヘルスケアシステムの実現について、サイエンス、マネジメント、政策、教育など、さまざまな角度から活発に議論。日本老年医学会と連携したシンポジウム「転倒転落を科学的視点で捉え直す」では、医療介護現場における転倒・転落問題に携わる関係者がそれぞれの立場から意見を交わした。
高齢者の転倒・転落は老年症候群
院内転倒による死亡事例の分析からの提言
荒井秀典(国立長寿医療研究センター 理事長)

荒井秀典氏
ほとんどの医療・介護施設では転倒・転落予防対策を講じていると思われる。完全に予防できなくても、それらに対する備えを怠らないようにし、骨折や死亡などの重大なアクシデントに至らないような体制を整備しておくことが望まれる。
そこで、転倒・転落による頭部外傷にかかる死亡事例を検討。転倒・転落から死に至った原因を分析し、頭部外傷がもとで亡くなる事態を回避するための対応をまとめる。さらに、院内における転倒・転落を予防するための視点での検討も行った。
センターに届けられた医療事故報告(2015年10月~2018年12月末)の院内調査結果報告書908件のうち、転倒・転落に関する死亡事例は18例であった。
- 【転倒・転落後の診断と対応】
-
- 1.
「抗凝固薬・抗血小板薬内服中の患者では頭蓋内出血の可能性を認識する初回CTで頭蓋内出血が認められる場合は、あらかじめ時間を決めて再度、頭部CTを撮影することも考慮する」⇒抗凝固薬・抗血小板薬内服中や初回CTで頭蓋内出血の所見がある患者では、急激に頭蓋内病変が進行する可能性がある。
ポイント=凝固・線溶系の障害、血小板減少症の病態では、神経学的所見が出現してから頭部CT撮影を行った場合、手術などの治療が間に合わない可能性もある。
- 2.
「出血などの異常所見があれば、脳神経外科医師の管理下に手術ができる体制で診察を行う。脳神経外科医師がいない場合は、手術が可能な病院へ転送できる体制を構築しておく」⇒急性硬膜下血腫でも脳表の静脈から出血する脳挫傷の少ないタイプでは迅速な血腫除去により救命される可能性もある。手術が必要な頭部外傷発生時の転送を含めた診療方針や判断について院内で検討し明文化しておく。
ポイント=転倒・転落による頭部外傷の事象発生に備え、転倒・転落後の診断と対応について検討しておくことが推奨される。
転倒・転落歴は重要なリスク要因と認識する
- 【頭部への衝撃を和らげるための方法】
-
「ベッド柵を乗り越える危険性がある患者では、ベッドからの転落による頭部外傷を予防するため、衝撃吸収マット、低床ベッドの活用を検討する。また、転倒・転落リスクの高い患者に対しては、患者・家族同意の上、保護帽の使用を検討する」⇒保護帽および衝撃吸収マットには転倒・転落時に身体に加わる急激な力を緩和する効果を期待できる。
ポイント=ベッド柵を乗り越える能力のある患者へは、離床の誘因を取り除き、適切なタイミングで患者の行動をサポートする配慮も重要である。
- 【転倒・転落リスク】
-
- 1.
「転倒・転落歴は転倒・転落リスクの中でも重要なリスク要因と認識する。認知機能低下・せん妄、向精神薬の内服、頻尿・夜間排泄行動も転倒・転落リスクとなる」⇒転倒・転落につながるヒヤリハットや同じ状況で転倒・転落を繰り返す可能性が高い。ナースコールを押して介助の必要性を知らせることが難しく、一人で歩行してしまう。睡眠薬や抗精神病薬の副作用によりリスクが高くなる。加齢性変化による尿便意の切迫状態が気持ちの焦りとなる一方で、健康時のボディイメージのまま行動する。
- 2.
「転倒・転落リスクの高い患者への、ベンゾジアゼピン系薬剤をはじめとする向精神薬の使用は慎重に行う」⇒高齢者では薬剤の感受性が高まり、代謝や排泄が遅延するため、健忘や認知機能障害、せん妄などの副作用が現れやすい。向精神薬との多剤併用は転倒・転落リスクがより高くなる。
ポイント=せん妄に対しては、薬物対応の前に、まず、原因の除去や早期離床、環境整備といった非薬物的対応に努めることが望まれる。
多職種による連携や情報共有が必要
- 【情報共有】
-
「入院や転棟による環境の変化、治療による患者の状態変化時は、転倒・転落が発生する危険が高まることもあるため、患者の情報を共有する」⇒多職種が多く勤務する日勤帯に、夜間と日中の状況を踏まえて転倒・転落リスクを分析して予防対策を検討し、夜勤帯へ伝達する。転棟などの環境の変化や患者の状態変化によって、転倒・転落リスクが高まることを認識し、転倒・転落リスクを再評価する。
ポイント=高齢者や認知機能低下の患者では、環境の変化などで混乱をきたす可能性があるため、転倒前の転倒・転落リスクに関する情報や入院前の患者情報が重要となる。
- 【転倒・転落予防に向けた多職種の取り組み】
-
「転倒・転落リスクが高い患者に対するアセスメントや予防対策は、多職種で連携して立案・実施できる体制を整備する」⇒多職種の医療スタッフがそれぞれの専門性を活かして患者のリスクを分析・評価し、個別のケアプランを多職種で構成されるチームで検討する。ヒヤリハットを含む転倒・転落に関する事象についての検討会や院内研修を開催する。
ポイント=個々の患者の状況に合わせた転倒・転落予防対策の立案・実践・評価が重要である。
高齢者において転倒・転落は、さまざまな原因で発生する、いわゆる老年症候群の一つである。従って、完全に予防することは不可能だ。しかしながら、高齢化に伴い、転倒・転落に関するリスク評価や対策を講じ、転倒・転落後に頭部外傷がある場合には適切な対応がなされることが望まれる。
転倒・転落の「再発防止」はファンタジー?
『やるべきこと』と『できること』
児玉安司(一橋大学法科大学院/自治医科大学 客員教授、弁護士)

児玉安司氏
シンポジウムのテーマに即して(1)トレード・オフ=何と引き換えに、何を許容するか(2)事故と紛争の実情(3)「やるべきこと」と「できること」の乖離――について、所感を述べたい。
トレード・オフされるコンプライアンス(法令順守)について、西村あさひ法律事務所の梅林啓弁護士は「ルールを守ることで、引き換えに何かを失う。ルールを守らないことで、引き換えに何かを得る。結果として人はルールを守らなくなる」と提唱している。実際、現場にこうした二律背反を強いると不祥事や事故が起こる。
例えば、鉄道業界では、安全な運行と安定的な定時運行は二律背反の関係にある。安全コストとコスト削減という経営的な関係もある。要するに、現場が無理をすれば、いつか鉄道事故が起こる。従って、国民の理解を得れば、無理なく計画運休ができるはずだ。
医療の置かれた状況はどうか。職業柄、毎日、紛争のさなかに身を置いていると、こと転倒・転落については「再発防止」がファンタジーに思える。現場では地域包括ケア推進の名のもとに、医療の質・安全の向上がいつも求められる。同時に医療の供給量は、高齢化と共に増加が求められる。質・量ともに上げるための手段にはコストも人手もかかる。
恒常的な人手不足の中で進められる働き方改革では、看護師の業務が多様化して人材がとられる。地域包括ケアで介護との接点が増大する。介護現場の離職率が高いので、離職ドミノが起こる。従って、二律背反によるこうした状況を超えるイノベーションが必要ではないか。
一方で、現場のやりがいは「その人らしさ」を守ることにある。しかし、人間性を無視すると、介護の現場は「絶望工場」になる。このため、人間性を引き出そうと、介護の現場は頑張っている。その結果、拘束しないで歩かせるから転倒・転落が起こる。胃ろうにしないで食べさせるから、誤嚥窒息が起こる。お風呂に入れるから入浴事故が起こる。いずれも、努力の果てにさまざまな問題が起こるということだ。
拘束廃止と転倒防止にも同じようなことが言える。それらが「完全に」両立するためには果てしなくコストがかかる。「見守り」や「人の注意力」は最大のコスト要因だからだ。従って、急性期、慢性期、在宅、入所介護、それぞれに拘束や転倒をどの程度許容するかを考える必要がある。それらを見極めた上で、コストよりも社会的許容を重視する必要があるのではないか。
医療看護の文献やガイドライン、マニュアルとの戦い
事故と紛争の実状はどうか。一般的な急性期病院のアクシデントを調査したところ、4997床の病院群で年間2万7300通のインシデント・アクシデントレポートが上がった。転倒・転落は3791通、食事関連は1537通だった。転倒・転落件数は病床数に迫る。500床なら月に1、2回以上の事故が起きている計算になる。
私も委員として参画している社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会の調査によると、全国の介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設1万75事業所で、損害賠償保険の加入は「有」が98.0%だった。
過去1年間に損害賠償請求を受けたことは「有」が22.0%であった。現場で夥(おびただ)しい紛争が起こっていることを示す数字だ。クレーム対応体制の構築は「している」が97.1%。平成30年4~9月の利用者・家族からのクレームは「有」が51.8%であった。クレームへの主な対応者は「生活相談員」が81.0%であった。
朝日新聞の報道(平成31年3月25日)によると、入所者におやつを詰まらせ死亡させた介護施設の准看護師に罰金20万円の有罪判決が言い渡された。裁判所は介助中に十分な注意を払わなかったとして業務上過失致死と判断した。「過失」の法解釈には無数のバリエーションがあり、その事例や事実関係、争点ごとに司法の判断は異なる。従って、一般的なルールを示すものではない。
食事介助の論点は、過失すなわち「やるべきことをやらなかった」の解釈であろう。「やるべきこと」は教科書やガイドライン、マニュアルなどに明記されている。しかし「できること」とのギャップが生じれば「過失」が広がる。だから、本音と建前に差があると、現場が困る。食事介助や転倒・転落、入浴事故の多くは「ちょっと目を離した隙」に起きる。ちょっと目を離す最大の要因は明らかに人手不足である。
参考までに、この事件では「因果関係」の観点から弁護側は窒息ではなく脳梗塞であると主張している。
では、医事紛争は何と戦うのか。相手は患者か、弁護士か、裁判官か。本当の戦いは医療看護の文献やガイドライン、マニュアルのoverstatement(言い過ぎ)ではないかと思う。それらに示される過剰な一般化や現実との乖離、「見守り」や「注意力」などマンパワーに依存する事柄は明らかにコストや規制の現状を無視しているといえるだろう。
「やるべきこと」と「できること」との乖離がリーガル・リスクに直結する
「やるべきこと」と「できること」の乖離は医療や介護の現場で日常的に見受けられる。例えば、拘束時の肺塞栓を予防するための対策として、D-dimerのカットオフ値を2.0μg/mlとして両足のエコーを行う。5~10μg/mlで設定するという意見もある。しかし、医療資源(マンパワー)がない中で、理想主義に寄ったガイドラインを出すと、医療現場で実施されない不人気の指針となる、それどころか、医療機関を訴える訴訟の時にだけ原告の役に立つ。従って、医療・介護担当者集団内でのフィージビリティスタディが必要になるのではないかと思う。
『日経ヘルスケア』2019年10月号の特集「介護訴訟をどう防ぐ」は見守りで転倒が防止できるかを検証している。見守りの距離3.0メートルでの実証実験によると、すぐに倒れたり一歩踏み出して倒れたりすることが報告されている。すなわち「じっと見守って」いても、すぐに倒れたら防げない。「見たり見なかったり」ではほとんど防げない。「作業をしながら」ではまったく防げない。
これまで見てきたように「やるべきこと」と「できること」の間に生じた乖離はリーガル・リスクに直結する。「場合」が特定しなければ「常に」なのか。そのルールはどこまで一般化できるのか、そのルールはどこまで現実化できるのか、そのルールで本当に「再発防止」ができるのか。
こうしたことを振り返ってマニュアルやガイドラインを見直し、頑張り続けている現場の実状をメッセージとして国民全体に伝えていくことが望ましいのではないか。
共通のプラットフォームでカスタマイズ
改めて転倒転落を考える~介護老人保健施設現場からの発信~
武藤章(医療法人三幸会 介護老人保健施設紫雲苑 事務長)

武藤章氏
介護老人保健施設が提供できるサービスには、入所、短期入所、通所リハビリ、訪問リハビリがある。転倒転落予防という点では、各サービスで少しずつ着眼点が違ってくる。
入所利用者といっても、病院よりリハビリを目的に入所され、在宅復帰を目指す方や、数カ月ごとに施設と在宅を行き来する方、介護老人福祉施設等の他施設に移る方もあり、退所先を見据えた転倒転落予防の視点は欠かせない。
短期入所は、主な生活の場は自宅であり、利用期間は数日~30日、利用頻度も毎月の方もあれば、1年に1回の方もある。施設内はバリアフリーとなっており、段差や手すり等の環境は整っているが、自宅ではないため「使い勝手」が変わる。これは入所利用者の在宅復帰を目指す方にも共通することではあるが、居室の環境をどれだけ使い慣れた自宅の環境に近づけられるかが大きなポイントである。
通所リハビリは、自宅玄関から送迎車への移動や乗降など屋外での移動も伴うため、利用者ごとに注意点が異なる。また、天候によっては傘をさすことが必要になるなど、さらに神経を使わなければならない。
訪問リハビリは、文字通りリハビリ職員が自宅に訪問し実施するリハビリであり、自宅内外で課題となっている動作(例えば、玄関の出入りや、最寄りバス停までの移動など)を実施することもあり、より注意が必要である。
本日は2019年4月~9月の当施設現状から転倒転落について考えていきたい。期間中の事故報告は69件、ヒヤリハットは191件であった。
転倒転落状況のまとめ
転倒転落事故は、入所・短期入所(泊り)サービス利用者で発生していた。
転倒事故31件中、4件が他科受診((1)左鎖骨骨折(2)右大腿骨頸部骨折(3)左大腿骨転子部骨折(4)右大腿骨転子部骨折)、内3件が入院となっていた。
転倒事故31件中、2件が頭部裂傷により縫合処置を行っていた。
事故発生は、9時~19時に多く発生していた。
入浴や排泄など直接的介助時の事故は少なく、就寝時やサービス提供を受けていない時に多く発生していた。
入所サービスの職員体制をみると、看護職員は11.8人(人員基準:9.7人)で、介護職員は26.9人(人員基準:24.3人)であった。通所リハビリは利用者20人に対し、常時4人以上配置。訪問リハビリは常に1対1で対応していた。
「入所者に対し自ら適切な介護保健施設サービスを提供することが困難」な状況か否かが判断できるソフト開発に期待
通所リハビリや訪問リハビリでは転倒転落事故は発生しておらず、入所フロアのみで発生している。その違いとして、利用者に対する職員人数とフロアの広さ(利用者と職員の距離)が挙げられる。離床センサーもさまざまあり、導入はしているものの、反応時に直ちに職員が駆けつけられないこともある。
介護保険制度施行時から、介護保険施設等において利用者または他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を禁止されている。
緊急で、やむを得ない場合として、次の3要件をすべて満たすことが定められており、1つでも要件を満たさない場合には指定基準違反となるが、その判断が大変難しい。
- 切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
介護老人保健施設の運営基準には「介護老人保健施設は、正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではならない」とある。また「提供を拒むことのできる正当な理由」として「入院治療の必要がある場合、その他入所者に対し自ら適切な介護保健施設サービスを提供することが困難な場合」と記載されているが、その判断も大変難しい。
施設によって、利用者数、利用者の状態、フロア構造・面積、離床センサー・低床ベッド等の整備状況、職員人数、職員経験値・スキルもさまざまである。
そのような中で、運営基準にある「入所者に対し自ら適切な介護保健施設サービスを提供することが困難」な状況か否かが判断できるソフト開発に期待したい。
今後も医師、薬剤師、看護職員、介護職員、リハビリ職員、支援相談員、管理栄養士、事務員などで転倒・転落予防や事故発生時の対応に努めていきたい。
他の年齢層より発生率が高く、防止がより難しい入院高齢者の転倒・転落
医療機関における入院患者の転倒・転落の実情
山本知孝(東京大学医学部附属病院 准教授)

山本知孝氏
各医療機関で転倒・転落防止のさまざまな取り組みがなされてきたが、現状では完全に防ぐことが難しい。今後の対策を考える上で、院内転倒・転落の実情を把握することは重要である。しかし、施設の種類や規模、体制等によって状況は異なり一括して論じることはできない。ここでは、大学病院における転倒・転落の実情を知るための手がかりとして、東京大学医学部附属病院(以下、当院)の入院患者に関する分析結果を提示する。
当院入院患者における転倒・転落発生状況
当院の病床数は1264床で、一般病床は1216床である(発表時点)。2018年度の入院患者数は延べ35万3647人で、新入院患者数が2万7637人、一般病床の平均在院日数は12.5日であった。2011年度から2018年度までのデータを分析したところ、以下の点が明らかとなった。
- 入院患者の転倒・転落発生率〔分母が延べ入院患者数(人日)、分子が入院患者の転倒・転落件数で、単位はパーミル(‰)〕は、各年度において1.5から1.9の間で推移した。一方、分母を年間退院患者数(年間新入院患者数にほぼ一致する)に置き換えて計算した発生率(%)は2.1から2.6の範囲であった。これらの指標はほぼ平行して推移し、変動しつつ緩徐に低下傾向を認めていたが、2018年度にはやや上昇した。
- 当院の年間退院患者数は、27000人前後で推移しているが、その年齢構成を見ると、65歳以上の高齢者がすべての年度において4割以上を占めていた。
- 患者を65歳以上の高齢者と15歳未満の小児、およびそれらの中間層(15歳以上65歳未満)に層別化すると、退院患者数を母数とした転倒・転落の発生率が最も高いのは高齢者、次いで中間層、小児の順であり、この順序はすべての年度で維持されていた。
- 全転倒・転落件数を母数とした年齢層別の転倒・転落発生割合では、すべての年度で高齢者が6割以上を占めていた。
- 各年齢層別に退院患者数を母数とした転倒・転落の発生率を算出すると、中間層と小児ではほぼ同じレベルの発生率となったが、高齢者ではそれらの2倍前後の発生率となり、2018年度は2.7倍で8年間中最大であった。
入院早期の診療情報に基づいた転倒・転落リスク評価の可能性
2018年1月から2019年9月までに入院期間が含まれる患者について分析したところ、とくに高齢者では、入院早期の転倒転落が多かった。
一般病床用看護必要度の評価を実施している病床に入院した患者について、入院中の転倒・転落の有無を目的変数として、年齢層別にロジスティック回帰分析を行った。
説明変数として用いたのは、入院時年齢、性別、BMI、Barthel Index合計点、入院日看護必要度A, B, Cそれぞれの合計点、転倒の原因となり得る疾患の有無、転倒の原因となり得る薬剤の有無で、いずれも入院初日のデータである。
疾患の病名リストはICD-10に基づいて作成し、DPCの入院契機傷病名または入院時併存傷病名としての登録の有無を変数とした。薬剤については、転倒・転落のリスクとなりうる薬効群について、個別医薬品コード等を参照して薬剤名リストを作成し、入院初日に発行された持参薬処方または入院処方にそれら薬剤が含まれるか否かを変数とした。
解析の結果、高齢者と中間層に共通する危険因子は、年齢、Barthel Index合計点、看護必要度Bの合計点であった。また、疾患と薬剤については、年齢層によって危険因子が異なる可能性が示唆された。
さらに、機械学習の手法を用いて検討したところ、入院早期のカルテ記載に基づいてその後の同一入院中の転倒・転落を予測することが一定程度可能であることが明らかとなった。2011年から2017年に当院に入院し、その期間が4日以上30日以下であった高齢者について、入院初日から3日目までのカルテのテキスト記録を用いてBi-LSTMとself attentionを併用した転倒・転落の予測モデルを作成したところ、ROC曲線のAUCの暫定値は0.78であった。
注目単語を可視化すると、医療者が転倒・転落を予期している症例では、モデルの予測値も高いことが分かった。さらに、転倒・転落の有無で2つの群に分け、年齢、疾患、検査値、処方薬などの共変量について傾向スコアを用いてマッチング を行い解析したところ、転倒・転落群において入院期間の延長を認めた。
既存の対策では防止が困難な転倒・転落が存在する高齢者
当院の転倒・転落発生状況の分析からは、入院高齢者の転倒・転落は、他の年齢層に比較して発生率が高く、防止がより難しいことが示唆された。高齢者ではとくに入院初期の転倒・転落の割合が高いことに注意が必要である。
入院初日の診療情報には、転倒・転落の危険因子として把握可能なものがあるが、その中には、各年齢層に共通なものとそうでないものがある。これらの理解を深めることで転倒・転落をさらに防止できれば、入院期間の不必要な延長を抑制できる可能性がある。
機械学習の手法によって、通常業務に基づいたカルテ情報から転倒・転落リスクを評価できるようになる可能性があり、今後この様な観点での臨床応用の進展が期待される。
ただし、リスクの評価だけでは不十分である。防止対策の効果を加味した分析ができていないことは、今回の解析の限界の一つであり、記録やアセスメントの業務負担を増大させずに、転倒・転落防止対策の有効性も含めた分析を可能とする方法論の開発が望まれる。
また、実臨床の経験からは、特に高齢者においては既存の対策では防止が困難な転倒・転落が存在すると考えられ、それらについては今後も個別に丁寧な検討を重ねる必要がある。
取材:伊藤公一