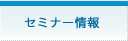基調講演「医療安全とガバナンス」要旨採録
地方独立行政法人 奈良県立病院機構 奈良県総合医療センター 総長 上田裕一

上田裕一氏
医療の世界にガバナンスという概念が取り入れられて久しい。しかし、言葉の解釈は人それぞれである。抽象的な横文字であればなおさらだ。医療におけるガバナンスはコーポレート・ガバナンスを転用できるのか、これまでの医療安全活動とは何が違うのかなどを考える講演『医療安全とガバナンス』が「医療安全全国フォーラム2017」(一般社団法人医療安全全国共同行動主催、2017年11月24日、幕張メッセ)で開かれた。演者の上田裕一奈良県総合医療センター総長は自らの体験を振り返りながら考えを述べた。
なぜ「ガバナンス」と表現されるのか
昨今、企業のコーポレート・ガバナンスがメディアを賑わしているが、ガバナンスという言葉を使わなければならない場面はどういう状況なのか、日本語で言うとどうなるのかという疑問を、実は2年前の医療の質・安全学会での講演で述べた。
英和辞典でガバナンスをひくと「国家などの統治、組織などの運営管理」とある。従って、コーポレート・ガバナンスは「企業統治」と訳されることが多い。広辞苑では「統治、支配、管理」とある。これを医療安全に転用すると「医療安全のために統治する、支配する、管理する」となるが、ちなみに、公益法人関連用語集には「一般的には組織における意思決定、執行、監督に関わる機構のことをいう。企業の場合は効率的かつ健全な企業活動を可能にするシステムをいう」とある。
しかし、どうも辞書のいう「内部統制」や「統治」ではなさそうだ。「ガバナンスとは組織や企業など、社会に関与するメンバーが主体的に関与し、意思決定や合意形成をするシステムである」との説明もある。それでは、効率的かつ健全な病院の活動を可能にするシステムとは何を意味するのか。
コーポレート・ガバナンスの場合、首脳部や執行部で決定された方策をいかに実行するかはマネジメント、つまり運営である。その運営状況をいかに管理・監督するかが内部統制すなわちガバナンスである。さらに企業のシステムが健全に機能しているかを審査するのが監査で、内部監査と外部監査に分かれる。
では、このコーポレート・ガバナンスの活動を病院のガバナンスに換えてみると、「病院の非安全行為の防止と医療の質の向上、収益を総合的に捉え、長期的な病院の価値の増大に向けた病院運営の仕組み」といえる。また、コーポレート・ガバナンスの活動にならえば、病院執行部で決定された方策をいかに実行するかはマネジメント、病院の運営状況をいかに管理・監督するかはガバナンス、病院のシステムが健全に機能しているか(=医療の質)を審査するのは監査――となる。
明記された「患者の安全を第一に」
厚生労働省の「大学附属病院等のガバナンスに関する検討会」は2016年2月から9月まで5回にわたって開かれ、12月にまとめられた記録によると、患者の生命、健康をあずかる医療提供施設として「患者の安全を第一とする高度な医療安全管理体制を確保することが何よりも優先されるべきことをすべての議論の出発点、大前提として確認する」としている。
この中にはいろんなことが書いてあるが、きょうは大学病院に限らず、病院あるいは診療所も含めて、そこで行われる医療の上でのガバナンスについて考えていきたい。このとりまとめは表題の中央に「患者の安全を第一に」と明記されている。それは、すべてに共通することであり、そこで働く人たちのためとか、病院の収益をあげるためではない。つまり、その要点は、法人や病院の体制、内部規定等を総点検しなさいということだ。
病院長の選出についても、かなり踏み込んだ意見が書かれている。国民の信頼に足る診療体制の再構築に向けて、あらゆる面で過去のしがらみと決別し、改革を断行する意気込みをもって行っていただくことを期待するとも書かれている。つまり、今までの制度を抜本的に変えろということだ。
とりまとめの中では「患者の安全を第一に据えてガバナンス体制を構築する必要がある」と謳われている。その基本的な考え方として「管理者(病院長)は医療安全の確保に関する法的責務を負っており、管理者には医療安全管理について十分な知見を有し、継続したリーダーシップを発揮できる者が選任される必要がある」「管理者が権限と責任を持って病院の管理運営に取り組めると同時に、相互牽制が機能するような適切な意思決定のあり方を含むガバナンス体制を構築する必要がある」と明言している。
ガバナンスの本質は"COMPLY or EXPLAIN"
では、病院長や執行部がガバナンスを効かせるためには何をすれば良いのか。そして、これまでしてきた医療安全活動とは何が違うのか。さらに、医療の質と患者安全を担保できる病院のシステムを実現するには何が必要なのか。
ガバナンスの本質を端的に言うと内外の関係者(ステークホルダー)との情報共有=COMPLY or EXPLAINである。「規則に従え。従わないのであればその理由を説明せよ」と訳すことができる。この考えは法令等で強制するのではなく「従うかどうかは企業の自主性に任せつつ、従わない場合には説明責任を果たしたうえで、それをどう評価するかは、投資家などのステークホルダーに任せる」というスタンスだ。病院なら患者やその地域の方々、市民や県民の方々がステークホルダーになる。従って、医療のプロフェッショナルである医師や看護師、薬剤師、技師などは、COMPLY or EXPLAINで何を守らねばならないか、説明しなければならないかをよく考える必要がある。
そこで、医療の質の実態を知り「何のためのガバナンスか」を考えることが大切だ。医療過誤や事故は氷山の一角であり、その下には標準から逸脱した医療がある。この医療の質を測る、逸脱を検出するにはどうしたら良いのか。日常的に検出するのは大変に難しいが、各診療科は分かっているはずだ。自分たちが持っている基準を下回る結果であれば、何が診療上の問題だったかを考えていかねばならない。
私の専門である外科系は、術前術後にカンファレンスをしている。例えば、術後カンファレンスで、行った手術のどこが悪かったのか、なぜ悪かったのか、それを次に起こらないようにするにはどうすれば良いのかも、検討する必要があると思う。実際、術前にかなり時間をかけて検討しても、術後の問題には残念ながら十分な検討がされていないことが多い。
少なくとも重篤な合併症が生じた場合には「病院全体として症例検討会を開催して評価するだけではなく、診療上の問題点が院内で広く共有されているか」「医療従事者の認識と、報告する組織風土」が問われるのではないか。その一助として、月間とか四半期ごと、あるいは半期ごとに重大インシデントや重大合併症については、網羅的に検討する必要があると思う。
しかし、医療の質について、経常的かつ継続的に測定していることに対して、その報告をどのように受け取り、診療科にアドバイスするかという仕組みが整っていないのが実情だ。むしろ、病院長が各診療科に定期的に提出を求め、それをディスカッションするところから入っていかねばならないと思う。つまり、体制を整えるだけではガバナンスの実効性は保てない。形骸化すれば不正の余地も生まれる。「これぐらいは報告しなくてもよい」「これぐらいは逸脱ではない」ということになりがちだ。
どのような情報を収集するのか、その結果を組織内外に共有することにも、高いハードルがある。敢えて言えば、死亡や合併症の発生率など、ネガティブなデータを公開することに対して、大変厳しい状況が生まれる可能性がある。病院の評価につながるからだ。外科医にとっては手術の紹介が減るかもしれない。あるいは若い外科医が次に着任してくれないかもしれない。しかしながら、医療のプロフェッショナルと患者や社会の間で相互理解できるシステムを作っていかねばならない。一病院だけが情報を出したとしても、他の多くの病院が追従しなければ、その文化は自ずと先が見えて止まってしまうだろう。
安全文化は報告、公正、柔軟、学習
内科も外科も診療水準の評価は大変難しい。専門性が上がれば上がるほど難しい。また医師が行おうとする治療方法がEBMに沿っているのか。沿っていない新規の医療技術や新規の治療法をトライしようとしているのかの把握も難しい。自主的に申請書を倫理委員会に出してくれれば分かるが、群馬大学の場合には、保険外診療という点が大いに問題になった。保険外診療を他科の医師や看護師、事務方が理解できるだろうか。言うまでもなく、大変に難しいと思う。
だからこそ、行った治療が日常的にデータベース化されている必要がある。少なくとも死亡率や術後の重大合併症などの治療の質は評価できるはずだし、蓄積もできるはずだ。それを診療科内だけではなく、院内には公表すべきだろう。そして、執行部にはそれを明解に記載したデータを提出すべきだ。
昨今は労働時間の問題もある。限られた人材の中で医療を続行しようと思えば、特に外科系は手術が終わったからといって家に帰るわけにはいかない。上手な手術をして術後経過が良ければ、すぐに帰ってもよい。外科医が継続して患者を診る必要がないこともある。一方では、術後経過が芳しくなく、長く経過を観察しなければならないのは、手術そのものに原因があるかもしれない。多くは患者の要因にあると思うが、それは、在院日数や術後合併症の多寡などに現れる。従って、医療従事者の認識を変えていかねばならない。「私たちのネガティブなデータを病院長に報告しなければならない」ではなく「私たちの医療の質を上げるためにはこのデータを集積・分析し、改善につなげるのだ」という文化が根付くことが必要だ。手術の技術を高めるのは難しく、手術チームのレベルアップはさらに難しい。
有名なJames Reason先生の『組織事故』によると、安全文化は「報告する文化、公正な文化、柔軟な文化、学習する文化」で成り立つ。報告する文化とは、自分自身のミスやエラー、自分に不利になる事柄をも報告するということだ。公正な文化というのは、起きてしまったことから学習し、安全性を高めるための対策を行うと同時に、その事故の被害者や社会に対して最大限の説明責任を果たすということだ。
安全性を高めるために対策を行うところまではいくが、被害者や社会に対して最大限の説明責任を果たす文化というところまでは、まだまだ達していないと思う。うまく説明できることはいくつもあるからだ。研修医や外科医は長年の間に「どのように説明すれば患者や家族が納得するか」といったことや「手術に対して大きな疑念を持たれない言い方」などを"隠れたカリキュラム"を通して学んでくる。
柔軟な文化は、文字通り、常に変化する医療に対応できるということだ。当然、患者ごとに違う場合がある。外科医や医療者は製造業とは違い、画一的な医療をしているわけではない。患者に合わせて適切な措置をしている。その中で起きた合併症については、「ある程度は致し方ないものだ」と考えがちだが、その変化する要求に効率的に対応できる文化を作らねばならない。予期できない事態に直面した場合に臨機応変にできるというのも組織文化である。
緊急時においては、第一線の医療者だけで判断、実行できる権限を委譲することも重要だ。何かあったときに病院長まで報告が届かないと、次の手を打てないというのではなく、緊急時には第一線の医療者が判断し、それを実行することを可能にする。産業界ではトヨタ生産方式の「アンドン」が有名だ。現場の作業者が「アンドン」で異常を知らせると、その現場で対応する。そのおかげで不良品の大量発生を未然に防げる。緊急の場合には、現場が権限をもって対応するということだ。
学習する文化は、過去の事故に学び、改善していくことだ。それは「報告する文化、公正な文化、柔軟な文化」が揃って初めて実現できる。『組織事故』における指摘はガバナンスにおいても不可欠だ。病院長がいくら報告しなさい、と言っても、それで対応できるものではない。診療に参加する第一線の医師や看護師、薬剤師、技師など、すべての人がそういう場面に直面するわけで、直面した際の態度、報告の仕方が問題になってくるからだ。
問題を認識したがらない文化
今日のクリニカル・ガバナンスを推進したのは英国ブリストル王立病院の事件である。これは1984年から1995年までの約10年間に小児の心臓手術で過剰な死亡例が生じ、内部告発から社会問題へと発展した事例である。長年にわたり死亡率が高いということは分かっていたが、1990年に赴任した麻酔科医が「この死亡率はおかしい、異常に高い」ということを病院長に内部通告した。しかし、これくらいの死亡率は致し方ないということで継続させていた。その後、術中死が報道されて社会問題となり、特別調査委員会を設置し国家をあげて大規模な調査が行われた。執刀した2人の心臓外科医だけでなく、事実を放置していた病院管理者も責任を問われた。特別調査委員会の調査報告書に基づく2000近い勧告で改善がもたらされ、英国の医療は変わった。
クリニカル・ガバナンスというのは、いわば英国の登録商標だ。ガバナンスにクリニカルを付けただけでなく、ナショナル・ヘルス・サービスの中で提唱されたことだと書かれている。通報者の麻酔科医はこの通告をしたことで、英国で医療ができなくなり、オーストラリアで今も麻酔科医をしている。ただし、英国の国会は、彼の発言によって英国の医療が変わったとして表彰している。
クリニカル・ガバナンスは、良い医療を促進することと、悪しき診療を防ぎ、容認できない診療を発見すること、つまり、医療の質を安全で規律づけるための仕組みである。英国も日本も米国も、病院における組織文化、すなわち院内で培われた信条や思い込み、価値体系などは、患者を安全に保つことに対してスタッフが示す態度に多大な影響を与えている。
ブリストル事件について言うと、麻酔科医だけが気がついたのではなく、当然、ICUのナースも医師も小児科医も、みんな気づいていた。でも止まらなかった。なぜ止まらなかったのか。
チームワークと協力の風土は、エラー防止に留意する安全に主眼を置いた作業プロセスやコミュニケーション方法と共に理想的なものである。これがうまく機能すれば、心臓手術に代表される高リスクな臨床環境においても有害事象を認識し防止できる。その認識をしたときには、きっちりと記録に残す。それが報告することにつながる。
しかし、残念ながら、内部から懸念の声が上がっても、問題を認識したがらない文化がある。問題が上がったとしても、対応が不十分な医療の質保証システムによる二重の危険性がある。つまり、報告する文化だけではどうしようもないということだ。医療施設はこれから変容しなければならない。英国は10年かけて変容した。医師、医療従事者の思考(組織風土や文化)はもちろんのこと、医療技術(標準的技術と先進的技術)や医療制度(法制度、提供体制、地域医療)もこれから変容していくことだろう。
特に病院においては、医師や部長、大学では教授の思考・認識を変える必要がある。自戒を込めて言えば、マネジメント能力、問題解決能力が問われている。私たちは「正しいことをしている、精一杯やっている、みんなでチームを組んでやっている」という認識を持っている。今後はさらに、何か問題が起きた場合には、何が問題だったのか、どうすれば防げたのか、なぜかを追及して、次の手術に生かし、次の新しい戦略や術式につなげることが必要だと思う。
ただし、重大なことが起きたとき、一つの専門診療科では対応しきれない状況にある。そうすると病院として責任をとることになるが、病院長あるいは副病院長を含めた執行部が対応にあたることになる。つまり、診療に関わるメンバーが主体的に関与して意思決定や合意形成をするシステムが機能することが求められる。患者安全に資するためには評価項目を設定し分析していることが大切だ。医療の質の向上を図るためだ。診療を止めるためではない。
誤解してならないのは、今までチャレンジして手術の技量を上げ、術式を開発してきたが、これを止めたら新しい手術ができなくなるのではないか、と考えることだ。新しい技量を要する新しい技術を導入するには何が必要かをきっちりと議論して、合意してから、一歩進める。そのことも患者に正しく伝わるように説明する。新しい技術の手術を受ける、提供されると聞くと、患者はインフォームド・コンセントをお願いしますと言われても、身構える。その際には、この技術はまだ新しく導入されたばかりで、結果は定まっていない、ということも説明すべきである。繰り返しになるが、患者安全に資する質の向上に必要なものは何かを今一度検討し、それを徹底するのもガバナンスだ。
管理者に悪い知らせを聞かせる文化
マネジメントで有名なドラッカーは1993年の著書で「Measurable Eventsを設定して常に『測る』、改善につなげる」ことを提唱した。逆に言えば、「測れないものはマネージできない」ということだ。だから医療でも測れる項目を見つけて抽出し、常に測り続けて改善につなげていかなければならない。
このように考えてみると、私たちの認識には、大きな壁があるのではないか。自分たちの病院の中における、若干ネガティブな情報を公開するのを躊躇することだ。例えば、去年1年間、心臓手術で5%の死亡率があったとすれば、そういう数字を出すのには抵抗がある。病院ランキング本には年間150件といった手術件数だけが出ている。医療の質を件数だけで表しているわけだ。
しかし、そんなことはない。院内の診療情報をどのように収集して公開するか。そのためには医療を評価するための院内の規程が必要だ。診療科が提出してきたデータを鵜呑みにして、そのままホームページにアップするのも問題だ。そうではなく、病院として責任・承認したものを公開するべきだと思う。従って、社会と情報共有するための情報公開内容の審議やそれを承認する専門の部署が院内には要ると思う。
講演のまとめとして紹介するのは、安全文化とは「管理者に悪い知らせを聞かせることができる文化」である。これは、シドニー・デッカー先生の『ヒューマンエラーを理解する』という本からの引用である。私の解釈では、安全文化とは「ボスが悪いニュースを聞いてくれる文化」である。悪いニュースを報告してくれることは「Thank you」であり、職員と一緒に対応する体制を作り、責任を果たすことができる文化である。
医療現場の脆弱なシステムの中で、悪い知らせを報告してくれた職員や一生懸命診療にあたった当該職員を守ることが、病院のガバナンスを一歩進める。そして、実のあるガバナンスの実現に向けて改善を進める。変容の端緒はここにあるのではないかと思う。