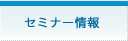河野龍太郎氏
2014年は大きな医療事故が相次いだ。東京女子医科大学病院、千葉県がんセンター、群馬大学病院で起きた事例である。これらは禁忌薬の投与や保健適用外診療といった、安全性が十分に確認されていない診療行為に伴って発生している。自治医科大学医学部の河野龍太郎教授は2015年11月22日に幕張メッセで開かれた「第10回医療の質・安全学会学術集会」で市立甲府病院の事例について報告した。
『小児への放射性医薬品過量投与事故調査と医療安全の問題』
自治医科大学医学部 メディカルシミュレーションセンター 河野龍太郎教授
事故調査で行うべき3つの分析
甲府病院の事例を報告する。本件は、市立甲府病院の小児RI検査において、8名の技師によって推奨投与量を大きく超過した放射性医薬品が準備されており、8名の技師と3名の看護師がそれらの放射能量を確認しないまま患者に投与し、検査を行っていたというものである。およそ12年間という長期にわたり異常は指摘されることなく継続され、この間延べ226人の患者に標準量を超える放射性医薬品が投与されていた。
事故調査には行うべき3つの分析がある。第1に死因究明。本件では死亡例はないが、なぜ亡くなったかという医学的因果関係の分析だ。第2に行動分析。関係者はなぜその判断をしたのか、行動の背後要因を分析する。第3にその他の分析。医療機器や材料などの問題を工学的因果関係から調べる。
立ち上げられた委員会は、RI検査問題について、事実確認と原因究明を行うとともに、その再発防止策を立案し、甲府市長に提出することを活動の目的とした。委員は5人。長尾先生が委員長、私が副委員長を務め、関本喜文(弁護士)、大野和子(日本核医学会専門医)、木田哲生(日本核医学専門技師)の各氏がそれぞれの専門家の立場で参加した。結果からいえば、非常に大変な作業であった。
各分野の専門家が独自調査で全容を公表
本委員会報告の特徴を端的に言えば、各分野の専門家が独自に調査し、事案の全容を公表したことだ。過去に院内の独自調査も行われている。
12年間に及ぶ長期の問題だったので、まずするべきは放射能量を再度推定することであった。それを踏まえて行動分析をしなければならないので全事例を時系列の一覧表にまとめる作業を行い、どのような状況下で、どれだけの事例が発生したかを全部確かめた。過量のセッティングをした技師長補佐がひとり自殺しているので、残念ながらこの人から話を聞くことはできなかった。
委員会活動が比較的うまく運んだのは、優秀な病院事務職員による地道な作業が行われたためだ。われわれがいくら頑張っても「推定原因」でしかない。すべての事故調査にいえることだが、真相は神のみぞ知る。所詮、われわれがどんな調査をしても、その結果は推定の域を出ないからだ。
特に、今回の場合、過去の話なのでヒアリングが重要な作業になる。しかし、その過程で記憶間違いの壁に阻まれる。いわば、ヒアリング調査の限界だ。本人に嘘をついているつもりはないが、記憶の変化が起こることがある。非常に難しい問題だ。そこで、われわれはできるだけ公平さを保つため、複数の調査員でヒアリングして、その概要を協力者自身に確認してもらった。
当事者はエラーをしたとは思っていない
私の担当は行動分析である。関係者の行動の背景をきちんと分析するのが目的だ。エラー分析ではない。行動分析では「なぜその人がそう判断したのか」「なぜ行動したのか」を分析する。
人間の行動モデルでは「エラーをした当事者はエラーをしたとは思っていない」という観点でものを見なければならない。例えば、ある人がプロポフォールを連続投与する場合、その瞬間、その人は、それが最も合理的だと判断して行動している。最終的に評価するのは別問題だという観点で見なければならない。
そうすると、準備の段階で自殺したA技師長補佐には放射性物質を過量に準備した合理的理由がある。(1)放射線量を増やすことで、診断に資する鮮明な画像を得たいという技師としての理想が主たるものであった(2)患者の入眠中に検査を短時間かつ1回で終了したい(3)短時間で撮像できれば、患者に睡眠薬を使用する頻度が減り、より安全に検査が施行できる(4)1回で検査を終了できれば、放射性医薬品を複数回投与しなくて済む――などということだ。
A技師長補佐の行動に潜む理由
他にも、A技師長補佐の行動の根底には「放射性医薬品を過量に体内に投与すれば放射線の減衰に時間がかかるため、その分、長時間の検査時間が確保できる」「検査をする側は患者が入眠するまでゆっくり時間をかけて待つことができ、落ち着いた状況の中で、鮮明な画像結果を得ることができる」という発想があったものと考えられた。さらにその背景には「A技師長補佐が放射線の影響を標準より過小に評価していたこと」「A技師長補佐の行動が発覚しにくい環境にあったこと」などが指摘できる。
12年間、正しく機能しなかった自浄作用
本件では、長期にわたり継続された理由が色々ある。異常と感じる職員がいながらも、そのことを医師や病院幹部といった放射線技師以外の管理責任者と共有できなかったことによる。
その原因は(1)放射性医薬品投与時における医師による内容確認の不履行(2)技師集団のRI検査に関する知識と経験の乏しさ(3)上級職による威圧的・高圧的言動による部下の萎縮=下の方が色々言っても上の方はつぶした。例えば、「お前がそんなことを言うのは10年早い、仕事を早く覚えろ」と部下は言われた。(4)技師間の情報共有の乏しさ――がある。
さらに(5)放射線を取り扱う専門家としてのコンプライアンス意識の欠如(6)報告行動への無理解と隠蔽体質(7)放射線科医師集団との接点の少なさ――などが複合的に影響して、技師集団内に消極的な隠ぺい・改ざん体質を生み、12年の長きにわたりRI検査室における自浄作用が機能しなかったことは極めて不適切である。
監督責任のある医師不在で起きた組織事故
本事案は、RI検査における放射性医薬品投与の実質的な監督責任を有する医師が不在の状況で発生した事態と捉えることができる。逆の言い方をすれば、医師の管理・監督のない環境が技師集団を自由にし、今回のような特異な診療行為の発生を許したのだ。
このような状況を長期間放置した当時の病院管理者や歴代の放射線科医、技師長には不作為としての課題が指摘される。さらなる背景として、長い間、我が国において、放射線科医、薬剤師、技師の間でRI検査体制の整備について十分な議論が行われず、放射性医薬品投与に関する責任が明確に定められないまま、技師に医薬品管理業務が委ねられてきたことが要因として存在する。これが、いわゆる組織事故である。
医療事故の犠牲者は2人いる
外部委員として参加する立場からの調査の教訓として、私は以前から「医療事故の犠牲者は2人だ」とずっと言っている。患者と医療従事者だ。患者は当然として、医療従事者が精神的なダメージを受ける場合が非常に多い。医療従事者のいい加減さが根本にあるわけでなく、医療は構造的に不完全なものだ。ここに問題がある。これをどう改善するか。
問題点を明らかにする手段は2つある。1つは起こった医療事故から学ぶこと。もう1つは潜在的なリスクをキャッチすることだ。潜在的なリスクキャッチには、ヒヤリハット情報を集めることが有効だ。これからやるべきは医療事故調査である。基本的な考え方は何か。同じ事故を二度と繰り返さないことだ。その時に遺族が納得したかどうかは全く関係ない。これは「2度と起こさないぞ」という強い意志をもって自分たちがやらなければならないことだ。だから、遺族は関係ない。
航空業界に比べて非常に少ない医療情報
特に私が一番問題にしているのは、関係者の行動の背景要因が十分に出ていないことだ。何が、どのように、なぜ、を踏まえて再発防止策をとる。そのためにはまずデータがなければならない。今回の事故調査で一番困ったのは、データの無さだった。
根本的に医療は情報が無い。主観的な情報はあるが、客観的なデータはほとんどない。私が長く関わってきた航空の世界ではかなりの再現性があり、色んなデータ類が残っている。だから、実態が明らかにでき、なぜ起こったかが明らかになる。ところが医療システムはまず情報がない。結局インタビューなどに頼らなければならないという限界がある。
整えられた、安全文化醸成のための体制
私は今年から東京女子医科大学の理事長特別補佐を兼ねて改革を支援している。女子医大病院に欠けていたものは「ガバナンス、医療安全文化、チーム医療」である。これらについては事故を契機に具体的な行動を取り始めた。例えば「医療安全・危機管理部」を平成27年4月に作った。組織的には理事長の下に医師、弁護士、その他事務の専門家が集まっている。「医療安全・危機管理部」は"日本で一番、謙虚に医療安全に取り組む組織作り"を目指している。
航空機の世界では、出発前に機長などが集まり「こうなったらこうしよう」などというブリーフィングをするのに、医療の世界ではそういうことが十分になされていないことを知り、非常に驚いた。今では女子医大病院は手術前にブリーフィングを当然としている。リスクの高いものについては、ハイリスク症例検討会や安全な医療推進検討会議を開いて手術に臨む。
安全文化醸成のための体制も整えられた。病院のリスクマネージャーは定期的に医療安全対策室にいて事故対応チームを組織し、事故が起こったら直ちにサポートにいく体制が作られている。「医療安全・危機管理部」では、事故対応チームにどのような能力が必要かなどを分析し、トレーニングマニュアルなどを作ろうとしている。
人間は、能力以上のことはできない
医療と航空をシステムとして比較すると、両者の違いが鮮明になる。1960年代は航空機事故が非常に多かった。しかし、時代と共にどんどん減っていった。なぜか。運輸安全委員会という常設機関が対応してきたからだ。この委員会は独立し、中立の機関としてプロフェッショナルの観点から分析した。初期のころはハードの問題が多かったが、今日では、行動分析が中心である。事故が減ったのは、事故調査をきちんとして対策を徹底的にとってきたからに他ならない。
今回の医療事故調査制度と違うのは、運輸安全委員会は国土交通大臣に勧告・意見する点だ。だから、強制力が全然違う。勧告を受けると、国土交通大臣はアクションをとらねばならない。具体的に事故調査をして対策をしたから変わって来たといえる。ヒューマンファクター工学の考え方として、どんなに優秀な人間でも情報がなければ正しい判断はできない。人は能力の範囲内でしか正しい判断と行動はできない。つまり、能力以上のことはできない。それが大原則だ。
「壊れている状態」が前提の医療システム
そういう観点で医療システムをみると、残念ながら医療システムにはたくさんの問題があり、解決は困難である。比較のために患者を制御対象と考えると、例えば、航空システムと原発システムには問題解決のための情報が最初からすべて揃っている。ところが医療システムは、患者が外来で受診する場合、患者の情報は限られており、医師が診断に必要かつ十分な情報を得ることは事実上不可能に近い。また予測もしにくい。必要な情報がないとどんなに優秀な人間でも正しい判断はできない。また、航空機も原発も「壊れていない状態」を基本的にオペレートしているが、医療は常に「壊れている状態」の患者をコントロールしなければならない。つまり、構造的な限界がある。
不完全なシステムの改良は難しい
今回の医療事故調査制度の目的は何か。不完全なシステムであるということを、病院だけではなく国民全体が理解しなければ問題解決にはならないと私は思う。患者も当然協力しなければならないし、このシステムを構成している全員が考えない限り、この不完全なシステムを改良するのは難しい。
そのためには事故調査報告書を書くときに、そのレベルまできちんと書くという観点が必要だ。そのためには行動分析のトレーニングをしなければならないだろう。死因究明は問題ないが、行動分析こそ極めて大事ではないかと思う。