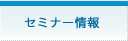東日本大震災から1年半。11月24日に大宮ソニックシティで開かれた「第7回医療の質・安全学会学術集会」では、震災のときに現場で対応にあたった医療者を迎え、医療安全の観点から「学んだこと、その後進んだこと」が議論された。パネラーの発言を報告する。
写真提供:第7回医療の質・安全学会学術集会 運営準備室
国立大学附属病院では
「東日本大震災時の大学病院の対応と国立大学附属病院の震災への準備」
藤盛啓成氏(東北大学病院医療安全推進室)
国立大学附属病院医療安全協議会は「東日本大震災の多面的検証と情報発信」プロジェクトを立ち上げ、国立大学附属病院と岩手医大、福島県医大を対象にアンケート調査を行っており、その結果、今後の課題が明らかになった。
被災地の各大学病院では、震災直後に深刻なライフラインの被害があった。東北大学(仙台市・震度6弱)は、停電6時間と都市ガス供給停止2週間、断水はなかったが、停電中はポンプや電動蛇口が停止したため、3月11日は夜まで水が使えなくなった。岩手大(盛岡市・震度5強)は停電2日間、福島県医大(福島市・震度5強)は断水1週間。筑波大(つくば市・震度6弱)は停電半日と断水2日間。なお、千葉大(千葉市・震度5強)については、トラブルはなかった。
設備では、東北大学で建物被害が発生し、特に耐震補強されていない建物に影響が大きく出たことがわかった。診療は、東北大、福島県医大では外来診療復旧まで12日と14日を要したが、入院中の給食は非常食などの対応でほぼ提供できた。
全国の大学病院では、耐震基準ができた1982年以前に建てられた病棟のうち、40%が耐震補強されておらず、耐震性に問題がある。自家発電装置はほぼ整備されているが、震災時には被災地以外の大学病院でも、停電やエレベーターの停止などが起こった。停電被害では、サーバー室の空調が非常通電対応になっていなかったために医療情報システムの停止が起こるという影響もあった。医薬品供給不足、医療機材納入不足もあった。被災地支援のDMAT(災害派遣医療チーム)を派遣した大学病院は30大学にのぼった。
現段階では、震災対応マニュアルはほぼ整備されているものの、東海地震を想定し、文科省に要望を提出している。具体的には、活断層対策の整備、自家発電能力の強化、発電設備の多くが地下にあることから津波対策強化などだ。原発事故対応については、原発から100キロ圏内に23施設があり、その内緊急被ばく医療施設に指定されている施設が11あるにもかかわらず、対応の遅れが目立つ。事故対応マニュアルが整備されている大学病院は46施設中5施設のみで、原発災害の訓練を6施設が行っているものの、独自訓練を行っているわけではない。
災害時の対策は、日常の業務の積み重ねの中で出来上がっていくものである。大学病院には特別に防災対策をリードする部署がないが、職員と患者の安全という観点から、医療安全対策室がその役割を担うことが重要だと考える。
石巻医療圏では
「東日本大震災への対応で学んだことと、今後の取り組みについて」
石井正氏(石巻赤十字病院外科)
石巻医療圏では震災に備え、2010年1月に、行政、消防、警察、医師会、自衛隊、DMATなどが集まり、「石巻地域災害医療実務担当者ネットワーク協議会」を立ち上げていた。「顔の見える関係を築いておくことが必要」と考え、地域の災害拠点病院である石巻赤十字病院が幹事役となって組織したものだ。宮城県では災害医療コーディネーター制度もつくられていた。石巻赤十字病院では、それに先立つ2008年時点で、マニュアルを改訂しており、それぞれの担当・責任の所在を明確にするなど、実現可能なものにスリム化を図っていた。
災害前にこうした体制ができていたことが、巨大津波の直撃を受け、死者3,134人、行方不明者1,012人という甚大な被害を受け、がれきの山と化した石巻市で、津波を免れた石巻赤十字病院に災害医療対策本部を設置することを可能にした。
震災の発生が3月11日午後2時30分、2時50分には院内が自家発電に切り替わり、3時25分には災害医療対策本部をつくった。その後すぐにトリアージエリアを設けた。救急患者は当日には99人だったが、これは、病院にたどりつけた人の数、ということであり、翌12日からは患者が急増し、震災3日間で2,000人を超える患者が搬送されてきた。症状は長時間水に浸かったことによる「低体温症」や、津波にのまれたことによる、津波肺炎などであった。震災から100日間で救急患者数は18,381人となった。
震災直後、石巻医療圏の避難所の数は300カ所以上(最大時328カ所)、避難所に入所している人数は4万人超であったが、通信事情も悪く全体の把握ができない状態だった。一方、全国から、救護チーム(その数は、最終的に3,000を超えた)が駆け付けたが、その人たちをどのように組織化し、混乱なく活動してもらうかが大きな課題であった。
そのため、救援に駆け付けた医療者らを全避難所に派遣し、数日間で環境・衛生・負傷者状況を把握。発災から9日後の3月20日、災害医療コーディネーターが一元的に統括協働する「石巻圏合同救護チーム」を発足させた。これにより、石巻市を中心に、東松島市、女川町を合わせたエリアで、統率のとれた救護活動ができた。感染症が起こらないよう、ラップ式トイレの配布や手洗い装置の設置などの対策をとった。
「合同救護チーム」が行ったことは、あらゆるデータを記録すること、対策を立てて実行しその効果を検証することと、通常の医療の中で行っていることと基本は同じだ。マニュアルではいろいろなことを想定する必要があるが、すべてを想定してしまうと、「想定外」のことが起こったときに対応できない。災害では、評論家は不要。マニュアルに振り回されずに、計画、実行、検証の繰り返しが最も重要である。
3.11の経験を踏まえ、次の災害に際しての「減災」対策への取り組みを始めている。1.他の災害拠点本部へのアドバイザリースタッフの継続的派遣、2.企業との連携、3.自治体災害医療対策人材育成などである。また全国の医療者によって、本年3月11日に災害時の医療活動を考え、支え、行動する「災害医療ACT研究所」を設立した。
在宅医療の立場から、二次被災地帯をどう救うか
「災害分布と災害時対応の類型等について」
川島孝一郎(仙台往診クリニック)
震災後、避難所に集まった人の数を、宮城県内の例で調べた。3日目には10万人、その後の2週間で32万人に増え、その後も長期的に避難所を活用した人は9万人だった。
家を流されたり自宅が崩壊するなどした直接的な被害を受けた地域を一次被災地域、ライフラインが断絶され自宅で生活できなくなった地域を二次被災地域とすると、一次被災地域の人は約9万人で、二次被災地域の人は約23万人と考えられる。この二次被災地域の人たちをどう救うかが、一次被災地域の人をどう救うかに次いで重要だと考える。
逆に、二次被災地域の救済がうまくいかないと、一次被災地域の救援もうまくいかないといえる。もちろん、それ以外の安全地域は放置してよいということではない。安全地域の人は、一次、二次の被災地の邪魔にならないように行動しなければ、一次二次の被災者も救えないことになる。具体的には不要なものを買い占めない、不要な電話をしないなどだ。
仙台往診クリニックは二次被災地域だが390人の患者がいる。人工呼吸器の必要な45人の在宅患者がおり、うち1人が津波でお亡くなりになり、44人の患者が助かった。3割の方は発電機やインバーターを持っていたため、人工呼吸器が使えたが、それも3日を過ぎると燃料がなくなり、我々も、ガソリンの供給も被災地に入ることもできなくなった。
厚生労働省が震災3日目には、往診の医師と看護師に緊急救急車両にするという認定をくれたため、12台の車両を出して、往診とガソリンの供給に回ることができたのは助かった。しかし、ヘルパー、ケアマネージャー、薬剤師や介護施設の職員には、そのような措置がなかったため、施設で患者が待っていても動きがとれないという問題が起こった。
結果的に、当院の在宅患者44人中6割は自宅に残ることができ、4割は入院することになった。しかし宮城県全体では200人の人工呼吸器装着者のうち、8割が入院した。
もし、事前に災害時の対策がとれていれば、この人々は、ヘリや救急搬送者などを使って病院に搬送されることにならなかった。そして、その分、一次被災者の救済活動ができたことになる。このように、自助、共助、公助のうち、「自助」の備えを行うことが共助・公助を拡大することにつながる。
福島原発事故については、仙台は欧米政府が自国民に避難を呼びかけた100km圏内に入っていた。もし、その人々が実際に避難しなければならないということになったとき、400人近い患者が他の診療所で診察を受けることを想定して、医療情報提供書を準備しなければならないということになる。
これらのことから、教訓として、ICF(国際生活機能分類)に基づいて、今回の震災の被災状況を分類する必要性を考えている。阻害因子は何か、環境因子は何かを明らかにして、それに対する備えを行えば、自助の範囲を広げることができるからである。
災害支援ナースの派遣を通じて
「災害支援ナースのあり方について」
石井美恵子(日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程救急看護学科)
日本看護協会と都道府県看護協会は、阪神淡路大震災の教訓から、大規模災害発生時に円滑な看護支援体制を行うシステムを構築してきた。そのマニュアル、シラバスの見直しを行い、指導者育成に取り組むところで、東日本大震災が起こった。
迅速な対応をとり、それまでの取り組みを生かすことができ、災害支援ナースをのべ3,770人派遣し、石巻市を中心に看護師を派遣し、コーディネーターの元に活動してきた。
この活動の結果、災害支援ナースの登録者が震災前は約4,800人だったが、震災後7,000人以上に増えた。このなかで、コーディネーターの役割について、より明確にする必要があるということ、また、リスク分散という考え方から、本部をどこにおいても同じ活動ができるのか、ということなど、いくつか課題があきらかになった。
まず、平時の備えの重要性。これは当たり前のことだが、当たり前のことがなかなかできない。災害時の看護には看護の知識の絶対量、さらに、災害看護の特殊な知識、指導するうえでは考える力が必要である。災害支援では、論理的な思考や対人関係の力量、コンサルテーションやマネージメントなど総合的な実践力が問われるが、これらは平時にも必要な能力であり、平時にできないことは危機の時もできないという認識が重要だ。
災害支援ナースのコーディネーターには、経験が重要だが、現状では海外の災害地で経験を積もうと思えば、職場をやめなければならない。日本国内での災害支援活動を行う体制づくりには、国際舞台にスタッフを派遣する体制が必要だ。
また、避難所における最低基準の必要性は、二次災害の防止対策の上でも重要である。アメリカのハリケーン災害でオバマ大統領が緊急事態宣言を出し、「全員避難してください。避難をしないで残った住民は救助しません。救助隊が危険にさらされます」と明言した。日本では、津波被害を受けた地域で、ブルーシートで覆った避難所が長期で置かれた例もあり、二次被害防止の姿勢、最低基準を満たす避難所という方針をしっかり打ちだすことが必要だ。飲み水はあっても、手を洗う水の用意ができない、20人が限度のトイレを50人が使用するといった、途上国の最低基準さえ満たさない避難所があった。
今回の支援では、行政が何を考えているのか見えないことも多々あり、問題解決が遅れたり、医療保険と介護保険がわかれているために、対応が遅れたり、もともとのシステムの脆弱さや矛盾点が露呈した。これをきちんと総括して、平時に立て直すことが重要である。
ボランティアナースの経験から何を学ぶか
「災害は国・地域・専門職の間に境界はないことを知っている」
田村由美(滋慶医療科学大学院大学 医療管理学研究科)
兵庫県看護協会の災害支援ボランティアナースとして、気仙沼での災害支援活動に4月2日から10日まで参加した。
インタープロフェッショナルワーク(IPW:他職種協働実践)の観点から、災害支援のあり方を見ることは、医療の安全、質に大きく関連すると考える。
災害においては、日頃からのネットワークが非常に重要な意味を持ってくる。私は、Gibbsのリフレクティブサイクル(経験を振り返り、気付きにもとづいて実践する手法)を用いて、経験から学ぶという看護教育をしているが、被災地に初めて入ったときは、大変に戸惑った。避難所で何が行われているのか、状況が把握できず、自分がどういう仕事をするのか、誰と活動すればいいのかわからず、茫然とするしかなかったからだ。
しかし、それまでのパキスタンやケニアなどでの支援活動、国内での水害時の支援活動の経験や、誰とでもすぐに打ち解けられる性格、排泄のケアについて専門知識を持っていることから、仮設トイレの衛生問題の解決など、自分の役割をその中に見出し、活動することができた。災害支援では生命・健康を守るということが最重要であり、それぞれの専門職が職種による専門性を生かしながら、協働することが大切であることを実感した。それを今後の教育に生かしていく。
まとめ
最後に、座長の藤盛啓成氏より、「田村さんの発表にありましたように、経験から学ぶということが非常に重要です。本日のみなさんの報告を、ぜひ、今後の活動に生かしていただきたい」と、締めの言葉があった。