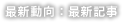NTT東日本関東病院(東京都品川区、606床)の看護部は、インシデントの発生要因を特定するためのツールの開発に取り組んでいる。リスクが起こった場所に着目し、それを視覚化することによって、インシデントの背景やリスク要因を明らかにしようという試みだ。その取り組みを取材した。
インシデントの発生場所からリスク要因を追跡
「インシデントレポートを数量的に分析しても、効果的な事故対策には結びつきにくい。いかにインシデントが起きた背景や要因を導き出し、それに応じた対策を講じられるかが大事」
そう語るのは、NTT東日本関東病院看護部長の坂本すがさんだ。医療現場では複数の業務が同時並行的に行われている。それだけにインシデントが起こる原因も単純ではない。 そこで坂本さんらは、2004年度の厚生労働科学研究(医療機関における安全管理システム開発におけるリスクマップの構築およびリスクマネジャーの有用性に関する研究、主任研究者=坂本すがさん)で、インシデントの発生要因を明らかにするための方法論を研究した。それがリスクマップを用いた分析手法だ。
リスクマップは、インシデントが業務フローのどこで発生したかが一目でわかるもの。インシデントが発生しやすい場所(業務ステップ)を明らかにすることで、業務フローのどこにリスクが潜んでいるかを特定出来る。つまり、的を絞った対策が検討しやすくなるというのだ。
場所に着目したのは、坂本さんが麻薬に関するインシデントの原因を追跡した経験がきっかけとなっている。当時、麻薬のインシデントの多くは、ナースステーションの処置台や患者のベッド周りで起こっていた。だが、その中に病室の流し台や洗面所で発生している例が少数ながらあった。なぜ、そんな場所で発生するのか-。疑問に思った坂本さんが当事者に確認したところ、服用のための水を準備していた看護師が、手に持っていた麻薬を流しにうっかり落としてしまい取り替える必要が生じたために、インシデントになっていたことがわかった。
「インシデントが起こる場所に注目したら、それまでわからなかった原因が特定出来た。他の薬剤も同じように追ってみれば、これまで見えなかったリスク要因がわかるのではないかと考えた」と、坂本さんは話す。
図表1と図表2は、坂本さんらの研究グループが作成した同院の与薬と注射に関するリスクマップである。40例のインシデントレポートを対象に、どの段階でインシデントが発生しているかを業務フロー図に落とし込んだものだ。フロー図に書き込まれた数字は、各インシデントに付けられた番号だ。
このリスクマップを作成する手順は次のとおりだ。まず、与薬と注射に関する業務フローを、担当者がインシデントレポートを参考に作成する。それを病棟の職員に見せて、実際の業務フローを確認。その内容を業務フロー図に書き加えていく。ここでは業務フローの正否は問わず、あくまでも実態を書くのがポイントだ。図表1のとおり、患者に薬剤が投与されるまでには、いくつもの複雑なルートがあることがわかる。
次に、インシデントレポートの提出者に、インシデントの詳細状況を所定の書類(詳細状況記入用紙)に記入してもらう。この書類は、時系列でインシデントの当事者や関係者が、何を実施したかがわかるようになっている。これにより、インシデントレポートからだけではわからない、インシデントの発生要因を探る。
さらに、インシデントレポートの提出者や関係者を対象に、担当者が聞き取り調査も実施する。また、各病棟の関係者に集まってもらい、90分程度のフリーディスカッションも行う。時には医師にも参加してもらう。これらは各病棟の業務の実態を明らかにするのが目的だ。
続いて、詳細状況記入用紙と聞き取り調査した内容を、所定のマトリックスに書き込む。マトリックスの縦軸には事例の内容が、横軸には業務フロー図の各ステップが記載されている。詳細状況記入用紙と聞き取り調査などで明らかになった各インシデントの要因を、マトリックスに記入(図表3参照)。それを基に、与薬と注射の業務フロー図に番号をプロットすればリスクマップが完成する。すると、業務プロセスのどの段階にインシデントが集中しているかがわかる。
リスクマップで明らかになったリスク要因
研究グループがこの方法で与薬に関するインシデント状況を追跡した結果、与薬のリスク要因が集中しているステップは次の3つに集約された。それは、1.医師がオーダーする段階、2.看護師による指示確認をする段階、3.実施のための準備と患者に実施する段階だった。
それら要因を詳細に見てみると、医師がオーダーする段階では、「指示の意図がわかりにくい」「指示のタイミング」「口頭指示」に、リスク要因が存在していることがわかった。
看護師による指示確認をする段階では、「ダブルチェック(ダブルチェック後にミスが生じている)」「複数の指示を受けた時の処理」「伝達ミス」「指示書で薬品を確認しなかった」が、リスク要因として挙がった。
さらに、実施のための準備をする段階では、「交代時に他の看護師に依頼することを忘れた」「使ってはいけない薬を伝達しなかった」「他の患者の点滴と間違える」「薬の置き場所を間違える」「薬の詰め間違い」があった。
また、患者に与薬を実施する段階では、指示書と患者のリストバンドと薬剤を照合することになっているが、指示書を持たずに患者に与薬したり、リストバンドの照合をしなかったために、患者の取り違えを起こしていた。
「リスクマップでインシデントを可視化することによって、これまで見えなかったリスク要因が見えてきた。これからは、それらリスクに焦点をあてた対策を検討していきたい」と、研究に携わったNTT東日本関東病院副看護部長の山元友子さんは話す。
リスクマップを作成するポイントは、「薬の旅」を確認するつもりで実態を把握すること。それには関係者からの聞き取りが不可欠であるという。
「インシデントの当事者や関係者が、何を考え、何をするつもりで行動したのかを、聞き取りで丁寧に拾っていくことが大事。インシデントの状況や業務の実態を自由に話せる場を設けることも有効」と、同じく研究に携わった同院看護長の堀川慶子さんは述べる。
インシデントレポートを事故対策に活かすために
研究グループは、転倒・転落に関するインシデントレポート392例についても、リスクマップを作成(図表4)。これは与薬のリスクマップとは異なり、業務フロー図は作成しない。院内の間取りを図にして、インシデントがどこで発生したか、場所を特定していくものだ。
ただし、この方法だとインシデントの概要は把握出来ても、その原因や発生要因は特定しにくい。そこでインシデントが起きた当時の様子を、患者と医療従事者から聞き取り、詳細な状況把握に努めた。さらに、インシデントの再現検証も試みた。検証の場面には、当事者だけでなく、建物のメンテナンス業者や脳外科の医師なども加わり、インシデントの発生要因を検討。その結果、思いもよらないリスク要因が存在していた事がわかった例もあるという。
それは歩行器を利用している患者が、廊下に埋め込まれた照明灯につまづいて転倒し、右手を骨折したインシデントだ。当初は転倒の原因が照明灯の段差(3mm)にあると考えられていたが、現場で再現検証した結果、歩行器の使い方に問題があることが判明した。つまり、患者のADL(日常生活活動)から判断すると、その歩行器を使うのは適切ではなかったのだ。
「さまざまな立場の人が、視点を変えてリスクを検証する必要性を痛感した。こうした場面に職員が参加することによって、リスク感性が高められ、医療安全に関する知識の獲得にもつながるはず」と、坂本さんは期待を込める。
同院ではこの検証をきっかけに、歩行器の適用判断や正しい歩行器の使い方についての研修を企画し、看護師向けに実施するようになったという。
一方、今回の研究によって、従来のインシデント対策の課題も明らかになった。与薬業務には薬の種類、処方方法、途中の指示変更などにより、業務フローに多くのフローラインと分岐点が存在する。だが、それらは標準化した既存のルールやチェックではカバーしきれないことがわかった。
また、従来はインシデントが発生する度に、ミスを回避するためのルールを追加したり、チェック体制を強化していたが、それらが業務の硬直化と職員の負担感を増加させていたことも明らかになった。
「チェック機能の形骸化が生じている面も見受けられた。マニュアルやチェック体制は、与薬や注射といった業務単位で設定されている。それらは単独では問題ないが、多くの業務が同時平行している医療現場では、フローを妨げる原因になっているかもしれない」と、坂本さん。今後は、業務フローの実態に応じた事故対策をいかに提示していけるかが課題だ。
「インシデントレポートからだけでは、リスク要因を導き出すのは難しい。だが、リスクマップを用いて、何が起こったのか実態を把握しようと努めれば、リスクの背景など業務の全体像が見えてくる。リスクの可視化は頭の整理にもつながるので、ぜひ多くの人にこの方法を知ってもらいたい」と、坂本さんは話している。