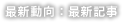病気の診断には、さまざまな検査が用いられる。X線撮影をはじめ、CT(コンピュータ断層撮影)やMRI(磁気共鳴画像)による検査など、高度な医療装置を使用するものもある。これら検査や画像診断などを行う放射線科においても、医療事故というリスクは常につきまとう。具体的にどんな対策が必要なのか、東邦大学医学部附属大橋病院(東京都目黒区、513床)の放射線科を訪ね、話しを聞いた。
被曝に対するリスクを最小限に
「検査には放射線を使うものがあるため、まずは被曝に対するリスクに注意を払う必要があります」と言うのは、東邦大学医学部附属大橋病院の放射線科医師である五味達哉さんだ。
同放射線科では、他の診療科から依頼されてさまざまな検査を実施したり、がん等の患者に放射線治療を実施している。中でも五味さんは、主に画像診断を担当する。各診療科から依頼された検査が患者に相応しいものかどうかを判断し、実際に検査された画像を診断して読影レポートにまとめ、診療科の医師に報告している。
最近では、国立弘前病院におけるがん患者への放射線過剰照射事故が問題になっているが、「検査においても、必要以上の被曝は避けること」と、五味さんは指摘する。
例えば、放射線を使う画像検査の1つであるCT検査。同院では、大人と小児でそれぞれ撮像条件を異にしている。
「病院によっては、小児も大人と同じ条件で撮影するところがありますが、小児は大人よりも体格が小さいため、X線量を減らして撮影しています」と、同院の放射線技師長補佐である新木操さんは言う。
また、撮影部位によっても必要なX線量が異なるため、照射条件を変更することで、必要以上の被曝を防いでいる。
不必要な被曝を避けるという意味では、患者や撮影部位の間違いにも気を配らなくてはならない。万一、撮影のやり直しとなれば、患者への負担が大きくなるからだ。
ところが、この種のインシデントは意外に多い。山形県放射線技師会が、2002年に会員に対して行ったアンケート調査によると、放射線科において起こりやすいインシデント事例として、「患者の間違い」「部位の左右間違い」「患者名の入力ミス」などが多いことがわかった。
「当院もオーダリングシステムが導入されてから、医師の入力ミスによる部位の間違いが見受けられるようになった」と、五味さんは語る。
そのため、CT検査前には、あらかじめ患者のカルテに目を通してチェックすることを欠かさない。元々、各患者の検査目的や、診療経過を確認するためにカルテを見ていたのだが、それが事故防止にも役立っているという訳だ。
もちろん、受付の段階においても、患者に名前と生年月日を言ってもらったり、検査室で診療放射線技師が患者の名前を確認するなどの方法もとられている。患者や部位の間違いを防ぐために何重ものチェックが必要なのは、他の診療科と変わらない。
MRI検査における注意事項
放射線は用いないものの、強力な磁気が発生しているMRI検査においては、患者への適応や入室時に特別な注意が不可欠のようだ。過去にはアメリカで、MRI検査室内に持ち込まれた酸素ボンベが磁気の力によって飛び、それが小児の頭部を直撃したため、脳挫傷で死亡するという事故が起きた。
「MRI検査室内には、磁性体の室内持ち込みは厳禁です。持ち込まれると、患者に危害を与える恐れがあります。たとえ検査が行われていなくても、常時、静磁場が発生していますので、注意してください」と、前出の新木さん。
一般的に使われている車いすやストレッチャー、点滴台などは磁性体であるため、MRI検査室に入る前には、非磁性体のものに変更しなければならない。同院では検査室の前に設置された前室において、それらに変えることになっている。見た目には磁性体と非磁性体の区別がつかないものについては、カラーテープを張って、その違いがわかるように工夫している。
他にも、時計や電子機器、人工呼吸器などの医療機器も持ち込み禁止だ。体内にペースメーカーなどの電子電気部品が埋め込まれた患者も不適応となる。脳動脈瘤クリップの中には非磁性体でないものもあるため、注意を要する。
「これら注意事項を日頃はわかっていても、診療科の医師の中にはまれに金属類を身に付けたまま入室しようとすることがあるが、危険なので止めてほしい」と、五味さんは注意を呼びかける。

強力な磁場が発生しているMRI検査室の入口には、入室の際の注意事項が掲示されている。
救急時やたまに来訪する医師や看護師などの所持品にも注意が必要となる。
造影剤のリスクへの対処
検査の中には、造影剤を使用するものもある。血管造影検査や、CT検査、MRI検査などで用いられる。
「造影剤を投与すると、一定の割合で副作用が起きることがわかっています。まれに、アナフィラキシー(注)反応によるショック死も起こり得ます。造影剤による副作用歴をはじめ、気管支喘息やアレルギー症状の有無などがあれば、副作用のリスクが高まるため、造影剤の投与を中止します。腎機能の低下している患者もリスクが大きい」(五味さん)
- (注)
- 【アナフィラキシー】 anaphylaxis
ある抗原によって感作された生体が、再びその抗原にさらされたとき、その抗原が肥満細胞や好塩基球に固着した抗体(ヒトの場合はIgE抗体)と反応し、その結果これら細胞から脱顆粒によってヒスタミンなどの化学伝達物質が放出され短時間のうちにアナフィラキシーショックとよばれる急激な症状を引起こす現象をいう。
出典:CD-ROM最新医学大辞典スタンダード版(医歯薬出版株式会社)

CT検査を行うためのオペレーター室。
造影剤を注入中に、血管外漏出が起こっていないかどうかを観察するなど、
常に見守りが欠かせない。
通常は、検査を依頼する診療科の医師がそれらを確かめ、造影剤の投与が可能かどうかを判断することになるが、中には放射線科に患者が訪れた段階で判明する場合もある。
「診療科によっては医師の中に、造影剤の適用の可否について十分に理解していない人もいる。診療科での患者への問診はもちろんのこと、放射線科においても再確認することが不可欠です。患者に対しても、造影剤の副作用によるリスクを、どこでどのように説明するのか、院内で十分な話し合いをしておくことが望ましいでしょう」(五味さん)
放射線科における検査や治療は、他の診療科の医師からの依頼に基づいて行われる。それだけに情報のやりとりや、患者へのインフォームド・コンセントなど、互いの密な連携が欠かせないことがわかる。

左側が東邦大学医学部附属大橋病院の放射線科医師、五味達哉さん。
右側が放射線科技師長補佐の新木操さん。