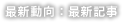児童虐待防止法の制定から17年になる。子ども虐待の発見・予防に医療機関、医療者が大きな役割を果たすことは言うまでもないが、児童相談所への相談経路を見ると、医療機関からの相談割合は全体の3%しかない。児童虐待防止において、今、医療者に求められていることは何か。長年、医師の立場でこの問題に取り組んできた山田不二子氏に話を聞いた。
- プロフィール
-
- 医師・医学博士
- 医療法人社団三彦会 山田内科胃腸科クリニック 副院長
- 認定特定非営利活動法人チャイルドファーストジャパン(CFJ) 理事長
- 特定非営利活動法人かながわ子ども虐待ネグレクト専門家協会(KaPSANC) 副理事長
- 一般社団法人日本子ども虐待防止学会(JaSPCAN) 理事
- 一般社団法人日本子ども虐待医学会(JaMSCAN) 理事 兼 事務局長

理事兼事務局長 山田不二子医師
児童虐待の定義と現状
医療者には児童虐待防止法で「児童虐待の早期発見等」(第5条)と「児童虐待の通告」(第6条)という役割がある。
では、子ども虐待とはどんなことを指すのか。厚生労働省は身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待にわけ、以下のような具体例を挙げている。
| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など |
|---|---|
| 性的虐待 | 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする など |
| ネグレクト | 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など |
| 心理的虐待 | 言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(ドメスティック・バイオレンス:DV) など |
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/about.html
児童相談所への児童虐待相談対応件数は、統計を取り始めた平成2(1990)年以来、増加の一途をたどり、平成27(2015)年度には103,260件とついに10万件を超えた(厚生労働省調べ)。虐待の種類別内訳は、身体的虐待28,611件(27.7%)、ネグレクト24,438件(23.7%)、性的虐待1,518件(1.5%)、心理的虐待48,693件(47.2%)となっている。
死亡事件も毎年50~60件、週に1回のペースで発生し、深刻な状況は続いている。
「平成27年度児童相談所での児童虐待相談対応件数<速報値>」より
参考URL http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000132366.pdf
日本の虐待問題のパイオニア、坂井聖二医師
虐待に関しては、「児童福祉法」に「通告の義務」などが盛り込まれていたが、有効に行使されていなかった。
日本で虐待が社会的に認知され、取り組みが始まったのは平成2(1990)年頃からだ。平成2(1990)年、大阪に「児童虐待防止協会」(現在はNPO法人化)、翌年に東京に「子どもの虐待防止センター」(現在は社会福祉法人化)ができ、どちらも当時は任意団体として電話相談を始めた。すると、母親たちから子どもを叩いてしまう、かわいいと思えないという相談が数多く寄せられたのだ。
厚生省(当時)が虐待の統計を取り始めたのも平成2(1990)年からだ。しかし、虐待の診断に必要な知識を持つ医師は日本にはおらず、パイオニアの一人と言ってよいのが「子どもの虐待防止センター」に設立当初から関わり、後に理事長となった小児科医の坂井聖二医師だった。
坂井医師は虐待の発見および立証という、医療者としての2段階の役割を果たしていた。そして、米国の専門書『虐待された子ども』の翻訳出版(明石書店・平成15年)、日本初の専門書『子ども虐待の臨床-医学的診断と対応』(南山堂・平成17年)など、多くの貴重な著作を残したが、平成21(2009)年に病死。同年、その遺志を受けて「日本子ども虐待医学研究会」(現在は一般社団法人日本子ども虐待医学会)ができた。
日本子ども虐待医学会の活動
「日本子ども虐待医学会」(当初「研究会」、平成26(2014)年に改称、平成27(2015)年に一般社団法人化)の会員は、当初から、医師に限らず、虐待発見に関わることの多い看護職、医療ソーシャルワーカーなど医療職全員に広げた。現在は会員数312人、小児科、児童精神科、放射線科、脳神経外科、整形外科、公衆衛生、法医学、歯科法医学などさまざまな領域から医療者が参加している。
活動内容は、年1回の学術集会のほか、学術集会期間中に会員限定参加で行われる「事例検討会」、非会員医療者、児童相談所職員、警察官、検察官等の関係者も参加できる「事例検討会」が各地で開催されている。
子ども虐待への医療者向け啓発マニュアルとして幅広く使われている、「一般医療機関における子ども虐待初期対応ガイド」(ガイドと略)は、同学会副理事長の奥山眞紀子医師(国立成育医療研究センター こころの診療部)を研究代表者、山田医師を研究分担者にして行われた厚生労働科学研究の成果だ。
医療機関向けの虐待対応プログラム「BEAMS」
「日本子ども虐待医学会」は、医療機関向けの虐待対応プログラム「BEAMS」により、虐待問題にかかわる医療者の養成を行っている。「BEAMS」は3ステージから成り、ステージ1は「虐待の早期発見と通告の意義を理解し、医療機関でのSentinel(歩哨・見張り番)として適切な行動がとれるようになること」が目的だ。ステージ2は「披虐待児の安全を担保し、地域、医学診斷をネットワークに的確につなげるようになること」。ステージ3では「虐待対応の医療的リーダーシップ」を目的にしている。
山田医師は、アメリカでの「性虐待被害児の医学的診察に関する臨床研修」をはじめとするさまざまな研修に参加し、診察、司法面接など専門性を習得しており、その経験から、「BEAMS」の講師としての活動も担っている。
「ステージ1」では、上記の「ガイド」を公認マニュアルとして使っている。
「医療機関に虐待が疑われる子どもさんが来たとき、何の対策も打たずに再び家庭に帰してしまうと、5%が死亡、25%は再受傷にいたる(『ネルソン小児科学』17版)と言われています。虐待の見逃しがないよう、知識と手順を学んでもらうのがステージ1です」と山田医師。
具体的には周辺状況、身体症状、重症度判定の目安、虐待鑑別疾患、虐待医学診断のための初期検査を知ることになる。
参考資料:日本子ども虐待医学会「一般医療機関における子ども虐待初期対応ガイド『通称:一般医向けマニュアル』」
http://jamscan.jp/manual.html
また、同学会は、虐待による乳幼児頭部外傷(Abusive Head Trauma: AHT)をテーマにした「AHT研究部」を作り、犯罪性の立証に関わる臨床医や法医学者と、会員以外の検察官、人間工学の研究者との連携も始めた。事故か虐待か、検察も立件に困難を極めている「AHT」というワンテーマでの連携を通じ、人間関係、信頼関係を深める試みが行われている。
「早期発見・通告」を妨げるものは?
「BEAMS」ステージ1の目的でもある、「早期発見・通告」の現状について山田医師は次のように話す。
「日本では、児童相談所への全通告のうち、医療者からの通告が3~4%にとどまっており、諸外国の約8%という数値と比べ、少なすぎると思います」
その要因として推測されるのが、「院内虐待対応組織」の「形骸化」だと山田医師はいう。
現在、医療機関において、虐待問題に取り組む体制としてもっとも確立されているのが「院内虐待対応組織」(Child Protection Team:CPT)である。これは、平成21(2009)年の「臓器の移植に関する法律」改正に伴い、児童からの臓器提供を行う施設になるためには、「(1)虐待を受けた児童への対応のための必要な院内体制」と「(2)児童虐待の対応に関するマニュアル等の整備」という2つの条件が必要になったことに関連する。これにより、全国の約500の医療機関に「院内虐待対応組織」(名称は医療機関により違う)ができた。臓器提供施設でない医療機関で「院内対応組織」を持つところもあるので、「院内虐待対応組織」をもつ医療機関はどんどん増加している。
院内対応組織がある医療機関には、虐待対応の医療ソーシャルワーカー、医師など担当者がおり、疑いがあれば「虐待対応委員会」も開かれることになっているが、十分に機能を果たしていないところもあるのではないかと山田医師は見ている。
「主治医や看護師らは、いろいろな場面で子どもをしかる親などを見る機会が多いため、虐待を心配して上司等に報告するのですが、正式に委員会開催にまで至らないことが多いようです。たとえば、乳幼児揺さぶられ症候群(Shaken Baby Syndrome: SBS)を脳外科医が見て、『転んだだけでもこうなる』と判断したり、小さな子どもの膣に異物が入っているときに、母親から『子どもが自分で入れたんだと思う』と言われて疑わずに信じてしまうこともある」(山田医師)
とくに難しいのは、2歳未満の乳幼児の診断だ。体表外傷がなくても、乳幼児揺さぶられ症候群等の「虐待による乳幼児頭部外傷」や腹部鈍的外傷、骨折などは判別しにくい。被虐待児の除外診断用に作られた「脳死下臓器提供者から被虐待児を除外するマニュアル」(山田医師らの研究による)のチェックリストを活用し、必ず必要な手順を踏むことが大切だという。
他機関との連携の重要性
医療機関からの通告数の少なさには、関係機関との連携不備という問題もあるのではないか、と山田医師は推測する。
虐待の疑いがある場合、医療者には、児童相談所の調査、警察の捜査への協力、司法手続きにおける犯罪性の立証という役割がある。
しかし、まだ関係諸機関との連携は十分とはいえないのが現状だ。
「児童相談所は医療者を調査協力者と見ていても、多忙のため情報のフィードバックをしてくれないことがあります。警察にとっては、医療者は情報提供者でしかないのか、情報は取るけれど戻さないことが多いのが現状です。すると、協力したのに、何だ、ということになります。情報も共有するところはしていかないと、知識も経験も人間関係も積み重なっていかない。他機関との連携は暗中模索の段階で、まだシステマティックにかみ合っていないのが現状です」と山田医師はみている。
虐待の予防、発生リスクへの対応
医療者には、虐待が起こる前に、発生リスクを感知し、虐待を予防するという役割も求められる。
「院内虐待対応組織のない小規模の病院やクリニックの医療者にとくに期待したいことは、虐待の発生予防という役割です」と山田医師はいう。
児童虐待のリスク要因として、経済困窮家庭、ひとり親家庭などの経済的な要因や親子関係、養育環境などが挙げられるが、児童、親を観察することで虐待のリスクが推し量れることも多い。
「洋服の汚れ、お風呂に入っているかどうか、身体の不衛生さや体重減少、体重増加不良、病気、むし歯などの放置など、注意深く観察してください。医師の前で子どもを怒鳴っている場合は、家庭ではより激しい態度をとっていると想像がつきます。ネグレクトも開業医が発見に関わることは可能です」
ハイリスク児発見時の対応としては次のようなことができる。
「対象児童が入院している場合は、児童相談所に通告後、児童相談所職員に待機ないしは同席してもらった体制で虐待の疑いを親に告知することになりますが、外来でそれをやると、親はもうお子さんを連れてこなくなり、より危険です。外来対応の症例については告知しないで、親に対し、『お子さんの様子が心配なので○日にまた来てください』と再診でつなぎ、親との信頼関係ができたところで、『自分としてはまだ心配なので、保健師さんに様子を見てもらってもいいですか?』とその場で保健師と連絡をとり、親につなぐようにします。それができないときは、親のいないところで、市町村の虐待対策組織である要保護児童対策地域協議会に情報を提供します」
通告は親を裏切る行為ではない
通告をためらう要因は他にもある。
「医療者は良心的なので、通告というのが、親を糾弾するようで抵抗があるのです。しかし、どんなに痛いことをする親でも子どもを愛しているし、子どもは親が好きです。親子、家族を引き離すことが目的ではなく、子どもの安全のために必要なことだと考えてほしいと思います」(山田医師)
山田医師が見てきたケースの中には、被害を受けた児童を児童養護施設に入れても、夏休みに家にもどってまた虐待を受けた子どももおり、児童相談所と市町村の要保護児童対策協議会が連携して、養育環境が整うまで、継続して子どもを守るという視点が重要だ。
「医療者は社会的ステータスが高いために、間違った通告をするぐらいならしない方がいいと考えることも多い」と山田医師は言う。
「通告して調査したら虐待ではなかった」という「ハッピーエンドの結果」が最も望ましいのであり、法的にも「故意の虚偽通告」でない限り責任を問われることはない。「誤通告は免責される」というのが原則だ。個人情報についても、虐待の通告は、児童虐待防止法で「個人情報保護規定の免責」の対象になっている。
諸外国の児童虐待防止にも詳しい山田医師によると、虐待の通報、通告に警察、検察にかかわる「司法小児科医」という分野が発展して、アメリカ医学会の専門医制度の中に「子ども虐待小児科医」が制度化されている。
「アメリカでは専門化が進み、一般の医師がすぐ専門医に委託してしまうという悪い面も出ています。日本には専門医制度こそないものの、通告や院内虐待対応組織、虐待診断マニュアル、地域の要保護児童対策地域協議会など、必要な体制はできています。あとは、こうした体制をどう活用するか、それにかかわる人材をどう育てるかが課題だと思います」と山田医師は話している。
企画・取材:山崎ひろみ