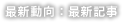がん治療の分子標的薬が相次いで承認されている。がん細胞に対する特異性が高く、従来の殺細胞性の抗がん剤によく見られた骨髄抑制(血球減少)や脱毛、消化管粘膜障害などの副作用がほとんどない、使用回数や期間に制限はなく年単位の長期投与も可能、薬剤によっては「効きやすい患者」「効きにくい患者」を事前に予測するバイオマーカー検査が存在しており、無駄な副作用の減少、医療費削減につながる。こういったメリットにより、がん種や病期によっては治療戦略が大きく変わりつつある。反面、薬剤それぞれ特有の副作用があって注意を要する。なかでも抗EGFR抗体薬やEGFRチロシンキナーゼ阻害薬、Bcr−Abl チロシンキナーゼ阻害薬というタイプの薬では皮膚障害が高率で随伴。痛みやかゆみによってQOLを低下させている患者が多く、対策が課題となっている。一方で国際的な臨床試験により皮膚障害の発現は分子標的薬治療が効いている指標になりえ、症状が強いほど生存期間が長いことが示唆された。これを受けて国内の関連学会は、皮膚障害が理由で分子標的薬治療が中止されることのないように呼びかけている。患者の中には、皮膚症状をコントロールしつつ分子標的薬をいかに長く続けるか、が生命線となっている人が少なからずいるからだ。こうした患者を継続的にサポートしていくには、がんの主治医と皮膚科医、看護師、薬剤師との連携が必須であり、そのための診療科あるいは施設を超えた協力体制の構築が急務だという。
分子標的薬の使用に伴う皮膚障害の診療やケアに慣れていない医師、医療スタッフも多い。そこで、その症状の特徴と見分け方、皮膚症状を悪化させない最新の治療法、患者を継続的にサポートしていく連携の築き方、それぞれのポイントについて取材した。
皮膚科学会で「対策マニュアル」を作成、メディアを通じた啓発活動も
2011年11月に日本皮膚科学会中部支部学術大会が開かれた。テーマは「他の診療科(general medicine)との連携」で、それに即して「分子標的薬皮膚障害対策マニュアル」が作られ配布された。大会会長でマニュアル作成を企画した三重大学病院皮膚科の水谷仁教授は、その巻頭で次のように述べている。
「現在、他科より皮膚科医に求められる知識・技術の1つが急増する分子標的薬とそれに伴う皮膚障害対策です。分子標的薬は数も多く、その皮膚障害も多彩であり、従来の薬剤による障害イコール薬剤中止といった図式ではなく、患者の生命予後をまもるため、皮膚障害と薬物治療の並存という高度な対応が求められている病態です」

マニュアルは医薬品メーカー各社から提供された対策資料をコンパクト(47ページ)にまとめたB5版の冊子で、代表的な分子標的薬8つが取り上げられている。それぞれの項目に多少の違いはあるが、薬剤の効能・効果、用法・用途に始まり、作用機序、皮膚障害の発現率、軽度・中等度・重度のグレード判定ポイント、グレード別対処法フローチャートなどが、豊富なイラスト、表、写真付きで解説されている。作成にあたっては「全国の皮膚科医が使えるマニュアル」を企図したという。マニュアルは1分科学会としては異例の5,000部という大部数が刷られ、三重大学医学部皮膚科のホームページからもダウンロードができるようにしてある。「対策」のすみやかな普及を意識したからだ。
分子標的薬の使用に伴う皮膚障害については、がん患者や家族にもさほど知られておらず、メディアを通じて一般への啓発活動も始まっている。本年(2012年)3月にはNPO法人JASMIN主催の「プレスセミナー」が開催され、マスメディアの記者を中心に50名強が参加。国立がん研究センター東病院消化管内科・吉野孝之医長は、がんの主治医の立場から最新知見に基づく「対策」の実際を、東京女子医科大学皮膚科学分野主任教授で日本皮膚科学会理事でもある川島眞氏は、皮膚科医を対象とした皮膚障害の診療経験に関する実態調査および意識調査の結果を講演した。それをもとにして数日後には全国紙や地方紙、医療系webサイトなどに記事が掲載された。
がん治療における分子標的薬とは
最近の分子工学の発達により、がん細胞の増殖や転移に関わる遺伝子、タンパク質などが次々と明らかにされている。がん治療における分子標的薬は、その特定の物質を標的として機能を弱め、がんの増殖・進展を抑制するという明確な狙いのもとに開発される。候補物質にがん細胞殺傷効果があるかを手当たり次第に試して薬にしていくこれまでの殺細胞性の抗がん剤とは開発コンセプトが大きく異なる。
現時点で判明しているがん細胞の増殖や転移に関わる遺伝子(がん遺伝子)で代表的なのは、Ras、Myc、Bcr−Abl、HER2、EGFRなどだ。反対にがんの発現や増殖、転移を抑制するがん抑制遺伝子にはP53、RB、P16などがある。
前出の吉野医長は、分子標的薬ががんの増殖を抑制するメカニズムを次のように説明する。
「これらの遺伝子は細胞増殖のアクセルとブレーキ役を担っています。正常細胞ではそのバランスがとれているが、がん細胞ではアクセルが勝っていることが分子レベルでわかってきました。分子標的薬はアクセルを担っている分子を叩いて、アクセルを抑制してバランスを回復させようとする薬です」
分子標的薬がいかに増えているか。吉野医長は米国のFDAの承認状況を示した。それによると2001年から2006年までに承認されたがん治療薬の67%は分子標的薬で、2015年には75%にまでになると予想されている。 これまで承認された分子標的薬には以下のようなものがある。
表 これまでに承認された主要な分子標的薬(2012年2月20日現在)
文部科学省新学術領域研究「がん研究分野の特性等を踏まえた支援活動」化学療法基盤支援活動のHPから引用
| 一般名/商品名 | 標的分子 | 適応がん種 | 米国承認年 | 日本承認年 |
|---|---|---|---|---|
| Rituximab/Rituxan* | CD20 | B細胞性腫瘍 | 1997年 | 2001年 |
| Trastuzumab/Herceptin* | Her2 ** | 乳がん | 1998年 | 2001年 |
| Alemtuzumab/Campath* | CD52 | 慢性リンパ性白血病 | 2001年 | 治験中 |
| Imatinib/Gleevec | Bcr-Abl/Kit ** | CML, GIST, Ph+ALL | 2001年 | 2001年 |
| Gefitinib/Iressa | EGFR ** | 非小細胞肺がん | 2003年 | 2002年 |
| Bortezomib/Velcade | Proteasome | 多発性骨髄腫, MCL | 2003年 | 2006年 |
| Bevacizumab/Avastin * | VEGF | 大腸がん, 非小細胞肺がん, 乳がん,グリオブラストーマ, 腎細胞がん | 2004年 | 2007年 |
| Cetuximab/Erbitux * | EGFR ** | 大腸がん, 頭頸部がん | 2004年 | 2008年 |
| Erlotinib/Tarceva | EGFR ** | 非小細胞肺がん, 膵がん | 2004年 | 2007年 |
| Azacitidine/Vidaza | DNMT | 骨髄異形成症候群 | 2004年 | 2011年 |
| Sorafenib/Nexavar | Multi-kinases ** | 腎細胞がん, 肝細胞がん | 2005年 | 2008年 |
| Sunitinib/Sutent | Multi-kinases ** | GIST, 腎細胞がん, NET | 2006年 | 2008年 |
| Dasatinib/Sprycel | Bcr-Abl/Src ** | CML, Ph+ALL | 2006年 | 2009年 |
| Panitumumab/Vectibix * | EGFR ** | 大腸がん | 2006年 | 2010年 |
| Vorinostat/Zolinza | HDAC | 皮膚T細胞性リンパ腫 | 2006年 | 2011年 |
| Decitabine/Dacogen | DNMT | 骨髄異形成症候群 | 2006年 | Phase I/II |
| Lapatinib/Tykerb | EGFR/Her2 ** | 乳がん | 2007年 | 2009年 |
| Temsirolimus/Torisel | mTOR ** | 腎細胞がん | 2007年 | 2010年 |
| Nilotinib/Tasigna | Bcr-Abl ** | CML | 2007年 | 2009年 |
| Everolimus/Afinitor | mTOR ** | 腎細胞がん、 上衣下巨細胞性星細胞腫, NET | 2009年 | 2010年 |
| Pazopanib/Votrient | Multi-kinases ** | 腎細胞がん | 2009年 | 申請中 |
| Romidepsin/Istodax | HDAC | 皮膚T細胞性リンパ腫 | 2009年 | 未治験 |
| Denosumab/Ranmark * | RANKL | 多発性骨髄腫による骨病変及び固形がん,骨転移による骨病変 | 2010年 | 2012年 |
| Iplimumab/Yervoy * | CTLA-4 | メラノーマ | 2011年 | Phase I |
| Vandetanib/Caprelsa | Multi-kinases ** | 甲状腺髄様がん | 2011年 | Phase Ⅲ |
| Vemurafenib/Zelboraf | BRAF(V600E) ** | メラノーマ | 2011年 | 未治験 |
| 未治験 | ALK ** | 非小細胞肺がん | 2011年 | 申請中 |
| Ruxolitinib /Jakafi | JAK ** | 骨髄線維症 | 2011年 | 2011年 |
| Axitinib/Inlyta | Multi-kinases ** | 腎細胞がん | 2012年 | 申請中 |
| Vismodegib/Erivedge | Hh signaling | 基底細胞がん | 2012年 | 未治験 |
* 抗体医薬 ** キナーゼ標的 下線:日本発の化合物
分子標的薬の治療成績
肝心の分子標的薬の治療成績はどうなのか。
吉野医長は自らの専門分野である消化器がんのなかで、大腸がんを例に解説した。「切除不能・再発大腸癌の薬物治療の変遷〜新薬導入のインパクト〜」というタイトルのついたグラフを指し示しながら、生存期間の中央値が無治療では約6か月であったが、1995〜2005年にかけて登場したイリノテカン、5FU+ロイコボリン、オキサリプラチンなどの薬剤により数倍に延び、さらに2007年から次々に承認されたベバシズマブ、セツキシマブ、パニツムマブといった分子標的薬により24か月にまでなったことを紹介した。この20年ほどで生存期間中央値は4倍ほど延びたことになる。ちなみに大腸がんの薬物治療では1次〜3次治療のどの段階においても薬剤の選択肢は豊富だが、大腸がん治療ガイドライン2010年度版を見ると、ほとんどのレジメンに分子標的薬が組み合わされている。
分子標的薬治療に高率で随伴する皮膚症状はなぜ起こるか
分子標的薬はターゲットが特異的であるため、発売当初、有害反応(副作用)は大幅に軽減されると期待されたが、この思惑は外れた。2002年に手術不能または再発した非小細胞肺がんに対する治療薬として世界に先駆けてわが国で承認されたゲフィチニブ(製品名イレッサ)では、重篤な副作用である間質性肺炎がそれまでの標準的な抗がん剤よりやや多く発生し、死亡者も続出した。期待値が高かったこともあって一般紙やTVなどでも繰り返し報道されたのは記憶に新しい。
分子標的薬の有害事象で特に頻度が高いのがゲフィチニブと同様にEGFRという癌遺伝子を標的とした抗EGFR抗体薬に伴う皮膚症状だ。EGFRは多くの腫瘍で過剰に発現してがん細胞の増殖に関わっていると見られているが、皮膚や毛包、爪などの正常細胞の増殖・分化にも深く関与している。当然、薬はそこにも作用し、増殖・分化が抑制されて皮膚の炎症が持続的に起こり、バリア機能の弱い保湿力が低下した状態になる。
身体の部位によって現れる皮膚症状は異なる。頭では脱毛症。目では長睫毛症、角膜びらん、潰瘍。顔面などではニキビに似た皮疹(ざ瘡様皮膚炎)。体幹や手足では丘疹、膿疱性の発疹、角質層の水分が減少して皮膚が乾燥し亀裂が生じる乾皮症、強いかゆみを伴うそう痒症。爪では周囲が赤く腫れて激しく痛む爪囲炎というふうになる。これらより頻度は少ないが薬剤(腎細胞がんや肝細胞がんに対するソラフェニブ=商品名ネクサバールなど)によっては、手足の末端部にしびれや知覚過敏、腫れなどが出て、重症化すると水ぶくれや潰瘍になる手足症候群が現れることもある。
誤解されやすいが、これらの皮膚症状の多くはアレルギー機序で発症するわけではなく、それぞれの薬剤の本来の作用の一端として現れる。したがって副作用ではなく、主作用と言うのが正しいともいえる。
「残念ですが分子標的薬はまだ発展途上。現状では正常細胞に思いがけない作用を与えてしまっている。将来的にはがんだけに働く分子を見つけ出して、それだけに作用する分子標的薬を目指さなければなりません」と吉野医長は言う。
他の疾患との鑑別ポイント
以上の皮膚症状は顔面、頭皮、前胸部などの上半身から現れることが多い。また、症状は同時に現れるわけではない。典型的なのは分子標的薬治療開始直後に紅斑や腫脹・感覚異常が起こり、7〜10日にざ瘡様皮膚炎が出現し、2〜3週間でピークとなる。3〜5週間では皮膚乾燥や亀裂、4〜8週間では爪囲炎が主だ。
以下それぞれの皮膚症状の特徴的な病態をあげる。
ざ瘡様皮膚炎は分子標的薬の治療開始から10日以内頃までに出現する。出現頻度は60〜80%。好発部位は顔面、前胸部、後頸部、背部、頭皮で、毛孔に一致した紅色丘疹、膿疱ができ、悪化すると痛みやそう痒を伴う。皮疹の特徴としてはひとつひとつが大きめで鮮明に紅い丘疹ないし膿疱が目立つ。本来は細菌感染のない皮疹だが、かゆみによる掻破により二次的に感染症を生じることもある。
乾皮症は皮膚が乾燥した状態で、そう痒や亀裂による痛みを伴う。出現頻度は約20%。全身に発症しうる。前腕や下腿では鱗屑が炎症性紅斑や色素沈着に伴って見られることもある。体幹では白く粉をふいたようになり、進行するとさざなみ様の浅い亀裂を伴い、サメ肌様になる。指先やかかとでは亀裂を伴うことが多く、疼痛が顕著になる。
爪囲炎は爪周囲に炎症を来し痛みを伴う。爪そのものの発育障害を伴うこともあり、陥凹形成や白色帯状横断線、剥離、脆弱化などの異常が発生すると、爪甲の一部が欠損して周囲の皮膚を傷害し、側爪郭に肉芽を形成、膿瘍ができることも。痛みが強く靴を履いたり、手仕事が困難となることもあり、その場合のQOLは著しく低下する。発現頻度は約20%。
手足症候群は、限局性の斑状の発赤で始まり、加重部や加圧部にタコの目のような硬くて強い角化が生じる。休薬すると症状はすみやかに回復する。
抗EGFR抗体製剤による皮膚障害
皮膚障害グレード2とグレード3の判定時のポイント
出典:「ベクティビックス全国TV/PC講演会(2010年9月):皮膚障害とそのマネジメント 」(この判定時ポイントは国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科医長 山崎直也氏の見解による)
| ざ瘡様皮膚炎 | そう痒 | 皮膚乾燥 | 爪囲炎 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| グレード 2 |
症状 | 痛み、痒みを訴える紅色小丘疹と膿疱が散在 | 激しい、または広範囲のそう痒そう破痕がある | 乾燥が顕著/亀裂が生じる | 発赤、腫脹により痛みを生じる爪の陥入に伴い肉芽形成も認める |
| グレード 3以上 |
症状 | 激しい疼痛/灼熱感/腫脹を伴う紅色小丘疹が集簇、散在 | 激しい、または広範囲なそう痒で日常生活に支障あり(不眠または睡眠障害がある) | 高度の亀裂が生じ、激しい痛みで、日常生活に支障あり | 高度の腫脹、発赤が生じ、これらによる肉芽形成も認める/激しい痛みを伴い歩行、手先の作業等の日常生活に支障を来す |
| キーワード | 顔貌が変化するほどの発赤、腫脹と皮疹の多発熱感 | 出血するほどのそう破 不眠 |
指先や趾尖、踵など手足に多発する深い亀裂 | 衣服のボタンを留められない 靴をはけない 歩行ができない |
皮膚障害対策は症状が出てからの薬物治療に先駆けて予防的投与をすることで数段効果的に
分子標的薬治療に伴う皮膚障害は直接的には生命を脅かすわけではない。だが薬疹と気付かず放置したり、手をこまねいたりしていると重症化する危険性がある。特に皮膚のひび割れや潰瘍を発現すると強烈に痛み、歩行など日常生活に支障をきたし、QOLを著しく低下させる。その程度によっては治療の中止や薬剤の減量を考慮せざるを得ないこともある。その場合、生命予後の観点で患者の不利益を招きかねない。
現時点で皮膚症状は軽度であっても分子標的薬治療では使用回数や期間に制限はないので、効果が持続している間は治療を継続することが多い。したがって薬剤投与中は程度の差こそあれ皮膚症状が完全になくなることはほとんどない。現状では皮膚障害に対して決定的な治療法が確立されているわけではないので、保湿を中心としたスキンケアで症状の予防に努め、良い状態をなるべく維持し、症状が出たらすみやかな対応によって重症化を防ぐことがポイントとなる。
吉野医長は3つのキードラッグをあげる。ひとつはテトラサイクリン系の抗菌剤で内服薬のミノサイクリン。この抗炎症作用を期待して使う。次は保湿剤のヒルドイドローション。そしていざ症状が出たときに使うステロイド外用剤だ。吉野医長は、自らが所属する診療科で分子標的薬による治療が開始されたら、同時に皮膚症状対策薬剤による治療も開始する。いずれ出るであろう皮膚症状に備え、予防的治療を開始するということだ。
根拠となっているのは2010年に発表された国際的なSTEPP試験の結果である。皮膚症状の出る前に治療を開始した予防療法群と、症状が出てから治療を開始した対処療法群で、グレード2(中等度)以上の皮膚障害の初回発現までの期間を比較した。それによると前者は48例中14例の29%で、後者は47例中29例の62%で、グレード2以上の皮膚症状が発現した。予防療法群は中等度以上の皮膚障害の発現頻度を有意に下げることができたことになる。また予防療法群では、グレード3以上(重度)のざ瘡様皮膚炎、そう痒症、膿疱性発疹、爪囲炎などの皮膚障害の軽減効果も報告された。
吉野医長はこれらの結果を踏まえ、「分子標的薬治療に伴う皮膚症状には新しい考えに基づく対処が必要」で、それは『予防』と『治療』を必ずセットとして行うことだ、と強調する。
分子標的薬治療に伴う皮膚障害に対する皮膚科医の取り組み状況
全国の平均的な皮膚科医は分子標的薬治療に伴う皮膚障害の診療経験はどれほどあるのか。またその対処法や課題をどれほど認知しているのか。
前出の川島氏は、皮膚科の勤務医および皮膚科を第一標榜とする開業医、計274名を対象とした診療経験に関する実態調査をした。調査方法は医療従事者向けのポータルサイト「Care Net」の会員に呼びかけて、調査の目的と趣旨に同意した人にアンケート回答してもらうという方法だ。期間は分子標的薬に伴う皮膚障害診療経験の有無を問う1次調査が2011年12月中旬の1週間。回答者は全部で274名、およそ9割が30〜50代で、勤務医が174名、開業医が100名。それによると診療経験は勤務医では88.5%、開業医では61%だった。
分子標的薬の薬疹の診療経験者を対象とし、その認識を問う2次調査の期間は2012年1月中旬の1週間。勤務医の回答者は58名で、男性が約78%、勤務する施設の形態は大学病院が約66%、500床以上の病院が約35%。開業医の回答者は33名で、開業形態は医院(診療所、クリニック)が100%。
設問、当該患者は「紹介受診か自発受診か」の受診区分は、勤務医で約87%、開業医で約32%が「紹介」であった。勤務医では「紹介」が、開業医では「自発」が多い点が注目される。
以下、主だった設問とその回答を勤務医・開業医とを対比する形で所載する。
| 分子標的薬による皮膚症状の治療薬剤 | 参考にする治療アルゴリズムの有無 | がん薬物治療専門科との連携 | |
|---|---|---|---|
| 勤 務 医 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
| 開 業 医 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
| 診療連携を開始すべき時点 | 分子標的薬による薬疹診療に関与すべき医療者 | 分子標的薬による薬疹に関する情報入手経路 | 寄せられたコメントより | |
|---|---|---|---|---|
| 勤務医 |  ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
| 開業医 |  ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
 ※クリックで拡大 |
以上の調査結果を踏まえ、川島氏は次のように総括した。
「第一線の皮膚科医は、限られた情報の中で分子標的薬の皮膚障害に日常的に取り組んでおり、主体的に取り組もうとする意識の高さがうかがえた。今後診療科間、あるいは病診連携などの課題を解決しながら、新しい分子標的薬を用いたがん治療を支えるために、我々皮膚科医の果たすべき役割は大きいと思われる」
診療連携はいつ誰とどのようにするか
冒頭で紹介した「分子標的薬皮膚障害対策マニュアル」では、がんの治療医が皮膚科医へ患者を紹介する要件として次の5点をあげている。
- 薬疹に対する治療が無効な患者
- 爪囲炎が長引き、治りにくくなった患者
- 重症化の恐れのある皮膚障害(紫斑、浮腫性紅斑、多形滲出性紅斑、びらんなど)のある患者
- 外用ステロイド剤を長期に使用する患者
- 上記以外の特殊な皮膚障害のある患者
前出の吉野医長は、重症化が予想される症例については、早めに皮膚科医にコンサルトを行う。爪囲炎などの重症例では皮膚科医あるいは整形外科医と連携して外科的処置も考慮する。薬の説明については、患者全員に対し、「おくすり説明書」を渡す。使う薬はどんな薬か、病状発現時期の目安、それぞれの病期にどのような薬を使うか、使用に際しての注意事項などの項目があり、説明は薬剤師に頼むことが多い。分子標的薬治療に伴う皮膚症状の対処法では、患者自身が行うスキンケアも重要だ。皮膚のケアでは石鹸の選び方、シャワーの使い方、保湿剤の使い方を、爪の手入れではカットの方法、日焼け防止では日焼け予防クリームの選び方や使い方、外出時の服装の注意など、この指導は看護師が担当するのがルーティンとなっている。
「在宅」に移行した患者の支援体制も構築中だ。
すでに日常的に実践しているのが看護師による「電話フォローアップ」。「いかがですか? 困っていることはありませんか?」といった呼びかけをする。化学療法を受けている患者からの「化学療法ホットライン」も設けてある。1日7〜8件の電話相談があり、主に薬剤師が応対している。これは必要に応じて医師にフィードバックし、指示を仰ぐ。
地域医療との連携では、「地域がん医療研修会」を定期的に開催している。たとえば「経口抗がん剤の適正使用」「院内で施行される外来化学療法について」といったテーマであれば、近隣の4市薬剤師会を通じて開催を通知し、参加を呼びかけている。保険薬局に勤務する薬剤師たちの参加が多いという。この研修会を通じては、分子標的薬に伴う皮膚障害、それに対する病院での対処法、保険薬局に分子標的薬治療に伴うと思われる皮膚症状を持った患者が来たらどのように応じて欲しいか、といったことを伝えている。
吉野医長はこれまでの診療経験を踏まえて連携の意義についてこのように言う。
「分子標的薬治療では、適切な副作用マネジメントが治療継続には重要で、薬剤師や看護師の積極的な参加は不可欠です。医師・薬剤師・看護師といった医療スタッフと家族を含めた全員の協力が生存期間の延長のみならず質の高い医療への実現につながります」
診療連携の課題と対策
前出の川島氏は診療連携の課題を、化学療法医、皮膚科勤務医、皮膚科開業医それぞれの立場を考慮しつつ分析した。そしてその課題を乗り越えるための方策について次のように提言する。
1)課題について
- 化学療法医の観点
「分子標的薬によるがん治療は、承認条件として現状では極めて重篤な、場合によっては致死的な状態であり、効果のあげにくい症例が対象であるため、がんの縮小が得られれば致死的ではない皮膚の障害で我慢できるものは我慢してほしいという思いがあり、それが皮膚科医との連携にやや消極的になることにつながっている。また皮膚科医に相談すると簡単に治療中止を提言されることが多いと考え、相談しにくいと感じているのではないか」
- 皮膚科勤務医の観点
「皮膚障害が生じても、治療の目的を考えれば、ある程度までは治療を継続すべきだと頭では考える。しかし皮膚を診療の対象とする皮膚科医にとっては、因果関係の明らかな皮膚障害は改善することが確実であるため、やはり中止すべきとのアドバイスをすることが多いのではないか」
- 皮膚科開業医の観点
「たとえば分子標的薬の皮膚障害に熟知していない医師では、通常のざ瘡、爪囲炎などと誤診しているのではないか。あるいは、薬剤による皮膚障害と診断したら、当然薬剤を中止すべきである、と考えているのではないか」
2)連携の方策について
-
化学療法医の場合
「皮膚科医を含めた対策会議を設けて、分子標的薬による皮膚障害の診断・重症度判定・治療法の標準化、治療中止基準に関するコンセンサス、診断・治療に関する役割分担の明確化、などについて十分な合意を形成する」
-
皮膚科勤務医の場合
「まずは、分子標的薬について、作用メカニズム、期待される効果を十分に理解し、その有用性を高く評価する。治療の目的を再確認し、通常の薬剤性皮膚障害とは異なる取り扱いをせねばならないという意識を皮膚科診療グループ全体で共有する。適切な治療を施し、いかに中止することなく、継続するかという方向で考えるように心がける」
-
皮膚科開業医の場合
「まずは分子標的薬そのものについての知識を持ち、その有用性を十分に理解する。その理解のうえで、いかなる皮膚障害が発生しうるかを学ぶ。薬剤の継続、中止に関して通常とは異なる判断が必要であることを理解する。通常のざ瘡、爪囲炎とは異なる治療法を選択する必要性を理解する」
《記者付記》
病病連携、病診連携をどう構築するか。多くは双方にとって、その端緒となる機会をつかむのが難しいと思われる。ひとつのヒントとしては前出の吉野医長が紹介した、地域の医療機関に向けて呼びかける研修会や勉強会がよい事例であると思われる。