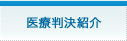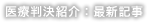高松高等裁判所令和4年6月2日判決 医療判例解説(2023年2月号)102号19頁ウェストロージャパン
(争点)
医師及び看護師が、患者がベッドから転落することを防止し、又は転落により重篤な障害が発生することを防止するために、必要な措置を講じるべき義務があったか否か
*以下、原告を◇1ないし◇2、被告を△と表記する。
(事案)
A(当時26歳の男性・農業の手伝い)は、平成27年(以下、特段の記載のない限り同年のこととする。)9月中旬頃から頭痛や倦怠感などの体調不良が続き、10月29日頃から頭痛、鼻汁や倦怠感が増悪するようになったことから、11月2日午後3時頃、父である◇1に付き添われて、Ⅴ病院を受診した。
Aは、同病院において急性肺炎と診断され、消防防災ヘリコプターで特別地方公共団体である△の運営する病院(以下「△病院」という。)に救急搬送されることになり、同日午後5時44分、◇1とともに△病院に到着した。
Aは、△病院において診察を受けた結果、11月2日即日に、△病院に入院することになり、△との間で診療契約を締結した。
Aは、△病院への入院時、血液循環不全の状態にあったため、同日午後7時及び午後7時30分に、それぞれヴィーンF(血液代用剤。すなわち、血液の血漿を代用する輸液であり、体液のバランスを整え、水分・血圧を維持するために使用される。)500mlを投与された。
Aの主治医であった呼吸器内科のB医師は、11月2日午後7時15分、◇1に対し、Aの身体抑制に関する説明を行い、◇1は、Aの身体抑制に関する説明・同意書の用紙にAの親族・代理人として署名押印し、Aの署名押印部分を代書して、同意書を完成させ、△病院に提出した。
Aは、11月2日午後8時52分頃、△病院において、急性呼吸窮迫症候群と診断され、同日午後9時15分にICU5号室に入室し、ICUにおいて治療を受けることとなった。
△病院は、同月2日午後9時30分頃、Aに対する両上肢の身体抑制を開始し、同日午後9時51分頃、気管内挿管による人工呼吸管理を開始した。
△病院の医師(男性)2名及び看護師(男女各1名)は、11月3日午前0時30分、Aの右手に動脈ラインを挿入するため、ベッドの周囲に集まり、Aに装着していた安全ベルトを外したところ、寝ていたAは、突然起き上がろうとした。Aは興奮しており、看護師から動かないように言われても従うことができず、ベッド上で身体を激しく動かしたことから、上記医師及び看護師(合計4名)はAを押さえつけたが、Aの動きを直ちに制止することはできなかった(本件不穏行動の発生)。
Aは、同日午後6時35分頃、SpO2(経皮的酸素飽和度。健常者の標準値は96~99%である。90%未満は呼吸不全の状態であり、長期に継続すると心臓や脳といった重要な臓器に十分な酸素が供給されず、障害を起こすことがあるとされる。)が80%台から上がらなくなり、収縮期血圧(動脈血圧の波の頂点、いわゆる最高血圧)が65mmHgに低下した。
△病院の看護師は、同病院の救急救命科の医師から指示されて、Aに対し、同日午後6時36分頃から、CVライン(中心動脈ライン)経由で、ヴィーンF500mlをポンピング(注射器を使用した加圧)により投与し、さらに、同日午後6時45分から2本目のヴィーンF500mlをポンピングにより投与し、同日午後7時1分から3本目のヴィーンF500mlを通常の点滴により投与した。
看護師は、同日午後7時20分におけるAをRASS-1(傾眠状態)~―2(軽い鎮静状態)と評価し、Aはナースコールを使用できる状態にはないと考えて、Aの手の届く範囲内にナースコールを置かなかった。また、Aのために、離床センサーが設置されていなかった。そして、看護師は、午後7時21分頃、Aに対し、この状態でいられるかと尋ねると、Aが頷いたため、Aに対し、また見にくることを伝えてICU5号室を退室し、その隣室のICU7号室に移動した。
Aは、同日午後7時29分頃、何らかの方法によりミトンや安全ベルトによる身体抑制を解除し、ICU5号室のベッドからベッド柵(高さ30cm)を超えて病室の床に転落し、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血及びびまん性脳腫脹の障害を負い、意識不明の状態になり、脳死状態になった(以下「本件事故」という。)。
Aは、その後も、△病院での入院を続けた。
△病院は、平成28年2月9日から同月14日までの間、Aに対し、合計約2万1222mlの輸液を投与した。
Aは、平成28年2月14日午後4時23分、死亡した。
そこで、Aの相続人である◇ら(Aの両親)が、△病院の医師ないし看護師がAの転落を防止し、又は、転落により重篤な障害が発生することを防止するための措置を講ずべき義務を懈怠した過失があったために本件事故が発生した旨主張し、また、Aが死亡したのは、本件事故に加え、死亡直前の時期の不適切な輸液投与を行った過失があったためであると主張し、主位的請求として、Aの死亡による損害につき、予備的請求として、Aが脳死状態になったことによる損害(金額は死亡の場合と同額)につき、◇らの固有の慰謝料と併せて、診療契約上の債務不履行又は不法行為(使用者責任)による損害賠償請求をした。
第一審(令和2年6月30日高知地裁判決)は、◇らの主位的請求及び予備的請求をいずれも棄却した。
そこで、◇らは、これを不服として原判決の取消しと自己の請求認容を求めて控訴した。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 遺族合計8249万8968円(主位的請求、予備的請求とも同趣旨)
(内訳:逸失利益4635万2450円+慰謝料2350万円+治療費39万0518円+入院雑費15万6000円+葬儀費用160万円+遺族固有の慰謝料両親合計300万円+弁護士費用750万円)
(裁判所の認容額)
- 一審(高知地裁令和2年6月30日)の認容額:
- 0円
- 控訴審の認容額:
- 遺族合計6605万2794円 (主位的請求を一部認容)
(内訳:治療費16万8579円+入院雑費6万7500円+傷害慰謝料77万円+葬儀費用160万円+死亡逸失利益3244万6715円+死亡慰謝料2200万円+遺族固有の慰謝料両親合計300万円+弁護士費用600万円)
(裁判所の判断)
医師及び看護師が、患者がベッドから転落することを防止し、又は転落により重篤な障害が発生することを防止するために、必要な措置を講じるべき義務があったか否か
前提として、裁判所は、Aについては挿管に伴う苦痛などを原因として不穏を起こし得るところ、本件事故当時、Aは気管内挿管を受けた状態にあったこと、一般的に、浅い鎮静下にある患者が突発的に危険行動を取ることは珍しいことではなく、現に、Aが、鎮静下で不穏行動(危険行動)に及んだこと、Aに対する鎮静は、看護師からの呼びかけに遅滞なく頷ける程度に浅く、この程度の鎮静であれば上記不穏を起こし得るといえるところ、本件不穏行動の際のAの不穏の程度が強かったことに照らすと、Aが不穏を起こせば、徐々に不穏を強めて前後不覚に陥り、ベッド柵(高さ30cm)を乗り越えて、頭部からICU5号室の床面に頭部を打ち付ける事態が生じ得たというべきであると判示しました。
そして、控訴審での鑑定の結果を踏まえ、△病院の医師及び看護師は、Aに生じた上記一連の事態を把握していたから、看護師が午後7時21分にICU5号室を離れた際、Aの鎮静が深まりつつあり、危険な行動に及ぶ予兆がなかったことを踏まえても、その後8分間の間に、気管内挿管をされたAが、これまでのように再び突然に不穏を起こし、不穏を徐々に強めた末、高さ30cmにとどまるベッド柵からAが転落する可能性(本件事故の発生可能性)について、十分に予見することが可能であったと判断しました。
次に、裁判所は、△病院のICUにおいて、ICU全体を見渡せる人員を常時1名確保すべき義務があったか否かについて検討しました。
裁判所は、ICUは、生命の危機にある重症患者を24時間体制で濃密に観察し、先進医療技術を用いて集中的に治療できるようにするために設置され、ICUに入室する患者によっては、抑うつや怒り、せん妄などの症状を呈することもある。その結果、患者が重要な点滴、チューブ、ドレーンなどを自己抜去してしまったり、ベッドから転落してしまうこともあり、重篤患者にとって、こうした事態は生命に危険をもたらすから、これを防止し、患者の安全を確保することが求められているといえると指摘しました。
鑑定の結果も踏まえ、裁判所は、このようなICUの性格からすると、ICUにおいては、通常ICU全体を見渡せる人員を常時1名確保すべきであるところ、とりわけ、△病院のICUはAが入室していた5号室のみが個室になっており、看護師や医師が6号室~10号室にいると、5号室の状況を容易に把握できない構造になっていたのであるから、ICUの各病室の入口に詰めている看護師が病室に入って作業をしている間、この看護師に代わり、ICU全体を見渡せる人員を設置することは、ICUが上記役割を果たし、重篤患者の安全を確保するためには不可欠であったといえ、そのような人員を常時1名確保していれば、△病院の医師及び看護師は、Aの危険行動を速やかに把握することができたといえると判示しました。
そうすると、3日午後7時21分の時点では、Aには何らの危険行動の予兆が見られず、本件身体抑制により、Aが直ちにベッドから転落する可能性はなかったのであるから、この人員配置をしていれば、Aが本件ベッドから転落する前にこの危険行動を把握し、同転落を防止できたといえると判示しました。
裁判所は、したがって、△病院において、ICU全体を見渡せる人員を常時1名確保していなかったことは、同医師及び看護師に結果回避義務違反があると認めるのが相当であると判断しました。
次に、裁判所は、ナースコールを設置する義務があったか否かについて検討しました。
裁判所は、Aが不穏状態に陥った際、手の届く範囲にナースコールが設置されていれば、不穏になったAが、徐々に興奮を強めることでナースコールを押すことができない状態に陥る前(本件ベッドから床面に転落する前)に、ナースコールを利用することが期待できたといえるとしました。
加えて、Aがナースコールのボタンを押せば、△病院の医師ないし看護師がごく短時間のうちにICU5号室を訪室することが可能であるといえるから、Aが不穏を強めるあまりに本件身体抑制を解除し、気管チューブ等を抜去するなどした後に本件ベッドから転落する前に、△病院の医師及び看護師から適切な処置を受けることで、Aが本件ベッドから転落することを回避できたといえると判示しました。
更に、裁判所は、本件ベッドに離床センサーが設置されていれば、Aが本件ベッドから起き上がる動作をするだけで、それを知らせる検知音が直ちに鳴るから、この検知音が鳴れば、△病院の医師及び看護師としては、鎮静が深まりつつあったAが、その流れに反して何らかの理由で起き上がり動作をしたことを直ちに知ることができたといえるとしました。
そして、Aに対する身体抑制は、△病院の医師及び看護師が、重大事象に至る前にAの危険行動を気付けるようにするための時間稼ぎとして作用するのであり、本件ベッドに離床センサーが設置されていれば、Aの起き上がり動作があった時点でその検知音が鳴り、それを聞いた△病院の医師ないし看護師がただちにICU5号室を速やかに訪室することで、Aが本件ベッドから転落する前に適切な処置を受けることができ、Aが本件ベッドから転落することを回避できたというべきであると判示しました。
そして、裁判所は、鑑定の結果によれば、△病院の医師及び看護師において、Aが本件不穏行動に及び、また、11月3日午後2時の挿管チューブを握ろうとする動作をした後、筆談可能になり、意思の表出が可能になった同日午後6時までに、(1)ICU全体を見渡せる人員を常時1名確保する措置を採るか、(2)看護師においてAの手の届く範囲にナースコールを設置するか、(3)△病院の医師及び看護師において、Aのベッドに離床センサーを設置することができたことが認められるから、これらの全部又は少なくとも一部の措置が機能することで、AがベッドからICU5号室の床面に転落するという結果を回避することができたものというべきであると判示して、結果回避義務違反を肯定しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認め、その後、上告(令和5年2月10日最高裁第二小法廷)されましたが、上告不受理決定により、判決は確定しました。