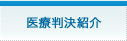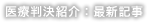東京地方裁判所八王子支部 平成6年11月15日判決 判例タイムズ892号226頁
(争点)
- 新生児が核黄疸であったか否か
- 新生児が核黄疸に罹患したことにつき医師に注意義務違反があったか否か
*以下、原告を◇1ないし◇3、被告を△と表記する。
(事案)
◇2(女性・初産婦)は、昭和62年11月8日、分娩のために△医師の開設する内科・小児科・産婦人科の医院(以下、「△医院」という。)に入院し、同日午後3時30分ころ、予定日より約1か月早い妊娠35週で、体重2630グラム、骨盤位分娩で男児◇1を出生した。
出産自体は順調で、◇2が初めて見た◇1は全身きれいなピンク色をしていた。◇1の血液型はO型でRH+、◇2はA型でRH+で血液型不適合には当たらなかった。
◇1は、出生直後から3日目の同月10日朝までクベースに収容されていた。◇1には、生後3日目から黄疸が出現した。
△医師は、11月11日朝から、◇1に対し光線療法を開始した。
△医師は◇2に対し、◇1の黄疸は生理的黄疸であると説明して光線療法を同月16日まで継続した。また同月10日ころ、◇1は少量のチョコレート様の液体を嘔吐し、△医師はこれをメレナであると診断してビタミンKを内服投与した。
◇1および◇2は、11月24日に退院した。
◇1は、生後6か月後、国立K病院で脳性麻痺の疑いがあると診断され、その後、都立T病院医療センターで脳性麻痺との診断を受け、リハビリのためM療育園に通院し、平成2年2月からS医療療育センターに入園し、脳性麻痺が核黄疸によるものである旨の診断を受けた。
◇1は、平成2年7月に、身体障害者一級の認定を受け、運動機能が全くなく寝たきりの状態で座ることもできず、日常の起居動作について常に家族の介助、付添いが必要であり、重度の言語障害がある。
そこで、◇ら(◇1および◇1の父母)は、◇1の脳性麻痺が、新生児核黄疸によるものであり、△医師が、核黄疸の発症を予見し、早期に治療を実施すべき注意義務を怠ったとして、△の診療契約上の債務不履行に基づく損害賠償請求をした。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- (原告3名合計)2億7283万1301円
(内訳:逸失利益9870万4819円+付添看護費用相当額の損害1億3036万3502円+慰謝料(原告3名合計)4000万円+弁護士費用2400万円の内金)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- (原告3名合計)1億3230万8485円
(内訳:付添費用5689万5908円+逸失利益3341万2577円+慰謝料(原告3名合計)3000万円+弁護士費用1200万円)
(裁判所の判断)
1 新生児が核黄疸であったか否か
この点につき、裁判所は、まず、客観的データはないものの、△医師が◇1に対し、異例に長期と認められる光線療法を施していること、光線療法施行中、通常は光線の作用により黄疸が軽減しているように見えることが多いにもかかわらず、◇2の観察によると◇1の黄疸は増強していると感じられたこと、△医師自身も、11月13日の時点において◇1の黄疸が大腿部まで広がっていた、すなわち通常の成熟児の場合において血清ビリルビン値が16mg/dl程度までなりうる状態になっていたことを認めていることからすると、黄疸の程度は重かったものと認定しました。
そして、◇1は、検査の結果、聴性脳幹誘発反応が極度に低下し、聴神経が侵されていることが認められるが、これは核黄疸による脳の傷害の場合にしばしば生じるものであり、逆に核黄疸では大脳皮質が影響を受けないことが多いところ、◇1について脳波検査等で大脳皮質の異常が認められない点でも症状は核黄疸に合致していると指摘しました。
また、S医療療育センターに入園した当初は眼球の異常及び歯のエナメル質の異常といった核黄疸に特有な所見が認められたと判示しました。また、核黄疸には、いわゆるプラハによる臨床症状の分類がなされており、◇1には、プラハの第一期症状の嗜眠傾向があったものと認められると判示し、以上を総合すれば、◇1は核黄疸であったものと認めるのが相当であると判断しました。
2 新生児が核黄疸に罹患したことにつき医師に注意義務違反があったか否か
この点につき、裁判所は、△医師も新生児医療に携わる医師として、一般的に新生児の黄疸を注意して観察し、黄疸が強いと認められる場合には、△の診療所にはビリルビン測定装置がないのであるから、他の医療機関に委託してビリルビン値を測り、その結果ビリルビン値が一定の限度を超えている場合には、△の診療所には交換輸血を自ら行いうる設備はないので、交換輸血を行える他の医療機関に患者を転送して、核黄疸を防止すべき注意義務があると判示しました。
そして、△医師が光線療法を開始した後である11月13日において、光線療法により皮膚の色は見にくくなっているにもかかわらず、◇1の黄疸が大腿部まで広がっていた。したがって、血清ビリルビン値は、通常大腿部まで黄疸が広がっている場合の目安である16mg/dlよりもさらに上昇している可能性があったと認められ、しかも、◇1にはプラハの第一期症状が出ていたのであり、血清ビリルビン値がかなり上昇している蓋然性が高かったのであるから、この段階で、△医師としては血清ビリルビン値の計測を他の医療機関に委託し、その結果いかんによっては交換輸血等の措置をするために◇1を他の医療機関に転送すべき注意義務があったにもかかわらず、ビリルビン値を計測せずに11月16日まで光線療法を継続したのであるから、△医師には上記注意義務に違反した過失があると認められるとしました。
更に、裁判所は、◇1が重度のアテトーゼ型脳性麻痺であり、進行性のものではなく、脳の各種断層撮影では異常が認められないこと、分娩経過は良好で、重度の仮死は認められず、また、仮死分娩を理由として脳性麻痺となった場合にみられるような症状が◇1には存在しないことなどから、◇1の脳性麻痺の原因は、核黄疸によるものと認定しました。そして、プラハの第一期症状が出ている段階において速やかに交換輸血を行えば、脳性麻痺の後遺症はほとんど免れることが臨床上認められているのであるから、△医師の過失と◇1の脳性麻痺との間には相当因果関係があると判断しました。
裁判所は、したがって、△医師は、債務不履行に基づき、◇らに生じた損害を賠償する責任を負うとしました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認め、その後判決は確定しました。