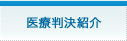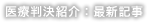前橋地方裁判所平成元年12月19日判決 判例時報1357号115頁
(争点)
医師に新生児低血糖症及び脱水症状に対して適切な処置を施す義務違反があったか否か
*以下、原告を◇1ないし◇3、被告を△と表記する。
(事案)
◇2は、昭和58年7月13日、産婦人科医である△医師の経営する医院(以下、「△医院」という。)において、△医師の診察を受け、妊娠反応が擬陽性であったので妊娠の疑いあり、分娩予定日を昭和59年3月12日との診断を受けた。また、◇2は、膣炎の診断も受け、これに対する治療を受けた。
◇2は、同月14日、△医院を訪れて、△医師の診断を受けたところ、超音波診断により妊娠が判明した。△医師は、◇2のこしけ(膣からの分泌液)に血液が混じっていたことから、流産の危険性があると判断し、切迫流産の治療を行った。
◇2は、出産のために、翌7月15日以降も△医院への通院を継続した。◇2には、依然としてこしけに混じって出血がみられたので、△医師は、同年8月29日ころまで切迫流産の治療を継続したところ、同年8月末ころには、出血が少量になったものの、同年12月ころまで出血は続いた。
◇2および◇2の夫である◇3は、◇2が△医院に通院し、△医師の診療を受けるようになったころ、それぞれ△との間において、生まれてくる子供にもし病的異常があれば、これを的確に診断したうえ、その症状に応じた適切な診療行為を行うことを内容とする診療契約を締結した。
◇2は、昭和59年3月17日、△医院に入院した。入院後、△医師が、分娩監視装置で◇2の胎児心音を測定したところ、胎児心音に極端な乱れが見られた。そこで、△医師は、胎児が仮死状態である可能性があると判断し、吸引分娩を行うこととした。◇2は、同日午後6時ころ自然に陣痛が開始し、同日午後9時37分、吸引分娩により◇1を出産した。
◇1の出生時の体重は2830グラムであった。
◇1は、分娩直後の状態としては、外見的には異常が見られなかった。
△医院においては、新生児は、生後6時間から24時間までは、哺乳をせずに保育器の中で保育して全身状態を観察することにしており、◇1に対しても同様の処置が取られた。
同月18日午前3時ころ、◇1に対し、出生後初めて、滋養糖(ブドウ糖粉末)を白湯で溶いたもの(以下「G水」という。)が少量与えられたが、◇1はこれを嘔吐した。
同日午前9時ころより、◇1に対し、ミルクが与えられ始め、以後3時間ごとにミルクが与えられたが、◇1の哺乳力は、平均的な乳児と比較して、やや弱いようであった。
◇1は、同月19日午前9時ころ、母である◇2の病室に移され、母子同室となったが、その後同日午前10時ころから12時ころにかけて、2度にわたり嘔吐した。
△医師は、◇1に二度の嘔吐があったこと、及び◇1の哺乳力が弱く一般状態としてもやや元気がないようであったことを考慮して、担当看護師に対し、◇1をナースセンターで預かって様子を見るように指示し、同日午後3時ころ、◇1は、ナースセンターに移された。この頃、◇1の体重は2560グラムであり、同日早朝より、120グラム減少していた。
◇1は、同日午後6時35分ころ、ミルクを10cc飲んだが、嘔吐もなかった。◇1は、同日午後9時30分ころにも、ミルクを20cc飲み、哺乳力もやや持ち直した状態だった。
◇1は、翌20日午前3時30分ころ、嘔吐がみられたが、その後同日午前6時30分ころに、ミルクを与えたときには哺乳力も良好であり、嘔吐もなかった。同日午前7時ころの◇1の体重は2540グラムであった。△医師は、同日午前8時30分ころ、担当看護師に対し、母子同室にするように指示を出した。◇1は、同日早朝から、保育器の中で、3時間程光線療法を受けた後、◇2の病室に移された。
△医師が、同日午後4時ころ、◇2の病室にいって、◇2に◇1の様子を尋ねたところ、眠っていて泣かないし、ミルクも飲まないということであったので、同日午後4時30分ころ、再び◇1をナースセンターに移して様子を見ることにした。
◇1には、同日午後10時30分ころ、三度にわたりかなりの量の嘔吐があり、この当時の◇1の皮膚の色は黄色くなっていたので、△医師は、◇1に対し、黄疸の検査として血清ビリルビン値の測定を行ったところ、その値は19.0mg/dlであった。
◇1は、翌21日午前1時ころにも、三度にわたり多量の嘔吐をした。この当時の◇1の状態は、皮膚がカサカサで割れており、強い脱水症状がみられるとともに、腹部がへこんでいて、全身の運動も活発でなく、黄疸症状も見られた。そこで、△医師は、◇1に対し、血糖値の測定検査を行ったところ、血糖値は12.5mg/dlであった。また、血清ビリルビン値の測定をしたところ、その値は、14.6mg/dlであった。
△医師は、この検査結果および◇1の症状から、◇1は、強度の脱水症状により、全身状態が悪化しているものと判断し、同日午前2時ころから、◇1に対し、5%グルコース液の輸液を開始した。
同日午前2時ころから、同日午前7時ころまでの間に、◇1に対し、5%グルコース液200mlが投与された。また、同日午前2時ころから、同日午前7時ころまでの間に、◇1に対し、鼻腔カテーテルによりG水10mlが投与された。◇1は、同日午前7時ころ、約24ccの尿を排泄した。
同日午前7時ころから、同日午後1時ころまでの間に、◇1に対し、5%グルコース液50mlが投与され、また、鼻腔カテーテルによりG水5mlが投与された。◇1の午前7時ころの体重は、2530グラムであり、午前9時30分ころの、血清ビリルビン値は、13.8mg/dlであり、血糖値は12.5mg/dlであった。◇1は、同日午前10時ころ、約30ccの尿を排泄した。
同日午後1時ころから、同日午後3時30分ころまでの間に、◇1に対し、5%グルコース液70mlが投与され、また、鼻腔カテーテルによりG水8mlが投与された。◇1は、同日午後1時ころ、約55ccの尿を排泄した。
同日午後3時ころ、◇1には軽い痙攣発作があり、◇1の血糖値は、12.5mg/dlであり、このころ◇1に対し、鼻腔カテーテルによりG水10mlが投与された。また、◇1は、このころ、約48ccの尿を排泄した。
同日午後3時30分ころ、◇1に対し、鼻腔カテーテルにより母乳10mlが投与された。
同日午後4時15分ころ、◇1の血糖値は35.0mg/dl、血清ビリルビン値は、13.8mg/dlであった。
同日午後5時ころ、◇1には、依然として痙攣発作の症状があったため、△医師は◇1の症状が重篤であると判断して、O病院の小児科に連絡を入れ、◇1の受け入れを要請した。
O病院小児科は、△医師のこの要請を受け入れたので、△医師は、同日午後5時30分ころ、◇1をO病院に転院させ、◇1は、同日午後6時ころ、O病院に入院した。
◇1は、O病院に転院したが、転院時の◇1の症状は、四肢は冷たく、体重測定時に、下肢のペダル漕ぎ様な動きに始まり上肢に及ぶ、四肢から全身にかけての間代性痙攣が出現するなど、痙攣重積状態にあり、CTスキャン検査で強度の脳浮腫が認められたので、O病院では、入院直後からNICU(新生児集中管理室)において、◇1に対する治療を行った。なお、◇1の入院時の血糖値は、130mg/dlであり、体重は2810グラムであった。
O病院小児科のT医師は、△医師からのO病院に対する新生児依頼書の記載並びに、△医師から電話で事情聴取した結果を勘案しつつ治療に当たったが、最終的に、病名を低ナトリウム血症、低血糖症、痙攣重積症、SIADH、敗血症の疑い、新生児高ビリルビン血症とし、◇1は生後何らかの原因による嘔吐、哺乳力不足(カロリー摂取不足)から、低血糖症と新生児高ビリルビン血症(新生児重症黄疸)となったところに、不適当な水分輸液がなされたため、高ナトリウム血症から低ナトリウム血症への急速な変化および過剰輸液による循環血液量の増加が生じ、これらに伴って、痙攣、脳浮腫が出現し、痙攣重積に至ったものであろうと判断した。
O病院では、◇1に対して、人工換気、薬剤投与、水分補給の抑制、光線療法などの治療が行われ、◇1の症状は、回復に向かい、同年3月29日には、人工換気は中止され、同年4月6日ころより哺乳開始となり、◇1は、同月23日、O病院を退院したが、退院時のT医師の説明によれば、◇1は死亡は免れたものの、脳浮腫によって脳が死んでしまっている可能性が高いとのことであった。
◇1は、退院後、3か月ないし5か月程して、痙攣が出現し、それ以降抗痙攣剤を服用し、生後1歳を過ぎても、首が座らず、寝たきりで寝返りさえ打てず、また、人の呼び掛けにも反応を示さない状態であったため、生後1年半ほど経過した、昭和60年秋ころ、四肢体幹機能障害により、身体障害者等級表により障害二級の認定を受け、更に昭和61年には障害一級の認定を受けた。◇1は、生後5歳を過ぎても、食事も排泄も行えず、その他の日常の動作も全くできず、人の呼び掛けにも反応を示さず、言語能力も全くない状態であった。
そこで、◇ら(◇1およびその父母)は、△医師に対し、△医師は、◇1に生後まもなく生じた新生児低血糖症並びに脱水症状に対して、適切な治療を行わず、かえって不適切な処置を施して、◇1の疾病を悪化させ、このため◇1に脳浮腫を生じさせ、その結果◇1に上記後遺症を生じさせたと主張して、債務不履行に基づく損害賠償請求をした。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 1億6215万円
(内訳:逸失利益3394万円+付添看護費7351万円+慰謝料(◇ら3名合計)4000万円+弁護士費用1470万円)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- 8483万0464円
(内訳:逸失利益3282万0032円+介護費2841万0432円+慰謝料(◇ら3名合計)1600万円+弁護士費用760万円)
(裁判所の判断)
医師に新生児低血糖症及び脱水症状に対して適切な処置を施す義務違反があったか否か
この点について、裁判所は、◇1の昭和59年3月21日午前1時ころの様子は、皮膚がカサカサで割れており皮膚乾燥著明であり、腹部がへこんで、全身の運動も活発ではなかったというのであり、また、◇1の血糖値は、12.5mg/dlであったのであるから、おそくともそのころには、◇1は、脱水症を伴う重度の低血糖症になっていたものであり、放置すれば重大な結果を生じかねず、早急に症状改善のための治療にとりかかる必要のあるものであったと認められるとしました。
裁判所は、また、新生児低血糖症及び脱水症の疑いが生じた場合、医師としては、直ちに、必要な検査を行うと同時に、低血糖及び脱水の症状を改善すべく、適切な輸液を開始すべき義務があるというべきであり、本件における昭和59年3月21日当時の△医師にも、同様の義務があったものであるところ、△医師が、同日、◇1の低血糖症及び脱水症に対して施した治療は、同日午前2時ころから、電解質を含まずグルコースだけを溶かした5%グルコース液の点滴投与を開始し、午前7時ころまでの間に200mlを、同日午前7時ころから午後1時ころまでの間に50mlを、同日午後1時ころから午後3時ころまでの間に70mlを、それぞれ投与した、というものであったと指摘しました。
その上で、5%という低濃度のグルコース液の投与並びに電解質を含まないグルコースのみの水溶液の投与は、新生児の低血糖症及び脱水症に対する輸液療法実施上の一般的原則に適合しないものである上、輸液量についても、輸液当初の◇1の体重が明確でないため、確定はできないものの、一日新生児体重1kg当たりの平均的輸液量とされている150ないし160mlに対して、少なくとも200mlを超える過剰の投与であったことが認められるとしました。そして、同日午後3時ころ、◇1には、痙攣発作が出現したが、このころの◇1の血糖値は12.5mg/dlであって、低血糖の状態は、全く改善されていなかったことが認められるとしました。
裁判所は、◇1は、脱水症及び極度の低血糖症状態にあったところに、△医師の電解質を含まない5%グルコース液の過剰輸液により、細胞外液及び細胞内液の水分代謝のバランスが崩れたことがあいまって、痙攣並びに脳浮腫を生じ、その結果痙攣重積状態に陥り、脳組織に不可逆的な損傷を生じさせ、脳性麻痺を残したものと推認しました。
裁判所は、△医師は、◇1の脱水症及び低血糖症に対して、医学上一般的でない不適切な処置を施していたものであることが認められるところ、診療契約によれば、△医師は、おそくとも◇1に脱水症及び低血糖症が生じていることが明らかとなった昭和59年3月21日午前1時以降、◇らに対し、◇1の上記症状に対して、早急に適切な治療を施し、上記症状を改善すべき、契約上の義務を負っていたというべきであるから、上記診療契約上の債務不履行があったと判断しました。
以上から、裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認め、その後判決は確定しました。