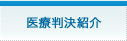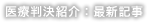名古屋高等裁判所平成2年7月25日判決 判例時報1376号69頁
(争点)
医師に細菌検査義務違反があったか否か
*以下、原告を◇、被告を△1および△2または合わせて△と表記する。
(事案)
昭和49年10月30日、Aは交通事故に遭遇し(加害車両運行供用者は株式会社である◇)、△1医師の経営する病院(以下、「△病院」という)に運ばれ、当直医の診察を受けたところ、非開放性の右大腿骨粉砕骨折(以下、「本件骨折」という。)があったが、骨折の付近に創傷はなく、他に左橈骨骨折、右下腿挫傷、右大腿挫創、顔面切創があり、体温は37度2分であった。そこで、同医師は、本件骨折の治療のためにキルシュナー鋼線牽引を施して骨の整復に努めるとともに抗生物質を投与して患部の化膿防止に努めた。
Aは同日から昭和50年1月20日まで△病院に入院した。
△病院の△2医師は、翌31日以降Aの治療を担当して、本件骨折につき上記治療方法を継続した。Aの体温は平熱が続き、白血球数も同年11月7日において9200でさほど異常でなかったものの、牽引によっても所期の効果が生じないので、△2医師は、同月8日内副子固定法による手術を施した。その後の経過が良好であったので、同月13日ギプスを装着した。同月18日、抜糸のためにギプスを開窓したところ、血種があったので、これを取り除き、更に、分泌物を体外に誘導するためのガーゼ(込ガーゼ)を一か所に挿入した。なお、ギプスを装着した後の体温の最高値は、同月14日が38度、15日が37度8分、16日が37度9分、17日が38度7分であり、また、白血球数は同月16日に1万4400となった。
△2医師は、同月22日、Aが強い疼痛を訴えたので2回鎮痛剤を注射し、3か所に込ガーゼをし(これは同月27日まで続いた。)、翌23日にもAが疼痛を訴えたので鎮痛剤を注射した。なお、Aの体温の最高値は同月21日及び翌22日が37度7分、同月23日が38度6分であった。
△2医師は、Aの傷が治らないので、壊死骨化した骨片を取り除けば傷が治ると考え、同月27日、Aの大腿部を2か所切開して壊死骨を探したが発見できず、込ガーゼ(5本)をしてガーゼ交換に7枚使用し、翌28日には、分泌物がなくならないので、込ガーゼに代えてビニールドレーンを傷口に挿入し、この日に3回の処置をしてガーゼ12枚を使用した(同年12月2日まで同様)。なお、Aの同月28日の体温は平熱であったが、白血球数は9700であった。
△2医師は、Aがギプスを嫌いこれを外すことを要求するので、同月30日、ギプスを外して副木をした。
同年12月3日からは処置回数が2回、ガーゼの使用枚数が8枚に減少し、同月12日の白血球数は1万500であった。△2医師は、同月17日には膿が減少したので、ドレーンに代えて込ガーゼ(2本)をし、同日及び翌18日には2回の処置でガーゼ4枚を使用した。しかし、同月19日以降、処置回数は1回、ガーゼの使用枚数は2枚に減少した。
△2医師は、23日にはAが吐き気を訴えたので、それまで投与していた抗生物質の投与を中止した。同月25日からは分泌物が多くなったので、処置回数が2回に、ガーゼの使用枚数が4枚に増えたが、同月28日からは処置回数が1回に、ガーゼの使用枚数が2枚に、更に、昭和50年1月1日及び翌2日には込ガーゼの本数が1本にそれぞれ減少した。
しかし、同月3日からは込ガーゼの本数が2本に、ガーゼの使用枚数が3枚に増え、同月8日にはガーゼの使用枚数が一旦1枚になったが、同月9日からは処置回数が2回に、ガーゼの使用枚数が2枚になった。なお、同月8日の白血球数は1万3600となった。
その後、△2医師は、手術の必要を認め、その旨をAの母親に話したところ、Aらは、手術を嫌い、同月17日に県立T病院への転院を希望し、同月21日同病院に転院した。
T病院では、昭和50年1月21日にレントゲン検査をした結果、骨折部の固定状況は良好であったが、患部には瘻孔(深部組織あるいは臓器と外部の間に生じた病的な管状の連絡)があり、排膿もあったため、次の治療方針を定めた。(1)まず膿の流出を止める。(2)そのためには暫く化学療法として8時間おきに抗生物質を与える。(3)次いで瘻孔造影を行う。(4)その後に病巣を掻把し局所に管を入れて抗生物質を持続的に流して洗い清める局所持続灌流を行う。
同月24日に細菌の検査をした結果、緑膿菌が存在することが判明した。同月27日には患部から多量の膿が流出しており、同月29日には瘻孔が3か所できていて、そこから多量の膿が流出していた。そして、同年2月11日の検査では、黄色ブドウ状球菌が多量に認められた。
同年4月22日、ギプスを切って瘻孔造影を行ったところ、透視の際に著しく異常な像が認められ、翌23日のレントゲン検査の結果では、骨折部位の近くの骨片に腐骨と思われるものが認められた。T病院では、同日、内副子固定を除去する手術をし、骨周囲の軟部組織が著しく変性汚濁していたのでそれらを除去するとともに腐骨をも除去し、髄腔内を掻爬するなどした後、骨折部に骨髄内に釘を挿入して骨を固定するキュンチャー釘固定術を施した。
同年7月21日、軟部組織は根肉芽で覆われ、骨癒合を望めないと思われる骨片が存在し、その部分には壊死組織が認められ、内部にも膿の貯溜が認められた。そこで、T病院では、この骨片を除去し、局所持続灌流手術を施した。その後、大きな骨片が壊死して腐骨になったので、同年11月19日にキュンチャー釘を取り除くとともに、病巣掻爬及び創外固定術を施したが、瘻孔からの膿の排出は続いていた。
T病院は、昭和51年5月17日病巣掻爬手術をし、同年9月6日には腐骨の形成によって骨欠損を生じた部分に骨移植術を行った。ところが、同年11月20日、AがT病院内で車椅子を使用していた際に転倒して炎症が再発したため、炎症の治療をしたうえで骨移植のやり直しをする必要が生じた。Aは治療を継続して再度骨移植をしても、所期の結果を生ずるか否か不明であること、及び経済的負担に耐えられないこと等の理由から、関係者と協議のうえ右大腿部の切断を決意し、昭和52年7月25日その手術を受け、昭和53年8月14日にT病院を退院し、同日をもって症状固定と診断された。この時点でAは27歳であった。その後、Aは、義足訓練等のため通院していたが、切断部に瘻孔ができたので、昭和54年3月3日に同病院に入院して瘻孔郭清手術を受け、同月17日に退院し、以後も義足を作製する必要上、少なくとも昭和55年1月16日まで同病院に通院したうえ、義足を装着した。
加害車両運行供用者である◇は、Aの大腿切断は△2医師の過失(抗生物質の投与の不適切、手術の時期の選択の不適切、手術時の滅菌不完全、手術方法の選択の不適切等)によるものであり、◇および△らは共同不法行為者に当たるとして、共同不法行為者相互間の求償権に基づき、求償金等を請求した。保険会社が◇に補助参加した。また、◇及び◇の車を運転していた運転手は、△2医師の不法行為により、Aから訴訟を提起され長期間にわたり物的、精神的に多大の損害を被ったとして慰謝料も請求した。
第一審(岐阜地裁多治見支部昭和63年12月23日判決)は、△2医師の過失を認め、◇及び△の負担部分は同等であるとして、◇の請求を一部認容し、◇及び運転手らの慰謝料請求は棄却した。
そこで、これを不満とした△らが控訴(◇は付帯控訴)した。
求償金等請求
(一審での請求額)
- ◇及び◇の車を運転していた運転手合計の請求額:
- 4940万1939円
内訳:Aの損害8038万7068円のうち、◇がAに支払った3940万1939円+◇及び◇の車を運転していた運転手の慰謝料(Aから訴訟を提起されたことによる)合計1000万円
(控訴審での請求額)
- ◇の請求額:
- 2769万3622円
内訳:一審裁判所が認定したAの損害額3504万6562円から◇の負担部分735万2940円を控除した金額
(裁判所の認容額)
- 一審裁判所の認容額:
- 1752万3281円
内訳:Aの損害額3504万6562円(T病院での転倒がAの右大腿部切断手術をもたらす要因になったことから、Aの義足代、後遺障害逸失利益、後遺障害分の慰謝料についてはそれぞれ70%程度の過失相殺を行う)の50%(◇車両の運転手と△2医師の寄与度に鑑み、当事者双方の各負担部分はそれぞれ50%と判断) - 控訴審裁判所の認容額:
- 2075万4953円
内訳:Aの損害額3715万6323円(*)のうち、◇の負担部 分1640万1370円(**)を控除した金額
- *Aの損害額の内訳
- 治療費849万1876円+付添看護料・入院中の食事代及び布団代291万4500円+入院諸雑費及び入院中の文書代60万3885円+通院交通費1万7560円+義足代28万2100円+休業損害848万7452円+逸失利益2629万1328円+入通院分慰謝料400万円+後遺障害分慰謝料600万円―過失相殺(Aの義足代、後遺障害逸失利益、後遺障害分の慰謝料についてそれぞれ50%程度の過失相殺)
- **◇の負担部分の内訳
- △病院における治療については、△2医師の過失のために治療期間が長引いたり、特別の治療を要したとは認められないため、△病院における治療費、付添看護料・入院中の食事代及び布団代、入院雑費、文書代、休業損害のうち△病院入院期間中の分、慰謝料のうち△病院入院期間中の分の合計256万4735円全部が◇の負担部分と判断。
その他の損害合計3459万1588円については、4割に当たる1383万6635円を◇が、6割に当たる2075万4953円を△らが負担
256万4735円+1383万6635円
=1640万1370円
(控訴審裁判所の判断)
医師に細菌検査義務違反があったか否か
この点について、裁判所は、治療経過及び証拠によれば、△2医師は、昭和49年11月22日頃には、骨髄炎の発症を疑って細菌検査をすべき注意義務があり、同△2医師においてこれをしていれば、Aが骨髄炎に罹患していること及び起炎菌の種類が明らかとなり、当該起炎菌に最も有効な抗生物質を投与することにより骨髄炎に対する適切な治療ができたのに、この検査を怠り、同年12月23日には安易に抗生物質の投与を打切ったため、骨髄炎の再活発化を招き、ついには右大腿部を切断するのをやむなきに至らせる一因を与えたものと認められるとしました。裁判所は、したがって、△2医師には過失があるというべきであるとしました。
以上から、裁判所は、上記(控訴審裁判所の認容額)の範囲で◇の請求を認め、その後判決は確定しました。