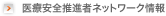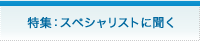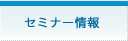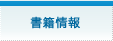静岡地方裁判所沼津支部平成5年12月1日判決 判例時報1510号 144頁
(争点)
診察行為における医師の注意義務違反(過失)の有無
※以下、原告3名のうち患者の妻を◇、被告を△と表記する。
(事案)
A(当時44歳の男性・工場長)は、昭和61年5月8日午後5時半頃、3日前から37度程度の発熱があり、これが改善されなかったため、△医師の経営する整形外科内科医院(以下、「△医院」という。)を訪れ△医師の診察を受けた。なお、△医院は内科及び整形外科を診療科目として標榜し、救急病院の指定を受けていた。
Aは△医師の問診に答え、「3日前から37度の熱が出て下がらない。喉が痛く、疲れやすい。」と訴えた。診察の結果、熱は37度であり、扁桃腺が赤く腫れていたが、ラッセル音等の異常音はなかった。そこで、△医師は、Aの症状を急性気管支炎・腺窩性扁桃膜炎と診断し、扁桃腺にルゴールを塗布するなどし、ニフラン(解熱鎮痛剤)等の内服薬3日分を与えて帰宅させた。
しかし、Aの症状は帰宅後も改善しなかった。Aは、△医師から交付を受けた薬も喉がつかえて飲み込むことができず、その後痰も出せないと訴えるようになり、同日午後7時30分ころには、息が苦しく横臥していることができないと訴え始めた。そこで、Aの妻◇が△医院に電話で「Aが息ができない状態である。」旨を伝えたところ、△医院の看護師が、△医師の指示を仰いだうえ、すぐ来院するよう返答した。
Aは、◇が運転する軽自動車に乗車し、同日午後7時55分ころ、△医院を再度訪れ、△医師の診療を受けた。診察室には◇が付き添ってきたが、Aは◇の介助なしに自力で歩いてきた。しかしAは、△医師の問診には「息苦しい。」と答えるのがやっとのような状態であり、◇が「咳が出て、痰がからんでいる。」などと説明した。また、△医師が喘息やアレルギーの有無を尋ねるとAは「ない。」と答えた。背中の聴診の結果、弱い乾性ラッセル音が聴取され、気管ないし気管支に痰が溜まっていることが推測された。診察中、Aは横臥するより座っている方が呼吸が楽である(起座呼吸)として、座っていた。Aは肩で呼吸しており呼吸音は荒かった。なお、Aは、時として首を横に振って激しく息を吸い込む動作をしていたが、△医師はこれを確認していなかった。そこで、△医師は、Aに呼吸障害があると判断し、ネブライザーを使用して、粘液溶解剤のアスプール2mlとアレベール1mlを吸入させるように看護師に指示するとともに、病状の進行がかなり急激であり、初期の診断と異なり、肺水腫や咽後膿瘍ないし喉頭浮腫などの重篤な疾患を疑い、△医院より人的物的設備の整ったT市救急医療センター(以下、「救急センター」という。)への転院を考え、救急センターへ電話を架けて転院の応諾をとった。その際、△医師は、看護師に上記吸入の効果を尋ねたところ、Aの症状の改善は得られないとの返答だった。
△医師は、Aらに転院することを告げ、その方法として救急車の利用は時間がかかるおそれがあると考え、Aを◇の運転する軽自動車に乗車させて救急センターに向かわせ、自己は自動車で先導もしくは追尾することとした。救急センターは△医院から約4キロメートルのところにあり、同センターまでは自動車で道路事情により早ければ7ないし8分、遅くて10分から15分かかるのが通常であった。
Aは救急センターへ向かうため△医院の診察室から玄関まで歩いたが、その際の歩行は◇に片腕を支えられたうえでのものであった。その時点ではAには自発呼吸があった。
◇は、Aを自己の運転する軽自動車の助手席に同乗させて△医院を出発した後、約10分程度で救急センターに到着したが、その途中のAの様子についてはこれを十分確認するだけの精神的余裕がなく、同センターの玄関前に自動車を止める寸前に初めて、Aの異変に気付き、△医師にAの異常を知らせた。△医師が駆けつけた時、Aは口から泡を出していた。Aはその後直ちに救急センターの集中治療室に運ばれたが、意識及び自発呼吸はなく、瞳孔が散大し、心停止の状態であり、四肢は冷たく湿潤し、チアノーゼが認められる状態であった。そこで、直ちに心マッサージ、気管内挿管及び血管確保などの救急蘇生術が施されたが、同日午後9時50分Aの死亡が確認された。死因は、急性喉頭浮腫を原因とする急性呼吸不全であった。
そこで、◇ら(Aの妻および子ら)は、△医師に対し、△医師の診療行為に過誤がありその結果Aが死亡したとして、診療契約上の債務不履行もしくは不法行為に基づき、Aおよび◇らの固有の損害の賠償を求めた。
(損害賠償請求)
- 請求額:
- 1億2108万9424円
(内訳:逸失利益6108万9425円+Aの慰謝料3000万円+妻子固有の慰謝料3名合計2000万円+葬儀費用100万円+弁護士費用900万円)
(裁判所の認容額)
- 認容額:
- 7282万1857円
(内訳:逸失利益4400万5613円+Aの慰謝料1400万円+妻子固有の慰謝料3名合計800万円+葬儀費用81万6245円+弁護士費用600万円。相続人が複数のため端数不一致)
(裁判所の判断)
診察行為における医師の注意義務違反(過失)の有無
この点について、裁判所は、△医師には、Aが2回目に△医院を受診した際、Aのような呼吸困難を訴える患者を診察するに際し当然に要求される、呼吸、脈拍、血圧、意識状態やチアノーゼの有無等のバイタルサインの把握をなさず、したがってまた、これらのバイタルサインの把握を通じ患者の重症度判断や緊急度の判定をなすべきであったのにこれを怠った注意義務違反が存したといわざるを得ないと指摘しました。
そして、Aの呼吸障害は喉頭浮腫に起因するものであり、Aは、△医院を出て◇の運転する軽自動車で救急センターに向かう途中、急激に呼吸困難を進行させ、Aが救急センターに到着したときは、既に回復不能な窒息状態(一般的な窒息の経過の第五期後半)にあったところ、この時点以前に気道が確保されていれば、同人を救命し得た高度の可能性があったことは一般的な窒息の経過等の認定事実から明らかであると判示しました。
Aの呼吸障害は喉頭浮腫に起因するものであったところ、Aが喉の痛みや嚥下困難を訴えていたことに加え、Aに呼吸困難の症状が見られたことからすれば、Aの呼吸障害の原因が喉頭上気道にあることが先ず疑われるべきであり、現に△医師も喉頭浮腫をAの呼吸障害の原因疾患の一つとして疑っていたと指摘しました。また、△医師は、喉頭に聴診器をあてて呼吸音を聞くことにより呼吸障害の原因が喉頭上気道部にあることを知ることが可能であった(以上によれば、△医師はAの呼吸障害の原因が喉頭浮腫にあることを認識し得たといえる)と判示しました。
そして、Aの呼吸困難は起座呼吸を必要とする状態であり、呼吸障害の程度としては重症であることが認められ、のみならず、△医師の問診に対するAの応答は話すのが苦しそうな状態であり、また、Aの呼吸は荒く、肩で呼吸をしていた状態であり、時として首を横に振って激しく息を吸い込む動作を見せていたうえ、△医院から救急センターに向かう際のAの歩行は◇に片腕を支えられてのものであったとことを指摘しました。
しかも、Aは、△医院を1回目に受診して約2時間後には起座呼吸を必要とする呼吸困難の状態に陥った上、△医院への2回目の来院時は自力歩行をしていたが、その後ほどなくして救急センターへ向かう際は◇の補助により歩行する状態になっていたことが明らかであり、Aの症状は短時間のうちに急激に悪化していたと判示しました。
裁判所は、以上のAの症状に加え、呼吸、脈拍、血圧、体温、意識状態等のAのバイタルサインないし全身状態を注意深く観察していれば、いやしくも救急医療に携わる医師としては、Aを救急センターに搬送する途中において、同人が窒息状態に陥ることを高度の蓋然性をもって予測することはできないにしても、首の状態や体位如何により喉頭の完全閉塞を招くか、あるいは低酸素状態が進行して意識を喪失し呼吸停止の状態に落ちる等によって呼吸困難が急激に進行する可能性を否定することはできなかったというべきであると判示しました。
したがって、Aを救急センターに搬送するにあたり、場合によっては同人が搬送中呼吸困難の急激な進行により窒息状態に陥ることのあり得ることを予見できたものといえるから、医師として救急医療に携わっていた△医師は、Aのバイタルサインないし全身状態を十分に把握したうえ、これを予見すべきであったといわざるを得ないと判断しました。
そして、Aが搬送途中呼吸困難になり、低酸素症・高炭酸ガス血症になると、意識障害が進行し、自力での気道確保は困難となること(この時点が気管内挿管による気道確保の絶対適応である)、したがって、このような場合に気道を確保するためには医師の介助が必要であること、もっとも、普通の乗用車のように狭い車内では気道確保の処置をとることは困難であるが、救急車であれば可能であり、気管内挿管も救急車を停止させることでこれを実施することは可能であることが認められるとしました。そうとすれば、△医師は、Aを救急センターに搬送するにあたり、救急車を利用したうえ、Aが呼吸困難に陥ることをも予想して気管内挿管等の気道確保の措置をとることのできる準備をし、自らもしくは看護師を伴ってAに付添い介助するべきであったと判示しました。
裁判所は、以上によれば、△医師は、Aの呼吸障害に関する医療行為に関与した医師として、Aの2回目の受診時にバイタルサインの把握を怠ったうえ、同人の呼吸障害の重症度及び緊急度の判断を的確に行わず、その結果、同人を救急センターに搬送するにあたり、呼吸困難の急激な進行により同人が窒息状態に陥ることを予見し、救急車を利用するとともに、臨機応変に気道確保の措置が採れるよう準備し、同人に付添って介助すべきであったのに、これを怠り、自己が追尾もしくは先導したものの、Aの救急センターへの搬送を◇が運転する軽自動車に任せた点において、Aの死亡につき過失があるものといわざるを得ないと判断しました。
裁判所は、上記(裁判所の認容額)の範囲で◇らの請求を認め、この判決に対しては控訴がされましたが、控訴審で和解が成立して裁判は終了しました。