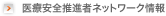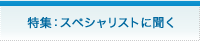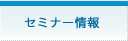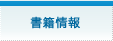名古屋高等裁判所 平成26年5月29日判決 判例時報2243号44頁
(争点)
- H医師が、各種検査を実施してAに膀胱癌が発症しているか否かを検索した上で、当該検査結果に応じた治療をすべき義務に違反したか
- Y病院の医師に診療契約上の説明義務違反があったか
(事案)
患者A(死亡当時77歳の男性)は、平成13年10月3日、Y医療法人が設置運営しているY病院内科を受診し、検査を経て巨大な膀胱結石及びこれに起因する両側水腎症、急性腎盂腎炎、慢性腎不全及び腎性貧血などを発症していると診断された。
Aは、同月15日、Y病院泌尿器科において、膀胱切石術及び膀胱瘻造設術(腹壁を通じて膀胱内に直接カテーテルを挿入し、排尿管理を行うことを目的とする尿路変更術)を受けた。Aの膀胱は、自然排尿が不可能な状況であったため、退院後も定期的にY病院泌尿器科を外来受診し、カテーテルの交換を受けるなどしながら膀胱瘻により排尿管理を行った。
その後Aは、膀胱結石を再発して平成15年7月4日に経尿道的膀胱結石破砕術を受けたほか、平成16年3月、7月とY病院内科に入院して細菌感染症や尿路感染症の治療を受けた。
Aは、平成16年12月6日、Y病院内科において左水腎症及び腎機能障害と診断され、その後、手術のためY病院泌尿器科に入院し、平成17年1月15日に経皮的左腎瘻造設術を、同月24日に左尿管皮膚瘻造設術を受け、退院した。
Yは、平成17年3月14日、右腎盂腎炎を発症して、Y病院泌尿器科に入院した。
Y病院泌尿器科に所属し、Aの主治医であったH医師は、同年4月4日、Aに対し、右尿管皮膚瘻造設術及び膀胱瘻閉鎖術(以下「右尿管皮膚瘻造設術等」という)を実施した。
Aは、左右の尿管皮膚瘻造設術の結果、膀胱を経由せず排尿管理がなされることとなり、膀胱に尿が流入することがなくなった。
Aは、右尿管皮膚瘻造設術等の後、膀胱瘻に設置したドレナージチューブから排膿が認められ、平成17年4月8日には膀胱瘻閉鎖術を実施した正中創(膀胱瘻)が離開し、同部位より排膿が認められた。
その後も死腔化した膀胱から排膿が続くとともに37.5度ないし38.5度の弛長型の発熱(一日の体温差が大きく変化する発熱の型)が続いた。H医師は、死腔化した膀胱が細菌に感染して炎症を起こしていると考え、排膿を検体として細菌培養検査を実施し、培養結果に応じた抗生剤をAに投与するなど炎症に対する治療を実施した。
また、Aは、右尿管皮膚瘻造設術等の後、定期的に膀胱洗浄を受けていたが、同年5月2日は膀胱洗浄後の排液に血液が混じっていることが確認された。その後も同月9日、11日、16日と膀胱洗浄の際、断続的に膀胱洗浄後の排液に血液、コアグラ、血餅などが混入していることが確認された。
H医師は、平成17年4月27日、Aに対し、膀胱造影検査及び骨盤腔部のCT検査を実施し、死腔化した膀胱の炎症部位を確認したが、明らかな膀胱腫瘍の所見を認めなかった。
H医師は、同年6月6日、Aの症状の原因と考えられる膀胱の炎症状態を確認するとともに、膀胱内の状況を確認するため、膀胱鏡検査、膀胱造影検査、骨盤腔部のCT検査を実施したが、膀胱鏡検査において腫瘍の存否や出血部位を検索することまではしなかった。当該CT検査及び膀胱造影検査の結果上、明らかな腫瘍の所見は認められなかった。
H医師は、Aの膀胱部の炎症に対する治療として各種抗生剤の投与等の保存的治療を実施していたが、治療効果が認められなかったため、これ以上保存的治療を実施しても症状の改善は見込めず、膀胱全摘術以外に症状を改善させる方法はないと考えるに至った。
H医師は、平成17年6月22日、A及びその子らに対し、これ以上の治療としては膀胱全摘術しかないと思われるが、同施術はリスクが高く生命に関係する手術となるため、実施可能な病院であるG病院を紹介するから直接そちらに依頼してほしい旨説明した。
H医師は、同月30日、G病院泌尿器科のT医師を訪れてAの治療方針を相談するとともに、G病院においてAに膀胱全摘術を実施してほしい旨依頼し、本人から依頼があれば実施可能である旨の回答を得た。
H医師は、同年7月6日、Aの子らに対し、T医師への相談を踏まえ、Aの全身状態が徐々に悪化していること、薬なしでは栄養状態及び貧血は改善せず、手術できるかどうか不明であることなどを説明し、膀胱全摘術を実施するか保存的にこのまま加療するか決めてほしいなどと述べた。
Aは、平成17年7月26日、子らを伴ってG病院泌尿器科を受診し、T医師の診察を受けた。T医師は、子らとAに対し、膀胱、特に前立腺と直腸との癒着が強いことから膀胱全摘術を実施すると直腸を損傷する可能性がかなり高く、そうなると人工肛門造設術が必要となって、現在の状況よりもQOLが低下する可能性が高い、現状を維持するより方法がない旨説明をした。
子ら及びAは、上記説明を受け、膀胱全摘術を受けることはせず、Y病院において保存的治療を継続することを希望した。
H医師は、同年9月2日にAを診察した際、左瘻孔部が肉芽状に増殖していることを認め、この時初めて腫瘍性病変の発生を疑ったが、当時のAの症状に照らし、保存的治療、対症療法以外に治療手段はないと考えた。
Aは、Y病院への入院を継続していたが、平成17年9月20日午前6時、膀胱部に生じた腫瘍からの大量出血が直接の原因で死亡した。
Aの子2名が、Y病院の担当医師が、膀胱洗浄の際の排液に血液が混入していることを確認した時点において、膀胱癌の発症を疑ってその検索及び鑑別をするための検査等を実施する義務があったのにこれを怠った過失によりAが死亡したとして、損害賠償請求訴訟を提起した。
一審判決(岐阜地方裁判所平成25年4月17日)が、H医師の検索治療義務違反を認め、Yに損害賠償を命じたため、Yが控訴した。
(損害賠償請求)
患者遺族(子2名)の請求額 : 2名合計4435万6568円
(内訳:患者の逸失利益985万6568円+遺族両名の慰謝料合計3000万円+葬儀費用150万円+遺族両名の弁護士費用合計300万円)
(判決による認容額)
一審(岐阜地裁)の認容額 : 2622万8282円
(内訳:(患者の逸失利益821万3807円+遺族両名の慰謝料合計3000万円+葬儀費用150万円)の60%相当額+弁護士費用240万円。端数不一致)
控訴審の認容額 : 2名合計1870万2221円
(内訳:患者の逸失利益550万2221円+遺族両名の慰謝料合計1000万円+葬儀費用150万円+遺族両名の弁護士費用合計170万円)
(裁判所の判断)
1.H医師が、各種検査を実施してAに膀胱癌が発症しているか否かを検索した上で、当該検査結果に応じた治療をすべき義務に違反したか
この点につき、控訴審裁判所は、まず、Aの膀胱腫瘍について、悪性であるとの確定診断はなされていないものの、死亡に至るまでの経過や良性腫瘍であったことを窺わせる事情がないこと(膀胱腫瘍の大半は悪性のものであることが認められる)からすれば、膀胱癌であったと認めるのが相当であると判示しました。
次に、控訴審裁判所は、膀胱腫瘍の最も重要な初期症状は血尿であり、その原因が膀胱の腫瘍部の血管が破裂、潰瘍、壊死等により損傷して出血することにあることからすれば、膀胱が死腔化しているAにおいても、平成17年5月2日行われた膀胱洗浄の際、その排液に血液が混入していたことは、膀胱癌が発症しており、そのために腫瘍部の血管が損傷して出血したものである可能性があることを示す事実であるというべきであると指摘しました。控訴審裁判所は、さらに、Aは平成13年以降巨大尿路結石や尿路感染などの既往があり、左右の尿管皮膚瘻造設術等の結果、膀胱が死腔化しているなど、膀胱癌のリスク要因があったこと、膀胱死腔炎では高い発熱はしないこと、右尿管皮膚瘻造設術等以降、膀胱分の炎症の治療として各種抗生剤の投与等を行っていたが、治療効果が認められなかったこと、平成17年5月2日に続けて、同月9日、11日、16日にも膀胱洗浄の際に血性排液がみられ、かつ、それらには血液のほか、コアグラ、血餅等が含まれていたものであり、これらの事実は、膀胱内部で一定量の出血及び凝血があったことを推認させることなどを考慮すれば、同月2日の時点においてはAの膀胱に癌があり、その腫瘍部の血管が損傷して出血していたものと推認するのが相当であると判断しました。
そして、控訴審裁判所は、上記のようなAの既往歴、右尿管皮膚瘻造設術等を施した以降の症状などからすれば、H医師としては、平成17年5月2日に膀胱洗浄を実施し血性排液を確認した時点において、Aに膀胱癌が発症していることを疑うべき契機が与えられたものであり、その後も、同月9日、11日、16日と膀胱洗浄の際にコアグラ、血餅等を含む血性廃液がみられたことからすれば、同月中旬頃までには、Aが膀胱癌に罹患しており、その腫瘍部の血管の破裂、潰瘍、壊死等による損傷によって出血したものである可能性を視野に入れて検査、診断等を行うことが求められ、適宜血性排液の細胞診、膀胱鏡検査、CT検査及びMRI検査等所要の検査を実施してAに膀胱癌が発症しているか否かを検索した上、当該検査結果に応じた治療を実施すべき義務(以下、「検索治療義務」という)を負っていたと解するのが相当であると判示しました。
その上で、控訴審裁判所は、しかしながら、H医師は平成17年5月2日に血性排液を確認した時点以後において膀胱癌を検索するために適切な検査を実施していないことから、H医師には検索治療義務の違反が認められると判断しました。
2.Y病院の医師に診療契約上の説明義務違反があったか
Yは、Aが、H医師の説明及び転医の勧めにもかかわらず、自らの判断で全摘術を拒否したのであり、Aが膀胱全摘術を受けていれば、感染症が進行することもなく、また、結果として膀胱腫瘍も発症することもなかったのであるから、Aの死亡について責任がない旨主張しました。
しかし、控訴審裁判所は、H医師は、Aが膀胱癌に罹患している可能性について言及しておらず、A及び子らは、Aに膀胱癌が発症している可能性を知らず、膀胱全摘術を実施すれば人工肛門の造設術を受けることが不可避であるとの理由で膀胱全摘術を拒絶したにすぎず、そこで与えられた選択肢は、このまま保存的治療を継続するか、又はQOLの低下を甘受して膀胱全摘術を受けるかというものであるにとどまり、生命の維持を可能にするため膀胱全摘術を受けるかどうかの選択肢は与えられていなかったと指摘しました。
その上で、控訴審裁判所は、仮に膀胱癌に罹患している可能性について説明がされていれば、Aにおいて、膀胱を全部摘出する覚悟もしなければ生命に対する危険が高まると認識し、人工肛門造設等の負担が生ずることとなるとしても、生存の確度を向上させるためQOLを犠牲にして膀胱全摘術を選択した高い蓋然性があるというべきであると判示しました。
さらに、控訴審裁判所は、Aは、自分が罹患している疾病(病名及び病状)について正確な説明を受けなかったものであり、これに対応する治療法の違い、利害得失等について分かりやすく説明を受けたものとは認められないから、H医師を含むY病院の医療従事者において説明義務を尽くしたということはできないと判断しました。
控訴審裁判所は、上記「控訴審の認容額」記載の損害賠償をYに命じる内容に、一審判決を変更しました。その後判決は確定しました。