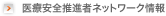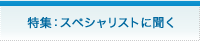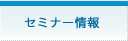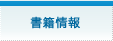最高裁判所第三小法廷 平成8年1月23日判決 判例タイムズ 914号106頁
(争点)
- Y2医師の過失の有無
- Y2医師の過失と患者X1の脳機能低下症発症との因果関係
(事案)
患者X1(昭和42年4月10日生、手術当時7歳)は、昭和49年9月25日午前0時30分頃、腹痛と発熱を訴えて、救急車でY1医療法人の経営するY病院に搬送された。X1は、Y病院の当直医によって経過観察の上加療を要すると診断されて入院したが、同日午後3時40分頃までに、X1は、Y病院の内科医であるA医師及び外科医であるY2医師の診察を受け、その結果、化膿性ないし壊阻性の虫垂炎に罹患しており、虫垂切除手術が必要であると診断された。
X1の両親であるX2、X3はX1の法定代理人として、同日、Y1医療法人との間で、虫垂切除手術(以下「本件手術」という)及びこれに付帯する医療処置を目的とする診療契約を締結し、Y2医師により本件手術が実施されることとなった。
同日午後4時25分、Y2医師は、介助者として看護師3名(U看護師長、M看護師、E看護師)、連絡係として看護補助者1名(S看護師)を配置し、X1を手術室に入れ、再度診察をした後、偶発症に備えて血管確保の意味で点滴を開始し、午後4時32分頃、X1の第三腰椎と第四腰椎の椎間にルンバール針を用いて、0.3%のペルカミンS(以下「本件麻酔剤」という)1.2mlを注入し、腰椎麻酔を実施した。
この麻酔実施前の午後4時28分のX1の血圧は112ないし68水銀柱mm(以下、単位は省略)、脈拍は78(毎分、以下同じ)であり、麻酔実施後の午後4時35分の血圧は124ないし70、脈拍は84で、いずれも異常はなかった。
Y2医師は、麻酔実施後X1の腹部を消毒し、麻酔高を確認した上、午後4時40分、執刀を開始した。この時点のX1の血圧は122ないし72、脈拍は78であった。なお、Y2医師は、M看護師に対して手術中常時X1の脈拍をとり5分ごとに血圧を測定して報告するよう、またU看護師長に対してX1の顔面などの監視に当たるよう、それぞれ指示した。
Y2医師は、マクバーネーの切開方法により開腹した後、腹膜を切開し、大網を頭側に押しやり、虫垂を切除しようとしたが、虫垂の先端は後腹膜に癒着して遊離不能であったため、逆行性の切除方法を採ることにした。
Y医師がペアン鉗子でX1の虫垂根部を挟み、腹膜のあたりまで牽引した午後4時44、5分頃、急にX1が「気持ちが悪い」と悪心を訴え、それとほぼ同時にM看護師が、脈が遅く弱くなったと報告した。そこで、Y2医師は、直ちに虫垂根部をペアン鉗子で挟んだまま手を離し、「どうしたぼく、ぼくどうした」とX1に話しかけたが返答はなく、顔面は蒼白で唇にはチアノーゼ様のものが認められ、呼吸はやや浅い状態で意識はなかった。この時点で、M看護師から、血圧は触診で最高50であるとの報告があった。
午後4時45分頃、本件手術は中止された。
Y2医師は、E看護師に傷口をガーゼで保護するよう指示し、自ら手術台を操作してX1をトレンデレンブルグ体位に変えながら、看護補助者のS看護師を大声で呼び、外科部長のY3医師及び外科医のB医師に患者の容態が急変したのですぐに来てほしいと電話で連絡するよう指示し、トレンデレンブルグ体位にした後、左手でX1の気道を確保しながら酸素マスクが顔面に密着するよう押し付け、酸素が毎分4リットルの割合で流れるように調節した上、右手でバグを握縮加圧して、X1の自発呼吸に合わせて気管内に酸素を圧入したが、次第にバグの加圧に抵抗が生じて酸素の入りが悪くなった。Y2医師は、この操作を行いながらM看護師に指示して、昇圧剤メキサン1アンプルを点滴器具の三方活栓から急速に静注させ、別のU看護師長に指示して、カルジオスコープの電極をセットさせ、心電図のモニターによる監視を開始させた。モニターの波形はかなり不規則で心室性の期外収縮が見られ、低電位であったが、心室細動はなかった。X1は漸次自発呼吸がなくなっていった。
午後4時46分ころ、Y3医師はS看護師からの電話連絡で直ちに手術室に駆けつけた。この時点で、X1の自発呼吸はほとんどなく、モニターの波形は不規則、低電位であり、心室細動に移行する前段階の状態を呈していた。Y3医師は、Y2医師から状況の報告を受けた後、M看護師に副腎皮質ホルモン剤ソルコーテフ100mgの静脈急注とノルアドレナリン1アンプルの点滴液内の混注を指示し、自らは経胸壁心臓マッサージ(心マッサージ)を実施した。
Y3医師が到着してから約1分後にB医師も到着し、緊急処置に加わった。B医師は、Y2医師からバグの加圧に抵抗があることを聞き、気管内チューブの気管内挿管を実施し、Y2医師はY3医師と交代して心マッサージを行った。
しかし、X1は、午後4時47、8分頃、心停止の状態に陥った。Y3医師は、再びY2医師と代わって心マッサージを行うと共に、直接心臓腔内にノルアドレナリン1アンプルを注射した。また、B医師が酸素の送入に苦労しているのを見て、聴診器でX1の肺を聴診したところ、喘息様の音が聞かれたため気管支痙攣によるものと判断し、気管支拡張のため、M看護師にボスミン2分の1アンプルの右上膊部筋注を指示した。
午後4時55分少し前、ようやくX1に心拍動が戻り、間もなく自発呼吸も徐々に回復し、午後4時55分の血圧は90ないし58、脈拍は120となり、以後は血圧、脈拍共に安定したが、X1の意識は回復しなかった。
午後5時20分、Y2医師は、本件手術を再開し、虫垂を逆行性に切除した。虫垂は先端が根部の倍くらいに腫れており、色は赤黒く、先端付近に膿苔が付着して化膿性虫垂炎の症状を呈していた。
午後5時42分、手術は終了した。
X1は、その後N大学附属病院、国立G病院、I温泉病院等に入院して治療を受け、昭和50年6月22日からは自宅療養を続けているが、病態の改善は見られず、現在は、脳機能低下症のため、頭部を支えられた状態のもとで首を回すことができるだけで、発作的にうなり声、泣き声を発し、発語は一切なく、小便は失禁状態、大便は浣腸のみで排便し、固形物の摂取は不可能で、半流動物を長時間かけて口の中に運んでやらなければならない状態であって、この状態は将来にわたり継続する見込みである。
そこで、X1と両親であるX2、X3は、Y1医療法人、Y2医師、Y3医師に対し、診療契約上の債務不履行または不法行為を理由として、損害賠償請求訴訟を提起した。
第1審(昭和60年5月17日名古屋地裁判決)は、Y2医師の医療行為には何らの注意義務違反も認められないから、その余の事実について判断するまでもなく、X1らの請求には理由がないと判示して、X1らの請求を棄却したため、X1らは控訴した。
第2審(平成3年10月31日名古屋高裁判決)も、Y2医師及びY3医師には過失が認められないか、またはY2医師に注意義務違反が認められるにしても、それとX1の脳機能低下症との間に因果関係が認められないと判示して、X1らの控訴を棄却したため、X1らは上告した。
(損害賠償請求)
患者及び両親の請求額 :一審及び控訴審 9398万4264円
(内訳:患者の逸失利益2921万3352円+患者の看護料4037万0912円+患者の慰謝料1000万円+患者の両親の慰謝料各500万円+弁護士費用440万円)
(判決による認容額)
裁判所の認容額 :一審及び控訴審 0円
最高裁判所 Y1医療法人とY2医師につき、患者敗訴の判決を破棄差戻
(裁判所の判断)
1.Y2医師の過失の有無
この点について、裁判所は、過去の最高裁判例を引用して、次のように判示しました。
「人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、業務の性質に照らし、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求されるのであるが、具体的な個々の案件において、債務不履行又は不法行為をもって問われる医師の注意義務の基準は、一般的には診療当時のいわゆる臨床医学の実践における医療水準である。この臨床医学の実践における医療水準は、全国一律に絶対的な基準として考えるのではなく、診療に当たった当該医師の専門分野、所属する診療機関の性格、その所在する地域の医療環境の特性等諸般の事情を考慮して決せられるべきものであるが、医療水準は医師の注意義務の基準(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行と必ずしも一致するものではなく、医師が医療慣行に従った医療行為を行ったからといって、医療水準に従った注意義務を尽くしたと直ちにいうことはできない。」
そして、裁判所は、本件麻酔剤の能書には、「副作用とその対策」の項に血圧対策として、麻酔剤注入前に1回、注入後は10ないし15分まで2分間隔に血圧を測定すべきと記載されているところ、原判決(控訴審)は、能書の上記記載にもかかわらず、昭和49年ころは、血圧については少なくとも5分間隔で測るというのが一般開業医の常識であったとして、当時の医療水準を基準にする限り、Y2医師に過失があったということはできない、と判示しました。その上で、裁判所は、しかしながら、医薬品の添付文書(能書)の記載事項は、当該医薬品の危険性(副作用等)につき最も高度な情報を有している製造業者又は輸入販売業者が、投与を受ける患者の安全を確保するために、これを使用する医師等に対して必要な情報を提供する目的で記載するものであるから、医師が医薬品を使用するに当たって能書に記載された使用上の注意事項に従わず、それによって医療事故が発生した場合には、これに従わなかったことにつき特段の合理的理由のない限り、当該医師の過失が推定されるものというべきであると判断しました。
その上で、裁判所は、本件麻酔剤を投与された患者は、ときにその副作用により急激な血圧低下を来し、心停止にまで至る腰麻ショックを起こすことがあり、このようなショックを防ぐために、麻酔剤注入後の頻回の血圧測定が必要となり、その趣旨で本件麻酔剤の能書には、昭和47年から前記の記載がなされていたということができ、他面、2分間隔での血圧測定の実施は、何ら高度な知識や技術が要求されるものではなく、血圧測定を行い得る通常の看護師を配置してさえおけば足りることから、本件でもこれを行うことに格別の支障があったわけではないのであるから、Y2医師が能書に記載された注意事項に従わなかったことに合理的な理由があったとはいえないと判断しました。
裁判所は、すなわち、昭和49年当時であっても、本件麻酔剤を使用する医師は、一般にその能書に記載された2分間隔での血圧測定を実施する注意義務があったというべきであり、仮に当時の一般開業医がこれに記載された注意事項を守らず、血圧の測定は5分間隔で行うのを常識として実践していたとしても、それは平均的医師が現に行っていた医療慣行にすぎず、これに従った医療行為を行ったというだけでは医療機関に要求されたる医療水準に基づいた注意義務を尽くしたということはできないと判示し、Y2医師の過失を認めました。
2.Y2医師の過失と患者X1の脳機能低下症発症との因果関係
この点について、裁判所は、X1には本件手術当時の午後4時32分頃、本件麻酔剤が注入されたが、Y2医師は看護師に手術中5分ごとに血圧を測定するよう指示したのみであったため、執刀を開始した午後4時40分の時点で血圧が測定された後は、午後4時44、5分頃、X1の異常に気付くまで血圧は測定されなかったところ、X1は虫垂根部の牽引を機縁とする迷走神経反射が起こる前に、午後4時40分直後から血圧低下の傾向にあり低酸素症の状態になっていたというのであるから、午後4時42分ないし43分ころに、すなわち、2分間隔でX1の血圧を測定したとしてもX1の血圧低下及びそれによる低酸素症の症状を発見し得なかったとは到底言い得ない筋合いであると判示しました。更に、裁判所は、X1の血圧低下を発見していれば、Y2医師としても、これに対する措置を採らないまま手術を続行し、虫垂根部を牽引するという挙に出ることはなかったはずであり、そうであれば、虫垂根部の牽引を機縁とする迷走神経反射とこれに続く徐脈、急激な血圧降下、気管支痙攣等の発生を防ぎ得たはずであると判断し、従って、本件麻酔剤を使用するに当たり、能書きに記載された注意事項に従わず、2分ごとの血圧測定を行わなかったY2医師の過失とX1の脳機能低下症発症との因果関係を肯定せざるを得ないと判断しました。
そして裁判所は、これと異なる原審の判断には、過失及び因果関係についての解釈適用を誤り、ひいては審理不尽、理由不備の違法があるというべきであり、この違法は原判決中Y2医師、Y1医療法人に関する部分の結論に影響を及ぼすことが明らかであるとして、原判決中、Y2医師及びY1医療法人に関する部分についてはこれを破棄し、X1らに生じた損害等も含め更に審理を尽くさせるために原審に差し戻しました。Y3医師に関する部分については、Y3医師の採った措置に過失があったとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができるとして、上告を棄却しました。