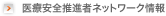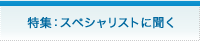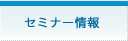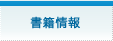名古屋高裁平成19年10月17日判決 判例タイムズ1278号264頁
(争点)
- 医師に過失はあったか
- 治療によって患者の死亡を回避できたか
- 損害(入院雑費)
(事案)
患者A(死亡当時19歳の男子大学生、以下、A)は、平成8年以降過去3回、Y1市が開設・運営しているY病院小児科において、胃腸炎及び腸閉塞(以下、イレウス)で入院していた。
Aは、平成13年9月30日、朝から腹痛を訴え、その後数回嘔吐したため、同日午後7時25分、Y病院の救急外来を受診した。同病院内科の当直医であったB医師は、Aを診察し、腹部が膨張していたこと、グル音が弱かったこと、筋性防御反応がなかったこと及びレントゲン撮影の結果を総合して、Aが単純性イレウスに罹患していると判断し、同病院に入院させた。
同年10月1日午前8時30分ころ、同病院の内科医のY2医師はB医師からAがイレウスによる入院したことの引き継ぎを受けた。
同日午後1時20分の時点で、Aは「いたーい」と訴え、腹満が著明で、苦痛表情があり、顔面はやや蒼白で、脈拍は140/分、体温37.2℃となっていた。Y2医師は、同日午後1時30分ころ、Y病院の透視室にて、Aに対し、イレウス管チューブの挿入を試みたが、チューブを十二指腸側に進めることができなかったことから、イレウス管を胃内に留置した状態で鼻に固定した。
Y2医師は、同日午後3時45分ころ、再度Aにイレウス管チューブの挿入を試み、応援医師の協力を得て、挿入を終えた。
しかし、Aは、挿入が完了した同日午後5時15分ころ、Y2医師に対し「息苦しい」と訴え、唇にチアノーゼが認められ、意識は朦朧とし、眼球の拳上も認められた。そこでAは集中治療室に搬送され、治療が試みられたが、Aは、同月3日午前7時17分、多臓器不全により死亡した。
Aの死亡後、剖検が実施されたが、その結果、バウヒン弁から80㎝口側の回腸にメッケル憩室があり、絞扼性イレウスが認められ、さらに、多臓器不全と播種性血管内凝固症候群(以下、DIC)に陥っており、瀰漫性肺胞障害、肝の小葉中心性壊死、急性尿細管壊死及び腸管の粘膜出血が認められた。
なお、イレウスは、腸管の器質的病変を伴う機械的イレウスと、伴わない機能的イレウスに分類され、さらに機械的イレウスは、腸間膜の血行障害を伴わない単純性イレウスと、それを伴う絞扼性イレウスほかに分類される。そして、絞扼性イレウスは、腸管虚血及び壊死をきたす原因疾患の一つであり、罹患すると、腹膜炎、DIC、ショック及び多臓器不全などを併発し、死亡に至ることも少なくないため、早期診断に基づく適切な治療が本疾患の予後改善に不可欠とされている。
その後、Aの両親で遺族であるX1とX2(以下、Xら)は、Y病院のY2医師が過失によりAに適切な治療を行わなかったためAが死亡したと主張し、Y2医師及び使用者であるY1に対し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償を請求して訴えを提起した。
第一審裁判所は、絞扼性イレウスかどうかの確定的判断を下すため、Y2医師にはCT検査の実施を決断すべき注意義務があったが、Y2医師はこれを怠った、として過失を認め、上記第1審の認容額の限度でXらの請求を認めた。Y1市及びY2医師が控訴した。
(損害賠償請求額)
遺族ら(患者両親)の請求額:計9241万5890円
(内訳:入院雑費6400円+葬祭費502万0361円+逸失利益5398万9129円+慰謝料2500万円+弁護士費用840万円)
(判決による請求認容額)
裁判所の認容額:【第一審の認容額】計7114万9827円
(内訳:入院雑費5200円+葬祭費120万円+逸失利益4344万4627円+慰謝料2000万円+弁護士費用650万円)
【控訴審の認容額】計7110万4627円
(内訳:入院雑費0円+葬祭費120万円+逸失利益4344万4627円+慰謝料2000万円+弁護士費用646万円)
(裁判所の判断)
医師に過失はあったか
この点について控訴審裁判所は、まず、Aは、(1)既往歴として、手術既往がないにもかかわらず過去3回イレウスで入院しており、平成13年9月30日の入院で4回目の入院であったこと、(2)白血球数は、入院時点で絞扼性イレウス診断の目安とされる値(1万/μl超過)を上回る1万2900/μlであったこと、(3)グル音は、入院時点の同日午後7時25分から弱く、同日午後8時10分ころ、翌10月1日午前0時ころ及び同日午前8時50分ころのいずれにおいても確認されていないこと、(4)鎮痛剤の複数回投与にもかかわらず、強い持続的腹痛が著明であったこと、(5)脈拍は、入院当初は70回/分で、翌10月1日午前6時30分ころは84回/分であったが、同日午前8時50分過ぎころは126回/分で頻脈を呈し、同日午後1時20分ころは140回/分とさらに増加していること、(6)体温は、絞扼性イレウス診断の目安は37℃超過であるところ、入院当初は36.7℃であったが(ただし、看護記録上は37.1℃)、翌10月1日午前6時30分は37.1℃、同日午前8時50分過ぎころは36.7℃となったが、同日午後1時20分には37.2℃に上昇していることが認められる、と認定しました。
そして、以上の診断結果、身体的所見、検査所見に、医療上の知見を併せ考えると、Aの診療を担当する医師としては、これまでの既往歴からして、保存的治療が4回目になる場合であるから手術の適応と考えるべきであったところ、当初から白血球数増多という絞扼性イレウスの発症を疑うべき所見があったほか、絞扼による腸管運動の低下も推察され、鎮痛剤の効果も乏しいほどの強い腹痛が持続し、頻脈、発熱などの所見も認められたのであるから、これらの所見を総合判断すれば、遅くとも10月1日午後1時20分の時点において、絞扼性イレウスの発症を疑うべき根拠があったものとして、直ちに開腹手術を決定し、その実施準備に着手すべき義務があったというべきである、と判示しました。
そして、Y2医師は、この開腹手術決定義務があったにもかかわらず、これを怠り、イレウス管の挿入を試みるなどしたのみで、開腹手術を決定しなかったのであるから、Y2医師の診療行為には、この点において診療上の注意義務違反があり、過失があった、と判示しました。
治療によって患者の死亡を回避できたか
この点について控訴審裁判所は、平成13年10月1日午後1時20分ころに、Y2医師がAに対し開腹手術を実施することを決定していたならば、Aが一時ショック状態に陥る前の同日午後3時45分ころまでに開腹手術を開始することができたものと認められ、同時刻までに開腹手術を実施することによってAの死亡を回避する蓋然性が十分あったということができる(なお、同日午後1時20分ころに開腹手術を決定していれば、手術前措置等によりAの全身管理がなされるなどして、Aがショック状態に陥ったとしても速やかに対応がなされたものと推認されるし、また、本件でY2医師が行ったイレウス管の挿入と失敗という経過がなかったならば、Aがショック状態に陥った時刻はさらに遅くなったものと考えられる)、と判示し、結果回避可能性(治療によりAの死亡を回避できたこと)を認めました。
損害(入院雑費)
この点について、第一審裁判所は、Xが主張する入院雑費を損害として認めました。しかし、控訴審裁判所は、Aは、平成13年9月30日から死亡する同年10月3日までの間、Y病院に入院していたが、入院当初から単純性イレウスと診断され、遅くとも同年10月1日午後1時20分の時点において、絞扼性イレウスの発症を疑うべき根拠があったものと認められるから、Y2医師の過失がなくとも相当期間入院治療を余儀なくされたものと認められる。したがって、Aの入院雑費とY2医師の過失との間に相当因果関係は認められない、と判示し、この部分についての第一審裁判所の判決を変更して、遺族の請求を棄却しました。
以上から、控訴審裁判所は第一審の判決を変更した上で、上記【控訴審の認容額】の範囲でXらの請求を認めてY1、Y2の控訴を棄却しました。