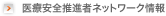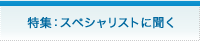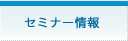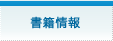福岡高等裁判所平成18年7月13日 判例タイムズ1227号303頁
(争点)
- 患者を移送した病院の医師(前医)に過失が認められるか
- 患者の移送を受けた病院の医師(後医)に過失が認められるか
- 前医の過失及び後医の過失それぞれについて患者の死亡という結果との間に因果関係が認められるか
- 損害を減額すべき事情の有無
(事案)
患者A(昭和26年生まれの消防士の男性)は、平成12年5月23日午後3時ころ、勤務中に右膝を負傷した。同日夕刻、Y1市の開設するY1病院救急外来を受診し、同病院に勤務する整形外科医のB医師の診察を受け、B医師の執刀により、局所麻酔下で異物を摘出する手術(本件手術)を受けた。
同月25日、Aは再びY1病院を受診し、手術創の痛みを訴えてY1病院に入院した。 その後、手術創の痛みは軽快に向かっていたが、同月31日午後7時ころ、Aは看護師に対して、シャワーの使用後に胸が苦しむと訴えた。6月1日午前5時30分ころ、Aはトイレから病室に戻る際に、意識を消失して廊下で転倒した。すぐに、Aは意識を取り戻したものの、胸苦しさ、息苦しさを訴え、チアノーゼが認められた。午前6時ころ、当直の整形外科医C医師の指示により、Aに心電図モニターが装着された。午前8時30分ころ、C医師から引き継いだB医師は、Aを診察し、緊急に処置しなければならない状態ではないと判断し、午前9時ころ循環器内科勤務医のD医師に診断を依頼し、午前6時以降に実施された心電図検査の結果とAが以前、(心室性)期外収縮を指摘されたことがある旨の2点を申し送った。その上で、D医師は、午前9時10分ころ、Aを診察した。
D医師は、診察した際の患者Aの症状や心電図所見から「急性冠不全症」又は「急性心筋梗塞」を疑って、高次医療機関での精密検査及び加療が必要であると診断し、同日午前9時30分ころ、Y2が開設するY2病院に対しAの受け入れとドクターカーの出動を要請した。上記診断に際し、D医師は、本件手術が施行されたことを既に認識していたが、肺塞栓症の疑いを持たなかった。
患者Aの搬出手続の際、D医師はY2病院の循環器内科のE医師に対し、Aの症状、これまでの措置、心電図検査の結果にT波逆転があり、急性冠症候群又は急性心筋梗塞が考えられるなどを説明し、診療情報提供書を交付した。E医師は、Y2病院到着後すぐにAを診察するとともに、血液検査及び心電図検査、緊急冠動脈造影検査を実施し、冠れん縮性狭心症と診断した。同日午後1時10分頃、AはY2病院に入院した。
6月2日午前6時50分ころ、Aは気分不良を訴えると意識を消失するようになり、午前7時25分ころ、E医師において、Aの心エコー検査を実施した結果、右心室拡張が著明で、心室中隔の奇異性運動が認められた。E医師はこの時点で初めて肺塞栓症を疑い、肺動脈造影検査のため血管造影室に移動させようとした際、Aの症状が急変し、呼吸停止や高度の除脈が発現した。以後、蘇生措置を尽くしたが、Aは4日午前6時24分に死亡した。Aの直接の死亡原因は、肺塞栓症である。
患者Aの妻X1とAとの間の子であるX2~X4が、D医師及びE医師が肺塞栓症を疑うことなく、漫然と心疾患と診断して、肺塞栓症の適切な治療せず、これによりAが死亡したとして、不法行為責任に基づき、両医師が勤務するY1市と法人Y2に対して損害賠償請求訴訟を提起した。
(損害賠償請求額)
患者の遺族の請求額:妻子合計9564万8095円
内訳:不明
(判決による請求認容額)
裁判所の認容額:妻子合計4630万4754円
内訳:患者固有の損害額4080万4756円((逸失利益4400万7928円+死亡慰謝料2400万円)から4割減額)+患者の遺族の損害額(葬儀費用150万円+弁護士費用400万円。端数不一致)
(裁判所の判断)
患者を移送した病院の医師(前医)に過失が認められるか
裁判所は、まず、患者Aの肺塞栓症の発症時期及びその原因について、Aは5月31日の1、2日前から肺塞栓症を発症していたものということができ、どんなに控えめに見ても6月1日早朝の意識消失等はまさに肺塞栓症によるものであると認定しました。
そして、D医師が、Aの6月1日の意識消失等を虚血性心疾患によるものであると診断したのは、客観的には誤りであったと認定しました。
しかし、当時の医学的見地からは、症状や心電図だけで肺塞栓症であると鑑別することは極めて困難であり、D医師に肺塞栓症と診断することを期待することは無理であったとしました。その一方で、肺塞栓症が可及的速やかな確定診断と治療開始を要し、これを怠れば、死亡率が相当高くなる疾患である点を指摘し、Aの症状、Aの意識消失等これに対する措置等の経過、また心電図検査の結果等の所見を得たD医師としては、6月1日午前9時ころ、少なくともAが肺塞栓症に罹患しているのではないかとの疑いを持つべきであったと指摘しました。そして、肺塞栓症の疑いを持った医師としては、(1)肺塞栓症罹患の有無について確定診断をするため、心エコー検査や肺動脈造影又は肺換気・肺血流スキャンの各検査を実施するか、(2)上記確定診断ないし所要の治療を得るため、しかるべき高次医療機関に患者を移送するかしなければならないとしました。そして、(2)の措置をする場合、高次医療機関が(1)の諸検査に円滑にとりかかり、適時適切な診療・治療ができるようにするために、少なくとも、肺塞栓症に罹患しているのではないかと疑いを持っていることを高次医療機関に対して申し送るべき注意義務があると判示しました。
しかしながら、D医師は、Aが肺塞栓症に罹患しているのではないかとの疑いを全く持つことがなかったため、これらの措置をとり得ることもなく、Y2病院に対し、Aの受け入れとドクターカーの出動を要請する際、Y2病院に対して、肺塞栓症の疑いに申し送りすることもなかったことから、D医師には、上記注意義務に違反した過失があると判示しました。
患者の移送を受けた病院の医師(後医)に過失が認められるか
裁判所は、E医師は、患者Aに対する診療を引き継いでから、同月2日午前7時25分ころまで肺塞栓症を全く疑っていなかったのであるから、同時点に至るまでのE医師の診断も客観的には誤りであったことを認定しました。
そして、本件では、E医師がAについて肺塞栓症を疑わなかったことについては、前医であるD医師の誤診が影響を及ぼしているとしても、後医としては、前医の診断とは別に、自主的に診断をすべきなのは当然であると判示しました。更に、肺塞栓症は可及的速やかな治療開始が大原則とされているのであるから、D医師から客観的には誤った診断結果を提供されたものの、Y1病院におけるAの症状や心電図検査の結果には肺塞栓症と矛盾するものはなく、むしろ、症状の発現に先立ち本件手術を受けていること、肥満体であることなど、肺塞栓症の誘因となり得るような要素の情報も把握していたのであるから、D医師の上記診断結果にもかかわらず、遅くとも、6月1日午後10時ころの時点において、肺塞栓症の疑いを持つことが可能であったし、かつ、そうすべきであったと認定しました。
しかし、E医師は、肺塞栓症を鑑別対象に入れることは6月2日朝に至るまでなかったというのであるから、この点につき、E医師には上記注意義務に違反した過失があると判示しました。
前医の過失及び後医の過失それぞれについて患者の死亡という結果との間に因果関係が認められるか
(1)E医師(後医)の過失と患者Aの死亡との因果関係について
患者Aは、6月1日午後10時ころの時点では、血圧が安定しており、その時点で、肺塞栓症を鑑別対象とした検査を更に実施し、肺塞栓症との診断結果が得られれば、十分に救命は可能であったということができることから、E医師の過失と患者Aの死亡との間に相当因果関係が認められると判示しました。
(2)D医師(前医)の過失と患者Aの死亡との因果関係
E医師による診療は、前医であるD医師から引き継ぎを要請された後医としてなされたものであり、しかも、D医師は、過失により、E医師に客観的には誤った情報を提供していたこと、それがE医師の過失の誘因となったことは否定できないことから、E医師の過失の存在により、D医師の過失とAの死亡との間の因果関係が直ちに切断されることにはならないと判示しました。
更にD医師からの要請に基づいてAの緊急搬入に応じたE医師にとっては、時間的制約のもとで、患者の診療情報を得るため、情報提供書に頼らなければならず、E医師がもっぱら心疾患を念頭に置いた検査・治療に偏ることになったのは、情報提供書にD医師の診断結果として急性冠症候群、急性心筋梗塞の疑いと記載されていたからであるから、D医師の過失がE医師をして同医師自身が負っていた注意義務違反を惹起させたものと評価でき、D医師の過失とAの死亡との間にも相当因果関係を認めることができると判示しました。
(3)病院間の責任原因
裁判所は、Y1病院のD医師とY2病院のE医師は、互いに一方が他方のした医療行為そのものに共同して従事したわけではないが、D医師とE医師の各過失は、前医の要請に基づいて後医に対して患者Aの診療が引き継がれた一連の過程において存在したものである上、各過失のいずれについてもAの死亡との間の相当因果関係が認められることからすれば、両病院は共同不法行為者として、連帯して、上記各不法行為に基づく損害賠償義務を負担するものというべきであるとしました。
損害を減額すべき事情の有無
そして、患者の損害額の認定に当たり、Aのように心室性期外収縮の診断を受けたことのある患者においては、肺塞栓症の診断は特に困難であること、D医師がY2病院へ移送を決断したこと自体は相当であったといえること、またE医師がAを受け入れてから1日も経たないうちに容態が急変していること等の事情を考慮するならば、上記のとおり、D医師及びE医師がともに過失責任を免れないとしても、直ちに全責任を負わせるのは酷であるから、結果に寄与した患者Aの素因ないしは被害者(患者)側の事情として考慮し、上記不法行為と相当因果関係を有する損害額を一定の割合で減額するのが相当であるとし、患者の損害額を4割減額しました。
その上で上記のとおりの判決を言い渡しました。